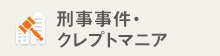民事訴訟法
- 複数の人が訴訟の当事者になる場合
-
第11編 請求の複数化に対する基本的規律
第1 複数請求訴訟に対する規律を理解する視点
1 訴訟手続の基本単位
⇒ 1人の原告が1人の被告に対して,審判対象たる訴訟物が単一1個であることを基本単位として組み立てられている!!
2 複数請求訴訟制度の趣旨
メリット デメリット ① 関連紛争の同時解決による効率性 ② 当事者の訴訟追行上の負担の軽減
③ 矛盾判断の回避
①審理が複雑化 ②訴訟遅延を招く
*メリット①ないし③は,弁論・証拠調べが共通の判断資料になることに由来
⇒ 複数請求訴訟の制度趣旨は,メリットとデメリットを調和させる点にある
3 原始的複数と後発的複数
原始的複数⇒要件緩やか
後発的複数⇒独自の要件充足が必要(∵相手方の防御上の利益)
第2 請求の客観的併合
1 意義
固有の意味の請求の客観的併合とは,当初から数個の請求について併合審理される状態をいう
*固有の意味とは,当事者複数の主観的併合を除く趣旨
⇒ 同一当事者間の複数の請求を典型例として挙げている!!
2 併合要件
視点 ①関連紛争の同時解決により効率性を高め,②当事者の訴訟追行上の負担を回避し,③訴訟経済を図りつつ,④審理の複雑化をせず,⑤混乱による訴訟遅延を防止する最大公約数とは何か
*併合要件[1]
① 数個の請求が同種の訴訟手続により審判されるものであること
② 法律上併合が禁止されていないこと
⇒特に,行訴法16条1項が立法政策として注目される!!
③ 各請求について受訴裁判所に管轄権があること
3 併合の態様と審判
(1) 単純併合
ア 定義
単純併合とは,法律上関連性がない数個の請求を並列的に併合する場合をいう
イ 典型例
相互に関連性がある場合 相互に関連性がない場合 ①土地明渡請求と明渡しまでの賃料相当損害金を併合する場合(附帯請求) ②物の引渡請求とその執行が将来的に不能な場合に備えてなされる損害賠償請求との併合(代償請求)
①売買代金請求と貸金返還請求を併合したような場合 (2) 予備的併合
ア 定義
予備的併合とは,法律上両立しない数個の請求に順位を付し,先順位請求が認容されることを解除条件として,後順位請求を併合する場合をいう
⇒ 主位的請求が認容されると条件が成就して予備的請求についての訴訟係属は失われる!!
イ 制度趣旨
順位を付すことで主張の矛盾を回避し,統一的かつ効率的な紛争解決
ウ 典型例
売買契約の有効を前提に主位的に売買代金を請求するとともに,売買契約が無効と判断されることに備えて,売買契約の無効による原状回復請求として引き渡した目的物の返還を予備的に請求する場合
(3) 選択的併合
ア 定義
選択的併合とは,同一の目的を有し,法律上両立しうる数個の請求を,その1つが認容されることを解除条件として他の請求を併合する場合をいう
⇒ 1つの請求を認容する限り,残りの請求は訴訟係属を失う!!
イ 制度趣旨
二重に給付を命じることが不合理な場合にこれを回避するため
ウ 典型例
所有権と占有権に基づく同一物の引渡しを請求する場合,所有権に基づく建物の明渡請求と賃貸借契約に基づく同一建物の明渡請求,債務不履行と不法行為に基づく損害賠償請求など
4 弁論の併合・分離
(1) 意義(152条1項)
手続裁量の考慮要素)
① 被告の負担軽減になるか
② 紛争解決の統一性確保に意味があるか
③ 審理効率の向上があるか
(2) 弁論の併合
ア 定義
弁論の併合とは,同一の訴訟法上の裁判所又は官署としての裁判所に別々に係属している数個の請求を同一訴訟手続内で審判すべきことを命じる措置をいう
イ 効果
請求の客観的併合
ウ 実施された証拠調べの結果の弁論後の取扱い
問題の所在 弁論が併合された場合,併合前に各々の事件において実施された証拠調べの結果は併合後にどのように扱われるべきか。特に,当事者が異なる主観的併合の場合に問題となる
● 当事者の援用を要すると解すべき
∵① 証拠調べに関与する機会がないままの証拠が自己の訴訟事件の事実認定に用いられるという事態は,当事者にとって不意打ち
② 当事者の手続保障
③ 併合前の訴訟は併合後も別訴訟たる性質を失わない
×① 弁論の併合制度の趣旨を重視すべき
② 援用を必要とすると,証拠資料が分断してしまう
③ 併合後に利用可能な証拠とそうでない証拠が混在して混乱する
④ 証拠共通の原理からしても自由心証からも妥当ではない
○ 併合前の証拠資料は併合後の当事者の関係においても同一の性質のまま証拠資料となる
⇒ 152条2項は,41年判例を前提に,併合後の当事者に尋問機会のなかった承認に対する尋問権を保障するという立法政策を採用
(3) 弁論の分離
弁論の分離とは,数個の請求について併合審理を解いて,ある請求を別個の手続において審判すべきことを命じる措置をいう
第3 訴えの変更
1 意義
(1) 請求の趣旨又はその原因の変更
ア 定義
訴えの変更とは,訴訟係属中に原告が当初の訴えによって申し立てた審判の事項を変更することをいう
イ 訴えの変更の典型例
請求の趣旨のみの変更例 請求の原因のみの変更例 特定の請求権の確認訴訟から給付訴訟に変更する場合 原告が被告に対して貸金元金の返還請求の訴えを提起して審理がされていたところ,同額でありながらも契約日を異にする別の貸金返還請求権を有する場合に,前者から後者に変更する場合 (2) 請求の拡張と縮減
請求の拡張⇒訴えの変更
請求の縮減⇒一部取下げと解すべき(∵明示的一部請求論)
*実務では,「一部取下げ」と理解し,被告が同意しない場合は「一部放棄」をさせる
(3) 追加的変更と交換的変更
ア 交換的変更
(ア) 定義
交換的変更とは,旧請求に代えて新請求を定立することをいう
(イ) 法律構成
○ 旧訴取下げ+新訴提起の複合行為
×① 訴えの取下げは訴訟係属の遡及的消滅をもたらす
② 訴訟資料を新請求に流用できない
③ 旧訴提起によって生じた時効中断効が維持できない
④ 同意がないと交換的変更ができない
* 判例は,単に,「旧請求につき撤回する」と述べたにすぎない場合は,『追加的変更』があったものとする[2]
* 判例は,交換的変更があった場合の時効中断効の維持を認めている
* 判例は,被告が交換的変更後の新請求に異議なく応訴した場合は旧請求について黙示の同意があったものと解している
イ 追加的変更
(ア) 定義
追加的変更とは,旧請求を維持しつつ新請求を定立することをいう
(イ) 機能
交換的変更 追加的変更(多用される!!) 旧訴の提起内容が明白に誤りであったとか証拠上肯認できないことが明白な場合に誤りを自認する場合の「補正」的手段として利用されるにとどまる 争点及び証拠の整理を経ることによって,請求そのもの,あるいは請求原因の修正変更をする必要が生じた場合に利用される 2 要件
(1) 制度趣旨
原告の迅速な権利救済への便宜と訴訟経済を図るというメリットと被告の防御上の不利益というデメリットを調和させる点にある
(2) 要件
① 請求の基礎に変更がないこと(143条1項本文)
∵Ⅰ 従前の訴訟資料を新請求の審理に利用するのにふさわしい関係の要求
Ⅱ 被告の防御の目標が予想外のものに変更されることによる不利益が生じないこと(主張される経済的利益がより大きいものになる場合は従前の訴訟資料は利用できないと解すべき)
*被告が陳述した事実に依拠して原告が訴えの変更をする場合は請求の基礎に変更があってもよい
② 著しく訴訟手続を遅滞させないこと(143条1項ただし書)
⇒ 口頭弁論終結時に接着した時点でも,新たに証拠調べがいらない場合は許可すべき
③ 事実審の口頭弁論終結前であること(143条1項本文)
④ 請求の併合要件を満たしていること
第4 反訴
1 意義
反訴とは,係属中の訴訟手続を利用して,被告が原告を相手方として提起する訴えを反訴という(146条)
2 要件
① 本訴の目的である請求又は防御方法と関連すること
② 著しく訴訟手続を遅滞させること
③ 本訴が事実審に係属し,口頭弁論終結前であること
④ 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属しないこと
⑤ 反訴請求について請求の併合要件を具備していること
3 審理と手続
① 書面を作成して提出する必要性(146条3項)
② Yが反訴提起後に,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁が提出した場合,本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合(最判平成18年4月14日民集60巻4号1497頁[3])
⇒ その部分については反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更される
* 反訴被告の利益を損なわないので書面や同意はいらない
③ 債務不存在確認の訴えに対して,被告が給付を求めたい場合
⇒ 反訴によらないと重複起訴の禁止に抵触する
* 反訴が提起されると,不存在確認の本訴は訴えの利益を喪失し却下
第5 中間確認の訴え
1 意義
(1) 定義
中間確認の訴えは,訴訟係属中に,本来の請求の当否の判断に対して先決関係にある法律関係の存否について,原告又は被告が追加的に提起する確認の訴えをいう(145条)
(2) 制度趣旨
請求の判断に対して先決関係にある法律関係の存否については,終局判決の理由中で判断されるが,これについては既判力が生じないので,これを訴訟物として追加することを許して紛争解決の効率性を上げるため
(3) 典型例
① 所有権に基づく建物明渡請求の訴えにおける訴訟物は,所有権に基づく返還請求権であって,その発声根拠とされる「所有権」の存否については既判力が生じない
⇒ 所有権の確認を求める訴えを追加する場合
* 訴えの変更の手続による
② 利息金支払い請求の訴えについては,元本債権の存在が論理的前提になるところ,これは直接の訴訟物とはならないので,この存否の確認を求めるのは,中間確認の訴えとなる
2 要件と手続
(1) 中間確認の訴えの要件[4]
① 訴訟係属中であること
② 本来の請求の当否の判断に対する関係で先決関係にある法律関係を対象とするものであること
③ その法律関係の存否について当事者間で争いがあるとして,積極的又は消極的確認を求めるものであること
④ 事実審係属中で,口頭弁論終結前であること
⑤ 他の裁判所の専属管轄に属しないこと
⑥ 請求併合の一般的要件を具備していること
(2) 中間確認の訴えの手続
第12編 当事者の複数化に対する基本的規律
第1 複数当事者訴訟に対する規律を理解する視点
1 訴訟手続の基本単位
2 処分権主義・弁論主義と紛争の個別相対的解決
民事訴訟は手続的関与が保障された当事者間においてのみ紛争を解決する仕組み!!
3 複数当事者訴訟制度の趣旨
メリット デメリット ① 紛争の一挙的解決 ② 審理の重複を回避
③ 矛盾判断の回避
①審理や手続の複雑化 ②訴訟遅延
③関連する紛争を統一的に解決するためには,訴訟資料の統一を図る必要があることから,訴訟当事者の権能に制限を加えることが必要な場合あり
⇒ 訴訟当事者の権能に制限を加える必要!!(当事者の自主性を尊重する民訴制度の基調と抵触する)
⇒ メリットとデメリットを調和させる点に趣旨がある
第2 共同訴訟
1 総説
(1) 共同訴訟の制度目的の必要性
共同訴訟とは,1つの訴訟手続に数人の原告又は被告が関与している訴訟形態をいう
⇒ 比較的広く共同訴訟が認められているのは,紛争の一挙的解決や審理の重複を避けるメリットが重視されている!!
(2) 共同訴訟の訴訟法的効果
ア 審理の併合
⇒ 審理の重複を避けて事実上訴訟資料の統一を図ることができるので,紛争の統一的解決に資する
イ 証拠共通・主張共通
問題意識 併合された手続の中で,ある共同訴訟人が提出した主張や証拠提出の効力が他の共同訴訟人に対しても当然に及ぶという効果を認めるべきかが問題となる
● 共同訴訟による統一的な紛争解決を重視すべき
⇒ 訴訟法的効果を広く認め,裁判資料を共通化すべき
* 審理内容面での統一性が法律上確保されることに
× このような効果を認めることは,処分権主義・弁論主義に基づく訴訟構造と矛盾のおそれ
⇒ 当事者が本来有するはずの訴訟資料提出・不提出の自由や争わずに訴訟手続を離脱する自由,すなわち自律的訴訟追行の自由を制約する可能性(40条1項2項)
↓
*必要的共同訴訟は法律上この効果が認められるが,本来は当事者の自律的訴訟追行を尊重する通常共同訴訟においてもこのような効果を認められるべきか
ウ 訴訟進行の統一
● 共同訴訟による統一的な紛争解決を重視すべき
⇒ 弁論の併合強制や弁論の分離を禁止すべき
⇒ 1人について中断事由が生じた場合には,全訴訟を中断すべき
∵ 全訴訟の進行の統一及び当事者の手続関与を強く保障する趣旨
× 訴訟法的効果を付与することには,個別訴訟の場合には軽快な手続であったものが,共同訴訟の場合には重く複雑な手続としてしまうおそれ
エ 訴訟共同の強制
● 共同訴訟による統一的な紛争解決を重視すべき
⇒ そもそも訴え提起の当初から共同訴訟として提起しなければ却下すべき
∵ 関係者全員がそろって訴えを提起しなければ不適法な訴えとして拒絶!
×① 原告の一部の反対や行方不明によって訴訟手続を利用できないことに
② 原告に散在する被告の特定の所在調査という困難な調査・探索の負担
2 共同訴訟の類型と付与される訴訟法的効果
(1) 通常共同訴訟と必要的共同訴訟
ア 視点
⇒ 合一確定の要請があるか
*『合一確定の要請』
合一確定の要請とは,同一人に対する判決効の矛盾衝突を避けなければならないとの法律上の要請をいう
*共同訴訟人の1人が受けた判決の効力が他の共同訴訟人にも及ぶ場合
バラバラの判断がなされると・・・
⇒ 各共同訴訟人が当事者として受けた判決の既判力と他の共同訴訟人に対する判決から拡張される既判力が矛盾衝突するおそれ!!
∵ 40条1項の「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合」との文言が,判決(既判力)による紛争解決という観点を背景に解釈されたものと考えられる
イ 構造
『合一確定の要請』⇒紛争の統一的全面的解決への指向が最も強くなる⇒強い訴訟法的効果(審理の併合,証拠共通・主張共通,訴訟進行の統一,訴訟共同の強制)を与える立法政策を採るべき
ウ 対照的な条文(39条)
『合一確定の要請』⇒通常の個別訴訟を束ねる⇒弱い訴訟法的効果しか与えない⇒事実上の統一的解決を図る
エ まとめ
*根本的な視点の相違
通常共同訴訟のベクトル 必要的共同訴訟のベクトル 当事者の自律的訴訟追行の自由を尊重すべき ⇒ 統一的紛争解決は事実上の利点
紛争の統一的解決を確保すべき ⇒ 当事者の訴訟追行の自由の制約はやむを得ない
(2) 固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟
視点 個別程度が可能であるか
ア 固有必要的共同訴訟
⇒ 4つの訴訟法的効果がそろったロイヤル・ストレート・フラッシュみたいなもの!!
イ 類似必要的共同訴訟
⇒ 個別提訴は可能であるので,「訴訟共同の強制」を外した3つの効果!!
第3 通常共同訴訟
1 意義
(1) 定義
通常共同訴訟とは,個別訴訟の併合形態をいう
(2) 特徴
① 審理及び判決の統一性についての法律上の保障なし
② 各共同訴訟人は各自独立で係争利益の処分ができる
③ 訴訟追行権も各自に独立
④ 同一期日での弁論や証拠調べなどが行われるという事実上の限度において審理の重複を回避し,事実認定の統一が図られる
⇒ 審理の併合(中),証拠共通(強)・主張共通(無),訴訟進行の統一(中),訴訟共同の強制(無)という程度で紛争の統一的解決の視点からみると,ハートのツー・ペアみたいなものか!!
(3) 39条の制度趣旨
民事訴訟における個別相対的解決の原則(当事者の自律的訴訟追行の自由)が共同訴訟においても貫徹されるべきことを宣言
(4) 反射効と通常共同訴訟
主債務者と連帯保証人とを共同被告として訴える場合,通常共同訴訟
● 主債務の存在が保証人の地位の論理的前提となっているから主債務の存否についての認定判断が異なるのは奇異
× だからといって,それぞれの訴訟追行の自由を制約してまで統一的解決を図る必要はない
2 主観的併合要件(38条)
(1) 制度趣旨
① 請求相互間に一定の共通性又は関連性があるときは,1つの訴訟手続で束ねて審理することが紛争解決の上で合理的
② 自己に無関係な他人間の紛争に巻き込まれる相手方の不利益を防止することにその趣旨を置く
(2) 要件
① 権利義務が共通の場合(前段)
② 権利義務が同一の事実上又は法律上の原因に基づく場合(前段)
③ 権利義務が同種で,かつ同種の原因に基づく場合(後段)
Cf. 客観的併合要件(136条)
3 訴訟資料・手続進行の統一
(1) 共同訴訟人独立の原則(39条)
ア 定義
共同訴訟人独立の原則とは,各共同訴訟人は他の共同訴訟人に制約されることなく,各自独立に訴訟を追行する権能を有していることをいう
⇒ 効果も行為者と相手方のみ!!
イ 帰結
① 訴訟資料(×証拠資料)は各共同訴訟人に共通ではなくなる
② 訴訟の進行も結果も,判決確定時期も異なりうる
③ 裁判所も弁論を分離し判決できる
∵Ⅰ 通常共同訴訟はあくまでも個別訴訟の結合形態にすぎない
Ⅱ 個別訴訟と同様に私的自治を訴訟上貫徹すべき
Ⅲ 係争利益は自由に処分可能であるから,訴訟において他の共同訴訟人の干渉を受けるのはおかしい
Ⅳ 訴訟法的観点からみても,審理の結果としての判決(既判力)の効力が他の共同訴訟人に拡張されないのだから,判決効の矛盾衝突を回避する必要がなく,訴訟資料と手続進行を統一する必要はない
(2) 共同訴訟人間の証拠共通
○ 証拠共通の原則は認められる
⇒ 通常共同訴訟でも,「証拠資料(×訴訟資料)」は共通化する!!
∵ 認定事実となる歴史的事実は1つしかないので,矛盾した事実認定を強いることは自由心証主義に対する不当な制約となる
* 共同訴訟人独立の原則が働く通常共同訴訟においても,共同訴訟人の1人が提出した証拠又はこれに対して提出された証拠は,他の共同訴訟人と共通あるいは関連する係争事実については,特にその援用がなくても事実認定の資料とすることができる
Cf. 対立当事者間に妥当する「証拠共通」や「主張共通」は,通常共同訴訟人間には妥当しない!!
(3) 共同訴訟人間の主張共通
● 主張共通を認めるべき
× 証拠共通は,弁論主義が尽くされた後の裁判所による証拠評価の問題であったのに対して,主張共通は訴訟資料の提出そのものの問題
○ 主張共通は認められない
∵① 主張共通を認めると,訴訟追行の自由を制約することになるので,共同訴訟人独立の原則(39条)に反する
② 自律的訴訟追行の自由を確保するための弁論主義が,併合審判の事実上の効用という観点から制約されることはあり得ない
× 通常共同訴訟は主観的併合要件の具備が求められるところ,38条の3つの要件は関連性の濃淡に差があるので,共同訴訟人独立の原則の機械的適用は不当である
● 当然の補助参加の理論を適用すべき
⇒ 共同訴訟人間に補助参加の利益が存在する場合は,たとえ申出がなされていなくても補助参加があったものとして取扱い,それにより主張共通を導こうとした
× 明示的な申出のないままに補助参加関係を肯定するのは手続の明確性・安定性を犠牲
* 実務上は,共同訴訟人間で準備書面や書証の写しが事実上交付されることで手続保障が図られる[5]
4 追加的共同訴訟(主観的追加的併合)
典型例
① 原告Xが被告Yに対して,取引的不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起した場合に,Yがかつて雇用していた使用者ZがXに対して使用者責任不存在確認の訴えを提起する場合
② Xの保証人Yに対する履行請求において,保証人Yが主債務者Zに対する求償請求の訴えを追加する場合
(1) 追加的共同訴訟の問題意識
訴訟の係属中に,第三者が当事者に対して訴えを提起して併合審判を求めることや,当事者が第三者にして請求を追加して併合審判を求めることがある
⇒ 民訴法も立法政策において,一定の場合にこれを認めている。というのも,第三者による追加として共同訴訟参加(52条),当事者による追加としては,訴訟引受(50条,51条)がある
(2) 主観的追加的併合の議論の射程距離
必要的共同訴訟において当事者が欠いていることが事後的に判明した場合は,このような追加によって不備を補正することは必要な措置で妨げられない
(3) 通常共同訴訟の主観的追加的併合の肯否
ア 問題意識
通常共同訴訟が成立する場合であっても,このような追加的併合を当事者の申立権として構成すべきか
イ 争いのない前提
弁論を併合するか否かは裁判所の訴訟指揮権に関わる裁量事項で,関連紛争でも通常共同訴訟であるから併合審判の保障がない。仮に併合されても,通常共同訴訟が成立するのにすぎないから,裁判所はまた分離できる
ウ 検討
○ 当事者による追加の事案について主観的併合を当事者の申立権として構成することを否定すべき(最判昭和62年7月17日民集41巻5号1402頁)
∵① 併合を認める明文の規定なし
② これを認めても新訴について旧訴訟の訴訟状態を当然に利用できるものではなく,必ずしも訴訟経済に適さない
③ かえって訴訟を複雑化させるという弊害も予想
④ 軽率な提訴ないし濫訴が増加するおそれがあり,新訴提起の時期いかんによっては訴訟の遅延を招きやすい
×Ⅰ ①「明文規定の不存在」,④「濫訴による訴訟遅滞」は決定的理由でない
Ⅱ ③「複雑化の弊害」も弁論の分離を考慮すれば足りるので,一般的にこの併合申立権を否定する根拠とならない
⇒ 真の争いは,②「訴訟状態(訴訟資料の集積による心証形成状態を含む)の利用の可否」にある
● 主観的追加的併合を認めると,別途当事者の援用を要するとして手続保障の付与を考えるべき
×Ⅰ 訴訟状態の分断を肯定することになる
Ⅱ (分断を認めると)関連紛争の統一的解決に資さない
Ⅲ 援用を認めないと追加当事者に不意打ち
⇒ +訴訟指揮への拘束は避けたい!!
∴ 適切な職権発動に期待するほかなく,併合審判の申立権は否定されるべき
5 予備的共同訴訟(主観的予備的併合)
典型例
① 代理人と契約したことを理由に,第1次的に本人に対して履行請求をして,併せて無権代理の疑いがある場合に備えて,第2次的に無権代理人の責任を追及するために予備的に併合提起する場合
② 土地工作物責任(民法717条)に基づく損害賠償請求について,第1次的に占有者を,第2次的に所有者を被告とする訴えを提起する場合
(1) 定義
予備的共同訴訟とは,各共同訴訟人の,又はこれらの対する各請求が実体上両立し得ない関係にある場合に,原告側がいずれか一方の審判を優先して申立て,それが認容されることを解除条件として他の請求の審判を求める併合形態をいう
(2) 検討
○ 予備的被告の応訴上の不安定・不利益,原告の便宜に偏することを理由に否定すべき(最判昭和43年3月8日民集22巻3号551頁)
∵① 被告及び請求原因の特定は原告の権能かつ責任であって,これを尽くしていないこの併合形態は不適法というほかなく,原告の事前調査の疎略さを予備的被告の犠牲において救済するのは妥当ではない
② 予備的被告は自己に対する請求についての判断が示される保障がないのに終始審理に関与しなければならず,しかも主位的請求の認容判決が確定すれば,請求棄却判決を得ることもなく訴訟係属が消滅してしまい,応訴負担が徒労に帰するうえに,原告の再訴に対してはこれを封じる手段が存在しない
③ 上訴との関係においては,主位的請求を認容した判決に対し上訴が提起された場合,この併合形態が通常共同訴訟で扱われる限り,予備的請求は当然には上級審には移審しないので,その結果併合関係は維持できず,統一的裁判は保障されない
×Ⅰ この併合形態は紛争の実体的関係を訴訟手続に反映する手段として適切
Ⅱ 紛争の統一的解決に資する(相対的解決が原則なのだが・・・)
Ⅲ この議論のフォーカスは,原告の利益と被告の利益の調和にあった
原告の利益 被告の不利益 実体的にいずれかは勝訴するはずの原告が両負けを免れるという利益 ①自己に対する請求の判断が示される保障がない,②主位的請求の認容判決が確定すれば,請求棄却判決を得ることもなく訴訟係属が消滅してしまう ⇒ 両者の利益を調和させる観点から,「同時審判共同訴訟」が創設!![6]
6 同時審判共同訴訟(41条1項,2項)
(1) 問題意識
判例によって主観的予備的併合が否定されたために,実体上両立しえない請求をするには単純併合による通常共同訴訟によらざるを得ない。
*通常共同訴訟による問題点
① この請求の内容は互いに両立しない択一関係
⇒ トレード・オフの関係にある両請求についていずれも勝訴を求めるので,原告としては主張が矛盾するので,自覚しないと両負けのおそれ
② 裁判所による公判の分離が可能
③ 上訴によって他方は当然には移審しないため併合関係が解消される
(2) 同時審判共同訴訟の創設という立法政策の採用
同時審判共同訴訟とは,両請求が実体上両立し得ないという密接関連性を有することを実体的基盤として,同時審判を保障するための訴訟政策的観点が加味された通常共同訴訟をいう
(3) 効果
① 弁論の分離ができなくなる
② 上訴により併合関係が解消しても,控訴審に併合義務(41条3項)を課して,判断が区々になることを防止
第4 必要的共同訴訟
1 意義
必要的共同訴訟とは,共同訴訟人全員について紛争の統一的解決を図らなければならない法律上の要請が高く,そのために訴訟法上もこれにふさわしい法的規律を与えるため,共同訴訟人の訴訟追行上の自由を制限してまで一挙的解決を指向すべき共同訴訟類型をいう
⇒ 訴訟法上の効果が最も強い「訴訟共同の強制」まで生じる固有必要的共同訴訟と,そこまでは生じない類似必要的共同訴訟がある
2 固有必要的共同訴訟
視点 合一確定を要求しなければならない高度の法律上の要請はあるか
⇒ 固有必要的共同訴訟のメリットとデメリットの調和の観点から,訴訟類型を選別し,「訴訟共同強制の効果」まで認められるべきかがコア
メリット デメリット ① 多数の者が関係する紛争が統一的抜本的に解決されるべきことを指向(≒固有必要的共同訴訟としないと紛争解決が中途半端になり,被告の応訴負担や矛盾判断のおそれ) ①「訴訟共同強制の効果」が生じるので共同訴訟人全員が揃わないと全体として当事者適格が認められず,訴訟手続利用の途が閉ざされる ②訴訟資料の統一化のために,訴訟追行の自由は一定程度制約される
(1) 他人間の権利関係の変動をもたらしうる訴訟
視点 第三者が他人間の法律関係の変動を請求する場合,法律関係の主体たるべき者全員を共同被告とする必要!!
∵① 法律関係の主体を除外して権利関係に変動をもたらす判決をするのは相当でない
② 訴訟共同を強制しないと,判決内容が区々になる可能性が生じ,法律関係の画一的変動を図る
(2) 数人が共同してのみ管理処分すべき財産に関する訴訟
視点 もともとは1個の法主体として訴訟当事者となりうる者について,その管理処分権が複数主体に分属している場合には,当該複数主体を当事者としなければならない
∵ 管理処分権が分属しているので,管理権者を除外して権利関係の変動をもたらす判決をするのは相当でない
Cf. 共同訴訟に同調しない者が存在する場合
⇒ 境界確定訴訟において,判例(最判平成11年11月9日民集53巻8号1421頁)は,同調しない者を被告とすべきとする
3 類似必要的共同訴訟
(1) 意義
類似必要的共同訴訟とは,「訴訟共同の強制」の効果は生じないものの,共同訴訟関係が成立すると合一確定に向けて必要的共同訴訟としての規律に服するとされるものをいう
(2) 原始的と後発的
類似必要的共同訴訟には,適格者の一部を欠いたままに訴えを提起された時から成立する場合と別々に訴えが提起された後に弁論が必要的に併合されることによって成立する場合がある
(3) 共同訴訟参加(52条)
既に先行して係属している訴訟に,第三者が原告又は被告の共同訴訟人として加入することによっても必要的共同訴訟として成立させることも可能
⇒ 当該訴訟の当事者適格を有している必要がある!!(最判昭和36年11月24日民集15巻10号2583頁)
4 効果―必要的共同訴訟の審判
ア 特色
① 訴訟資料や手続進行を整え,統一的なものとするための規制を加える
② 共同訴訟人独立の原則の適用を排除すべき
③ 共同訴訟人間に強制的に連合関係を認める
イ 40条1項
① 共同訴訟人の1人がした訴訟行為は,他の共同訴訟人の利益になる場合には,全員のために効力を生じる[7]
② 他の共同訴訟人に不利益になる場合には,他の共同訴訟人に対する関係ではもちろんのこと,訴訟行為をした共同訴訟人についても効力を生じない[8]
③ 訴えの取下げは,類似必要的共同訴訟では単独でできるが,固有必要的共同訴訟では原告が全員でしなければ効力が生じない
ウ 40条2項
① 相手方の訴訟行為は1人に対してなされたものであっても,全員に対して効力を生じるものとされる
∵ 共同訴訟人の一部が欠席しても,相手方の訴訟行為が妨げられないように便宜を図る趣旨
エ 40条3項
① 共同訴訟人の1人について手続の中断又は中止の原因があるときは,全員について訴訟の進行が停止される(40条3項)
∵ 手続進行の統一と明確を図る趣旨
オ 共同訴訟人のうちの一部の者が上訴した場合
○ 判決は全員に対する関係で確定が遮断され,当該事件は全体として上訴審に移管し,上訴審の判決の効力は上訴をしなかった共同訴訟人に及ぶ
∵① 上訴は,上訴審に対して原判決における敗訴部分の是認を求める訴訟行為であり,一般的に他の共同訴訟人に利益な行為とみられる(40条1項)
② 手続進行の統一及び合一確定の要請に適う(40条3項)
カ 一部の者が上訴した場合,上訴をしなかった共同訴訟人も上訴人となるか
● 上訴人説
⇒ 上訴審は,上訴をしなかった者に対する期日呼出しや準備書面の送付をする必要があるし,判決に当事者と表示し送達の必要性
×① 上訴しなかった共同訴訟人の合理的意思に反する
② 実務感覚にそぐわない取扱いを強いる
○ 上訴人とならないと解すべき
∵ 合一確定のためには,原判決の確定遮断,訴訟全体の移審,そして,上訴しなかった共同訴訟人に対して判決効が及ぶと解すれば足りる(最大判平成9年4月2日民集51巻4号1673頁)
第5 通常共同訴訟と必要的共同訴訟の選別問題―共同所有関係紛争
1 基本的視座
視点 実体法的考慮と訴訟政策的判断の調和の観点
実体法的考慮 訴訟政策的判断 民事訴訟は実体権の実現・処分のプロセスである以上,当事者適格の選別にあたっても,実体法上の管理処分権の帰属の態様が基準となるはず ⇒ 訴訟物たる権利関係の性質を中心とする実態法的考慮が不回避!!
当事者適格は,訴訟追行権という訴訟上の権能に関わる問題 ⇒ 決定には,紛争解決の実効性,訴訟経済などの諸要請との関係における訴訟政策的判断が不可欠!!
2 実体法的観点
視点 請求の基礎となる管理処分権の実体法的性格からこの問題を考える
*権利の性質
総有[9] 合有[10] 共有[11] 固有必要的共同訴訟 固有必要的共同訴訟 通常共同訴訟 3 訴訟法的観点
*相反する2つの視点
共同訴訟強制の縮小修正という政策 共同訴訟強制の拡大という政策 ①共同訴訟人となるべき者が1人でも欠けていると,その訴えは不適法とされてしまう ②争う意思のない被告を当事者の地位に拘束した状態に置く
③上訴審で共同訴訟人となるべき者が発見されると,原判決破棄,訴え却下となり訴訟不経済
①紛争の全面的解決 ②共有者の一部に対する訴訟を認めることは被告選択に関する原告の処分権の過大評価となる
③原告側に個別訴訟が認められると被告が数度に渡る応訴負担を課せられる
④原告が一部の者に勝訴し目的物に強制執行をする可能性がある
4 共同所有関係紛争に関する当事者適格についての判例理論
(1) 判例理論に対する基本的視座
⇒ 対内的関係と対外的関係を区別する
*判例理論の動向
対内的関係 対外的関係 「訴訟共同の強制」の効果が生じる範囲を基本的に広く取っている ⇒ 一挙一律解決を指向することに障害が少ない!!
「訴訟共同の強制」の効果が生じる範囲を縮小して個別訴訟提起の容易化を図る方向性 ⇒ 持分権,保存行為,不可分債権,不可分債務の理論を駆使する!!
(2) 共有者が原告となって提起する場合の原告適格(能動訴訟)
ア 共有不動産についての所有権(共有権)確認
イ 共有不動産についての持分権確認
ウ 共有物の妨害排除請求
エ 共有物の引渡(返還)請求
オ 登記手続請求
(3) 共有者が被告とされる場合の被告適格(受働訴訟)
ア 確認請求
イ 給付(引渡し・登記手続)請求
(4) 共有者内部での紛争
第6 選定当事者(30条)
∵ 訴訟の単純化
* 明文で認められている任意的訴訟担当
第7 訴訟参加
1 参加制度の必要性と制度の枠組み
(1) 参加制度のメリットとデメリット
メリット デメリット ①訴訟外の第三者がすでに係属している他人間の訴訟の結果に利害を有する場合は,参加できればその訴訟手続で自らの利益を擁護・保全する機会が与えられる ②継続中の訴訟当事者にとっても関連紛争が全面的に解決する
①第三者が参加介入することによって審理が重く複雑なものとなる (2) 訴訟参加の立法政策
法は,メリットとデメリットを調和させる観点から訴訟参加の制度を規定している。具体的には,Ⅰ紛争タイプとⅡ当事者の利害関係の濃淡―を考慮して複数の参加制度を設けている
当事者と同格で参加する 在来当事者の援軍として参加 制度 Ⅰ独立当事者参加 Ⅱ共同訴訟参加
Ⅲ補助参加 ⇒ 各制度は同じ訴訟参加の制度であるから,ⅠからⅢを区別は,各参加制度の趣旨・機能と各参加制度相互の機能的連関及び役割分担の観点から要件設定と手続規律に意識すること
第8 補助参加
1 意義[12]
補助参加とは,他人間の訴訟の結果に法律上の利害関係を有する第三者が,当事者の一方を補助しこれを勝訴させることによって,自己の利益を確保する参加制度をいう
2 典型例
債権者Xが保証人Yに対して保証債務履行請求を行った。これに対して,主たる債務者Zが補助参加することが考えられる
⇒ Zは,X=Y間の訴訟の中で,主債務に関する弁済,相殺や消滅時効の抗弁を主張して攻撃防御活動を行って保証人の勝訴を補助し,これによって『保証人』からの将来の求償請求を予防する!!
3 補助参加における参加の利益[13]
(1) 訴訟の結果について「利害関係を有する」こと
「利害関係を有する」とは,訴訟の結果について,「法律上の利害関係」を有していることが必要
∵ 訴訟手続の複雑化を招いてまで補助参加を認める必要はない
(2) 法律上の利害関係の中身
ア 定義
「法律上の利害関係」とは,訴訟の結果について,法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがあることをいう(最決平成13年1月30日民集55巻1号30頁)
イ 注意点[14]
法律上の利害関係とは,必ずしも判決が直接に補助参加人の権利義務に影響を及ぼすべき場合や判決効が補助参加人に及ぶ場合に限られない[15]
⇒ ある程度は間接的なものも含まれているという意味(具体的には,訴訟の結果を前提にして補助参加人の権利義務その他法的地位の決定の参考となるおそれ,すなわち事実上の影響[16]があればよい)!!
ウ 法律上の利害関係があるとされる典型例
① 被参加人が敗訴すれば,参加申出人が求償・損害賠償その他一定の訴えを提起される関係にある場合 ② 第1の訴訟が第2の訴訟の先決関係にある場合 ③ 当事者の一方と同様の地位・境遇にある者が補助参加を申し出る場合(③の場合には否定する学説もある) (2) 「訴訟の結果」について利害関係を有すること[17][18]
「訴訟の結果」とは,判決主文で判断される訴訟物たる権利又は法律関係の存否についての利害関係をいう
∵① 訴訟の結果を判決主文における訴訟物判断と考えると基準が明確
② 判決理由中の判断は既判力が生じないから,補助参加人の利益保護の必要性が薄い一方で,利害関係が乏しい者が参加することで第三者の介入の余地が拡大
3 補助参加の手続
(1) 補助参加の申出(43条1項)
(2) 補助参加の許否(44条1項2項)
4 補助参加人の訴訟上の地位
(1) 独立性と従属性の複合的性格
補助参加人は,独立的性格(自らの利益のために当事者の意思に反してでも,既存の訴訟手続に参加することができるので,単なる補助者とは異なる)と従属的性格(相手方との間に独自の訴訟上の請求を提示して当事者となるものではない)との複合的性格がある
(2) 補助参加人の訴訟行為
原則 被参加人と同様の一切の訴訟行為をすることができる(45条1項)
例外
① 被参加人がもはや行えない行為(45条1項但書)
∵ 補助参加が他人間の訴訟を前提にするものであることに基づくとともに,審理の混乱を防止するため
② 被参加人の行為と抵触する行為(45条2項)
∵ 主たる当事者である被参加人の利益保護を優先する趣旨[19]
③ 訴訟自体の処分・変更にかかわる行為
∵ 補助参加が他人間の訴訟を前提とするものからくる限界[20]
5 補助参加人に対する裁判の効力(46条)
(1) 問題の所在
46条は,既判力の補助参加人に対する拡張なのか,既判力と異なる特殊な効力なのか
(2) 検討
● 既判力の拡張と解すべき
×① 民訴法46条各号には除外事由があり既判力とは性質が異なる
② 参加人と被参加人の間には審判対象たる訴訟物がない
③ 参加人と被参加人は共同関係にあり対立関係から生じる既判力とは違う
④ 裁判の効力は,参加人と被参加人の判決理由部分も含めないと意味ない
⑤ 訴訟告知を受けただけで,現実に訴訟に参加していなくても裁判の効力を受けるとされている(53条4項)
○ 参加的効力と解すべき
∵ 同一当事者側で共同して訴訟を追行し敗訴した者相互間の責任分担原理である衡平,禁反言に基づいて認められる
(3) 判例
ア 最判昭和45年10月22日民集24巻11号1583頁
⇒ 判決理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否の判断に及ぶ
イ 最判平成14年1月22日金法1645号49頁[21]
⇒ 判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などをいう
2 共同訴訟的補助参加
(1) 意義
共同訴訟的補助参加とは,係属中の訴訟の判決効が及ぶものの,当事者として参加する適格がない第三者がする補助参加をいう
(2) 効果
必要的共同訴訟人に近い訴訟上の地位を付与
第9 訴訟告知(53条)
1 意義
訴訟告知とは,訴訟係属中,訴訟の結果について利害関係を有する(=補助参加できる)第三者に対して,当事者が訴訟係属の事実を通知することをいう。
2 制度趣旨
第三者に対して参加の機会を与えるとともに,当事者が敗訴した場合に被告知者に対して参加的効力を及ぼすことで紛争解決を目指す点にある。
⇒ 被告知者の利益のためと告知者の利益のためという2つの側面あり
3 要件
① 訴訟係属中であること
② 告知権者は当事者か補助参加人又はそれらから告知を受けた者
③ 告知を受けられるのは,訴訟参加しうる第三者に限られる(補助参加,独立当事者参加,共同訴訟参加,訴訟承継)
4 効果
被告知者の参加の有無に関わらず,参加的効力を及ぼす(53条4項,46条)
第10 独立当事者参加
1 意義
独立当事者参加とは,継続中の他人間の訴訟の目的となっている権利又は法律関係について,第三者が自己の請求を定立して参加・介入し,対立牽制しつつ,三者間で一挙に紛争を統一的に解決するための参加制度をいう。
独立当事者制度の制度趣旨は,在来当事者の訴訟追行を牽制しつつ,自らの請求について審判を求め,統一的な紛争解決を得る訴訟追行上の地位と機会の保障という点にある
2 「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する」
(1) 詐害防止参加(47条1項前段)
訴訟の結果によって「権利が害される」とは,判決によって事実上権利侵害を受ける第三者であれば足りると考えられる(利害関係説)
∵ 補助参加の連続性を意識しつつ,利害関係の程度を補助参加より強度のものとする
*判例は,訴訟の結果,間接的に自己の権利を侵害されるおそれがある者をも包含するとしているので,判決効説を否定し利害関係説に立っていると評価
⇒ 補助参加と異なり,「権利」とされているところに特別の意味を見出すか否かの違い(利害関係説は,なるべく特別の意味を見出さない処理)
(2) 権利主張参加(47条1項後段)
権利主張参加をするには,他人間の訴訟における請求と,参加人の請求とが論理的に両立しない関係にある必要がある
Ex. XがYに対して土地所有権に基づく引渡請求訴訟を提起したところ,Zは,当該土地の所有権は自己にあると主張してXに対して土地所有権確認,Yに対して確認と引渡しを求める場合
* 権利主張参加は積極目的なので,詐害防止参加のように参加の利益は問題とならない(訴えの利益の問題に還元されると考えられる)
第11 訴訟承継
1 訴訟承継制度の意義と必要性
(1) 訴訟制度の目的
当事者の訴訟追行権の基礎が第三者に移転した場合にそれまでの訴訟状態を当該第三者に引き継がせる制度をいう
(2) 制度趣旨
訴訟係属中に実体関係が変動した場合は,その当事者間で本案判決をしても,紛争の解決にならない。そこで,いったん訴訟が開始され,紛争解決過程において訴訟状態が形成された場合には承継を認めるのが合理的
2 当然承継
(1) 定義
当然承継とは,法定の承継原因の発生によって法律上当然に当事者が交替して訴訟承継を生じる場合をいう[22]
∵ 訴訟手続の中断・受継に関する規定から推知される
(2) 承継手続
中断が生じる場合 中断が生じない場合(訴訟代理人) 受継の申立て⇒受継決定(128条) 代理人が旧当事者の名で訴訟を追行 2 特定承継
(1) 意義
特定承継とは,係争物の譲渡により特定的な地位が移転したことに起因して承継を認める場合をいう。
(2) 制度趣旨
訴訟状態の形成過程における当事者の既得的地位の保障という点
⇒ 特定承継の場合は,当事者からの申立てを待って,その変更が訴訟手続に反映される仕組み
(3) 承継原因
ア 要件
特定承継をするには,「紛争の主体たる地位を前主から承継したと評価するに足りる実体関係の変動があること」が必要
イ 考慮要素
① 前主との間の訴訟資料が利用できること
② 承継人もまた前主の訴訟資料に依存する関係にあること
③ 前主の原告に対する義務と承継人が原告に対する義務との牽連性の程度
⇒ 従前の訴訟資料を第三者に引き継がせることが不当といえないという実質論と第三者の地位が前主からの伝来的取得に基づくという歯止めを形式論として相関的に考量して,承継の制度趣旨(当事者の既得的地位の保障)に適合するかを判断する[23]
注)承継人に対する訴訟物が前主と異なっているからといって,承継が認められないことはない点に注意
ウ 最判昭和41年3月22日民集20巻3号484頁
設例 Xは,甲建物をYに対して賃貸した。この賃貸借契約は一時使用の賃貸借で存続期間満了により終了した。そこで,Xは,Yに対して「賃貸借契約終了に基づく建物収去土地明渡請求」をした。ところが,ZがYから甲建物の一部を賃借して営業をするに至った。そこで,Xは特定承継の申立てをして,Zに対して「所有権に基づく建物退去土地明渡請求」をした[24][25]
3 承継の効果
承継の効果は,承継人は承継直前の訴訟状態における前当事者の地位を引き継ぐこと
⇒ 時機に後れた攻撃防御方法の提出のように,前当事者がすでに行うことができなくなった行為については,承継人もできない[26]
[1] 原始的客観的併合の要件は,突き詰めて考えると,①や③は別に客観的併合の場合のみ問題になるわけではないと思われる。というのも,①の場合,例えば,通常訴訟であるのに手形判決を求めることはできないし,③の場合,専属管轄違背があれば併合訴訟ではなくても訴訟は違法になる。そうすると,視点で述べたメリットとデメリットの調和の観点は,原則として,客観的併合を認めつつ,例外的に立法政策で否定している場合に禁止されるというものといえる。とすれば,特段の立法政策がない以上,ほとんど無条件に併合が認められていると解すべきであろう。
[2] つまり,判例は,原告の意思を合理的に解釈しなるべく交換的変更ではなく,追加的変更と把握することによって,複合行為説の不都合性を回避しようとしているものと考えられる。調査官解説によると,この判例は被告が明示的に異議を述べているようである。異議を述べた場合は追加的変更と解すべきものと思われる。32年判例は要旨次のように判示する。「訴えの変更が許されるかは,旧訴の係属中新訴を追加的に提起することが許されるかの問題と考えられる。そうだとすれば,いったん係属した旧訴の訴訟係属が消滅するかは訴えの変更とは直接関係がない」と述べて,訴えの取下げには,被告の同意が必要なのであるから,訴えの交換的変更の場合には被告の同意が必要である。ただし,黙示の同意がある場合は明示の同意は不要であるとする。
[3] 判旨は次のとおりである。「本件相殺は,反訴提起後に,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として対当額で相殺するというものであるから,まず,本件相殺と本件反訴との関係について判断する。係属中の別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは,重複起訴を禁じた民訴法142 条の趣旨に反し,許されない(最高裁昭和62 年第1385 号平成3 年12 月17 日第三小法廷判決・民集45 巻9号1435 頁)。
しかし,本訴及び反訴が係属中に,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは禁じられないと解するのが相当である。この場合においては,反訴原告において異なる意思表示をしない限り,反訴は,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分については反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更される
ことになるものと解するのが相当であって,このように解すれば,重複起訴の問題は生じないことになるからである。そして,上記の訴えの変更は,本訴,反訴を通じた審判の対象に変更を生ずるものではなく,反訴被告の利益を損なうものでもないから,書面によることを要せず,反訴被告の同意も要しないというべきである。本件については,前記事実関係及び訴訟の経過に照らしても,上告人らが本件相殺
を抗弁として主張したことについて,上記と異なる意思表示をしたことはうかがわれないので,本件反訴は,上記のような内容の予備的反訴に変更されたものと解するのが相当である」。
[4] 中間確認の訴えの要件は,②と③が要求される代わりに,訴えの変更であるにもかかわらず,「請求の基礎の同一性」が要件から外されているということに特別類型としての意義がある。
[5] 主張共通の問題意識というのは,相共同訴訟人が有益な主張をした場合にそれに他方が,気が付かないという場合と考えられる。このような場合,相共同訴訟人の準備書面の写しの送付が行われればその主張の確認をすることが可能である。したがって,実務上は主張共通を認めないことによる弊害は生じていないと解される。
[6] 少し議論がかみ合っていないと思われるが,主観的予備的併合訴訟というのは,大上段の議論では,客観的予備的併合や主観的追加的併合との概念上の対比という形で抽象的に議論することは可能であったと思われる。もっとも,主観的予備的併合が認められるべきとの実践的な主張は,原告の両負けの危険性を強調するものと考えられたわけである。そうすると,別の制度でこの危険性を除去できるのであれば,主観的予備的併合というのは純粋な概念法学上の肯否の問題にとどまると解されるように思われる。この点,両負けの危険性は,通常共同訴訟で事実上実現されると思われるが,弁論の分離をされるおそれがある。そこで,弁論を分離させないことにより,制度的に統一的解釈を事実上保障しようとするのが同時審判共同訴訟といえるであろう。「制度的」に「事実上」というのがパラドックスな制度といえるであろう。
[7] 例えば,XがY1とY2を共同被告として訴えた訴訟が必要的共同訴訟である場合,Y1がXの請求原因の要件事実を否認ないし抗弁を提出し争えば,全員が争ったことになり,Y2との関係で擬制自白が成立することはなくなる。
[8] 例えば,上記の例でY1がXの請求原因の要件事実について自白をしても,自白の効果は生じない。もっとも,Y2が欠席して公判に出頭しない場合はY2についても擬制自白が成立し自白の効果が認められることもある。
[9] 総有の場合は,構成員は物の使用収益権能を有するにすぎず,持分を観念することはできない。そのため,処分は構成員全員でする必要があると考えられる。
[10] 合有は持分を観念することはできるが,その処分権の権能は制限され一般には管理処分権能は共有権に共同帰属すると解されている。
[11] 共有の場合には,各共有者は持分を有し,自由に管理処分権を行使することができる。もっとも,処分行為か保存行為かで要件が異なるが,基本的には通常共同訴訟を認めてよいものと考えられる。
[12] 調査官解説は,補助参加の目的とは,「当事者以外の者が訴訟に参加して当事者の一方を補助する訴訟活動をすることによって被参加人に有利な判決を得させることを助け,併せて被参加人に対し敗訴判決がされることによって補助参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に事実上の不利益な影響を受けることを防止することを目的」とするとしている。「法的利益に事実上の不利益な影響」というのも法律上の利害関係に含まれることを前提として目的の設定のようであり,間接的利益も法律上の利益と把握されている点が注目される。
[13] 参加の利益の要件は,第三者の参加を許容するかの選別機能を有するので慎重に検討される必要があるところ,訴訟参加の制度のうち,独立当事者参加や共同訴訟参加はあくまでも第三者が「当事者」として参加していくものであるから,当事者適格がないと参加できない。したがって,第三者は訴えの利益を有しているということになるから,参加の利益が否定されるということはあまり考えられない。これに対して,補助参加というのは,もともと当事者として参加するわけではなく,勝訴判決は得られても,「間接的」な利益を受けるにすぎないことが多いので,間接的な利益は参加の利益ではないと考えてしまうと補助参加を認める範囲がほとんどなくなってしまう。このように,この要件は特に補助参加との関係でシビアな問題を提起することを自覚しておく必要があるものと解される。
[14] 補助参加にいう利害関係が法律上の利害関係であることを必要とするか,それとも事実上の利害関係でも足りるのかとする点について争いがあるように指摘する文献も見られる。しかし本当に問題であるのは,「法律上の利害関係」とは何かということを明らかにすることである。というのも,そもそも,補助参加という参加形態では,補助参加人が意図するような勝訴判決が得られても間接的に利益を受けるにすぎないということがいえる。そうだとすれば,間接的な利益=反射的な利益と解すれば,それは「法律上の利害関係」ではないと解することができる。しかしながら,もしそうすると,補助参加では,「法律上の利害関係」があるという範囲が著しく限定されるということになる。そこで,「法律上の利害関係」の中にも,間接的な利益を取り込むことが求められるわけである。
[15] 判決の効力が及ぶ場合は共同訴訟的補助参加となる
[16] 山本戸克己教授は,この事実上の影響力のことを「判決の証明効」と説明する
[17] 「訴訟の結果」については,従前,訴訟物限定説と訴訟物非限定説が対立している。もっとも,両者の帰結は大きくは異ならないように思われる。例えば,XがYに対して所有権に基づいてダイヤモンドの引渡請求をする場合において,ZがX=Z間の売買契約の無効を主張している場合には,ZがYに対して補助参加する利益は認められるかが問題となる。従前,訴訟物限定説によると補助参加の利益が否定され,訴訟物非限定説によると補助参加の利益が肯定されると理解されていた。しかしながら,訴訟物限定説の意図は,「訴訟物たる権利の存否」を「訴訟の結果」ととらえていると理解すると,Xの所有権に基づく引渡請求が認められYが敗訴すると,Zの法律上の地位に影響が生じる場合には,訴訟物限定説に立っても,補助参加の利益を肯定することになることもできる。
[18] もう少し敷衍すると,従前,補助参加の利益の射程距離を限定するメルクマールとして利用されてきたのが,「訴訟物に限られる」か,「判決理由中の判断も含まれる」のかという対立軸であったわけである。これは,従前,利害関係の中身は,法律上の利害関係に限られると言ってみたはいいものの,その法律上の利害関係の中身を明らかにしてこなかったわけである。考えてみれば,補助参加は,間接的に参加人が利益を受けるものにすぎないから,厳密な意味における「法律上の利益」を持っていることはないはずである。そこで,そこでは,「法律上の利益」の射程距離の中にどれだけの間接的な利益も含めるのかという解釈作業が要請されることになるが,従前の学説はこの点はさて置いて,訴訟物か判決理由かという「訴訟の結果」という文言の解釈に関連して大雑把な二項対立により結論を導こうとしていたものと考えられる。しかしながら,調査官解説が明らかにするように,法律上の利害関係に間接的なものを取り込むと,訴訟の結果を訴訟物と理解したとしても,補助参加の利益が認められる範囲は相当に拡大することになる。すなわち,「法律上の利益」の中身が具体的に明らかにされた以上,「訴訟の結果」の解釈は紛争解決のメルクマールとしての役割を失ったものと解するのが相当であろう。もっとも,現実には,ある程度,法律上の利害関係の中に間接的な利益が取り込まれていることに照らすと,訴訟物非限定説と結論は比較的近いのではなかろうかと思われる。
[19] 例えば,参加人が否認し争っても,被参加人が自白すれば被参加人の訴訟行為が優先することになる。
[20] 判例は,補助参加人の上訴期間は被参加人の上訴期間内に限るとしている(最判昭和37年1月19日民集16巻1号106頁,なお,旧試2008年2問参照)。調査官解説は,旧法に被参加人の上訴期間内に限るとする明文がありこれが受け継がれているとする。しかも,本件は検察官を被告とする認知の訴えに対して,家督相続人が補助参加したというものであり,「被参加人が控訴していないため,補助参加人のした控訴が却下されることにより,補助参加人としては実体的審判を受ける機会を失ってしまったものであり,判決正本が検察官に送達されたことを補助参加人が知らないことは通常無理のないことであろうから,本件のような場合の補助参加人にはまことに気の毒な結果」であったとしている。この判例に照らすと,補助参加人に対する判決書の送達が被参加人よりも遅い場合には,補助参加人の上訴期間は法定期間よりも短縮されることになる。これに対して,藤田462は「疑問が残る」とする。また,上田539は「判決が参加人に送達された時点から独自に上訴期間が進行すると解すべきであろう。補助参加は参加人のための手続保障制度でもあるから,判決書の送達は必要的であり,また,右のように解しても両当事者に不当な結果を生じることはない」として判例に反対している。
[21] 売主Xがいずれかが買主と考えられる二人(YとZ)のうち,一方(Y)に対して代金支払請求訴訟を提起し,かつ,他方(Z)に訴訟告知をした。この場合のX=Y間の訴訟で,「被告知者(Z)が買主である」との理由で請求棄却判決が確定してもその判決の効力は被告知者(Z)には及ばない。
[22] [論証]法定の承継原因が発生しても訴訟代理人がある場合,手続は中断しない。そして,この場合,代理人は,旧当事者の名で訴訟を追行することになる。もっとも,実質的には,承継原因が発生した時点で承継人は当事者となっていると評価できる。したがって,旧当事者の名で判決がなされても,その判決は承継人に対して効力を有するものと解される。この場合は,判決の更正を求めることになる
[23] [論証] 承継が認められるには,紛争の主体たる地位を前主から承継したと評価できる実体関係の変動があることが必要である。なぜなら,特定承継の目的は,新たに当事者となる者の手続保障を図りながら,既存の訴訟当事者の既得的地位を保障しようとする点にある。とすれば,単に実体法上の訴訟物の譲渡のみを承継の原因とするのは相当ではなく,他方で,新当事者に対する手続保障の観点から,新旧当事者に何らの関連性もない場合を承継原因とするのも妥当性を欠くからである。そして,紛争の当事者たる地位の承継があるかは,①訴訟資料の共通性の程度と②前主の原告に対する義務と承継人が原告に対する義務とが牽連している程度の相関関係を考慮して判断するものと考えられる。
[24] 本問の場合,XはYに対して債権的請求をしているので,物権的請求とは異なり,Yが占有を失ったとしても債権的請求権がなくなるわけではない。もっとも,XがYに対する訴訟を維持して勝訴判決を得ても強制執行をすることができないので意味がないといえる。この場合のXとしては,①Zに対する別訴を提起する,②特定承継で引き受けさせる―の2つの解決が考えられる。調査官解説は,実質論を展開し,「通常の場合,Zの地位がYの従前の主張と訴訟資料に依存するとともにXもYとの関係で提出した反対の訴訟資料を転用できるものである以上,正当な要請として是認すべき」であるとする。そして,「Zとしても,従前の訴訟資料を利用できる点において,新訴を提起されはじめから訴訟離床を収集提出すべき立場に置かれるのと比較してはるかに利益」とする。そのうえで,調査官解説は,以上のような実質論から承継は認められるが,問題は理論構成とする。すなわち,敷衍すると,本件のX・Y間の請求は債権的請求であるから,仮に,YがZに対して転貸したとしても,YはXに対して目的物を明け渡す義務を負っている以上,XがYに対する訴訟をする訴えの利益がなくなったとはいえないので,適格承継説に立つ限り,被告適格がYからZに対して移転しているとはいえないことになる。上告論旨もこの点を論難するものである。判旨は,Zが賃貸借終了に基づく建物退去,土地明渡義務をXに対して負担するYから当該建物を賃借した場合は,「建物収去義務に包含される建物退去義務に関する紛争の主体たる地位が被告から第三者に移転したもの」と理解して,これをもって被告適格の承継があると見るわけである。判旨は,「紛争の主体たる地位」を敷衍して,X・Z間の建物退去義務の存否に関する紛争はZにおいてYから建物を賃借しその占有を承継したことを契機として,ZのXに対する退去義務の存否に関する紛争という形態をとって両者間に移行すると説明している。この点,調査官解説は,X・Y間の義務は債権的なものであるから,これがZに引き継がれることはあり得ない。しかるに,判旨が紛争の移行ありというのは,「当該紛争は,前法律的な建物の支配をめぐる経済的利害の対抗関係として把握されている」とみるしかないとする。したがって,『紛争の主体たる地位』とは,もはや実体法上の権利義務の帰属点として理解されているのではなく,むしろ,経済的利害対抗関係の当事者として観念されていると考えることができる。
[25] 所論にかんがみ敷衍して説明する。まず,この論点は,口頭弁論終結後の承継人と訴訟承継の場合の2つの場面で問題となる。もっとも,前者では,もはや既判力を及ぼされる者は訴訟手続に参加する余地はないのであるから,その範囲は限定的にとらえなければならないものと思われる。したがって,判例は,前者では純粋な適格承継説を採っているものと解せられる。そこでは,実質的判断として,当事者間の公平と手続保障をメルクマールにした実質論で結論を出した後で,それを適格承継説にあてはめるという構造であった。もっとも,そこでは,先述のように,純粋な適格承継説が採られているから,本件のように,X・Y間が債権的請求で,X・Z間が物上請求という場合は適格承継説のフレームの中に入らないので,承継人とは認められなかった。ところが,後者の場合では判例はこれを認めている。これは,実質的利益衡量の差と考えられる。というのも,後者の場合は,Zも訴訟手続に参加することができ,しかもZも従前の訴訟資料を利用できるという点に照らすと利益を受けているので,ただ,既判力の拡張を受ける前者とはZをとりまく利益状態が異なっているということができるように思われる。判例は,このような基本的視座に立って,後は後付けの理論である「紛争の主体たる地位」が移転していると解したわけである。これは,調査官解説にかんがみると,どうやら判例は適格承継説を前提に,それを法律論以前の社会科学のレベルでとらえているというだけで,一応,適格承継説の亜流と位置付けることはできそうなように思われる。これは見方を変えると,そもそも,X・Y間では債権的請求である以上,訴えの利益は存続するのであるから,被告適格がZには移転していないのであって,Zに対する請求はまったく別個に生じたので承継を論じる余地はないと解することもできるように思われるのであって,訴えの利益の移転を判旨が相当に社会学的にとらえていることが注目されてよいように思われる。
[26] [論証] 原則として,訴訟承継の効果として承継人は従前の訴訟状態の拘束を受けることになる。しかし,承継原因の発生によって実質的に訴訟に利害関係を喪失した前主の訴訟追行に拘束されるとするのは,代替的手続保障の観点から問題がある。したがって,この場合は例外的に従前に訴訟状態の拘束を受けないものと解する。