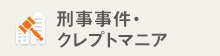名古屋の弁護士による刑法総論
第1編 刑法の基礎原理
第1 犯罪と刑罰の基本観念
1 刑法の意義と沿革
2 刑法の分類
3 刑法の行為規範―自然犯と法定犯の区別
4 刑法の社会的機能
(1) 規制的機能
刑法の規制的機能とは,国民に対して,どのような行為が罰せられるのか,どの程度の刑が科せられるのかをあらかじめ知らしめ,そのような犯罪行為に出ないことを命じることにより,国民の行為を規制する機能をいう
(2) 社会秩序維持機能
① 法益保護機能
刑法は,刑罰という最も峻厳な制裁を手段とすることによって,最も強力
な形で法益保護の機能を果たす(他の法律と比較して法益保護機能が強い)
② 人権保障機能
Ⅰ 善良な市民のマグナ・カルタ
一般人との関係では,刑法に犯罪として定められていない行為について
は,それがいかに反社会的で不道徳な行為であっても処罰されないことを
保障する機能をいう
Ⅱ 犯人のマグナ・カルタ
犯人との関係では,刑法に定められた以上の刑を受けないことを保障する機能をいう
5 犯罪と刑罰に関する基礎理論(刑法理論)
(1) 犯罪理論
犯罪理論とは,犯罪の本質をどのように理解するかという問題の理論をいう
① 非決定論(19世紀的価値観)
非決定論とは,人間には自由意思があり,自己の行動についても因果の法則に支配されることなく,その理性的判断により選択することができることを前提とする犯罪理論をいう。非決定論を前提とすれば,犯罪行為は自由な意思を有する人間がその理性的選択に基づいて行ったものである。そうすると,犯罪に対する評価は,理性的選択の結果といえる外部に表れた犯人の行為及びその結果に対して行えばよい(客観主義)
② 決定論(20世紀的価値観)
決定論とは,人間に自由意思があるとするのは幻想であり,その行動は遺伝的素質と社会的環境によって支配され,決定され尽くされていることを前提とする犯罪理論をいう。決定論を前提とすれば,犯罪行為は,人間の自由な選択に基づいているのではなく,遺伝的素質や社会的環境により必然的に生じる現象であるということになる。そうすると,犯罪に対する評価は,外部に表れた犯人の行動により決まるというわけではなく,むしろ,犯人の持つ社会的な危険性に対して行う必要がある(主観主義)
(2) 刑罰理論
刑罰理論とは,なぜ国家は刑罰を科することができるのかという問題の理論をいう
① 応報刑主義
応報刑主義とは,刑罰は,犯罪に対する応報として科せられるという考え方をいう
∵ 犯罪との均衡を失するような刑罰を科すことは刑罰の役割に反する
② 一般予防主義
一般予防主義とは,刑罰は,これを科することによって社会の一般人を威嚇し,将来における犯罪を予防するためにあるという考え方をいう
∵ 一般予防主義の場合,「みせしめ的」な要素があるので,必ずしも刑罰は犯罪に相応するものである必要はなくなる
③ 特別予防主義
特別予防主義とは,刑罰は,これを科することによって犯人自身が将来再
び犯罪に陥ることを予防するという考え方をいう
Ⅰ 刑罰を科することによって犯人自身を一般社会から隔離する
Ⅱ 刑罰という苦痛を犯人に加えることにより,犯人を懲らしめそれにより再犯を防止しようという考え方をいう
Ⅲ 刑罰によって犯人を改善・教育し,真人間として社会復帰させることによって,再犯を防止しようという考え方をいう
| 犯罪論 | 決定論 | 非決定論 |
| 犯罪理論 | 客観主義 | 主観主義 |
| 刑罰理論 | 応報刑主義・一般予防主義 | 特別予防主義 |
(3) 通説の理解
通説は,自由意思との関係では,古典派・近代派の考え方はいずれも極端かつ一方的であり,そのまま受け入れることはできないとする。そこで通説は,人間は,素質と環境との制約を受けながらも,主体的に自己の行動を決定する自由意思を有すると両者の折衷的な立場をとっている(相対的意思自由論)。
通説は,制約を受けるとはいえ,人間の自由意思を一応認めるので,犯罪理論については,客観主義の立場をとっている(客観主義)。他方,刑罰理論については,人間の自由意思を一応認めるのであるから応報刑主義が基本となるが,一般予防・特別予防主義とトレード・オフの関係にあるわけではないから,応報を基本としつつ,一般予防・特別予防主義の考え方を加味して考えるべき
第2 罪刑法定主義
1 意義と沿革
罪刑法定主義とは,いかなる行為が犯罪となり,それに対していかなる刑罰が科せられるかについて,あらかじめ成文法をもって規定しなければ人を処罰することができないとする原則をいう
(⇔ 刑罰専断主義[国家のほしいままに処罰])
*「罪刑法定主義からいって問題である」という主張が弁護人から出されることがあるが,これは,国家の恣意的な処罰を招きかねないという意味
2 実定法上の根拠
(1) 憲法31条
(2) 憲法73条6号ただし書
(3) 憲法39条前段
3 具体的内容と派生原理
(1) 罪刑の法定(成文法主義)
罪刑の法定とは,国民の代表である国会の議決によって制定された狭義の法律をもって明示される必要があるという原理のことをいう
ア 慣習刑法
∵ 狭義の法律ではない
イ 絶対的不定期刑
∵ 刑罰についての定めがない場合,「狭義の法律をもって明示され」たとはいえない(法律を定めたうちに入らない)
ウ 命令・条例に対する委任(特定委任)
狭義の法律において罪刑の基本的枠組みが定められている限り,その罪刑の具体的内容を部分的に命令や条例に委任することも罪刑法定主義に反しない(←「罪刑法定主義」からいって問題ないか)
エ 白地刑罰法規
法律で処罰の対象となる行為の枠を一応定めたうえで,構成要件の細目を政令以下の命令に委ねることも,それが特定事項に限られている限り許される(←「罪刑法定主義」からいって問題ないか)
(2) 類推解釈の禁止の原則
ア 類推解釈の禁止の原則の典型
法律に規定していない事項まで法律を適用することは裁判官の解釈によって罪刑の法定を実質的に無意味にして処罰の範囲を際限なく拡大することを意味するから,その結果,国家の恣意的な処罰を招くおそれがあるから許されない。
Cf. 有利類推解釈は認められる
イ 類推解釈の禁止の原則の射程外
刑法の文言に形式的に忠実であるべきである,という文理解釈をすることを求めることが類推解釈禁止の原則の射程に入ってくるわけではない。
もちろん,刑法の公示機能を没却するほどの実質解釈は許されないが,刑法の精神に照らして,法の予想しうる限度まで実質解釈をすること(目的論的解釈)は許されている
(3) 遡及処罰の禁止の原則(憲法39条前段)
遡及処罰の禁止の原則は,罪刑法定主義のコロラリーの一つと考えられている。遡及処罰を認めるきっかけは,国家の恣意的な判断に基づきやすいし,法的安定性を害し個人の自由を不当に侵害するからである。
(4) 明確性の原則
明確性の原則とは,刑罰法規はできるだけ具体的であり,かつ,その意味するところが明確でなければならず,刑罰法規の内容があいまい不明確であるため,通常の判断能力を有する一般人の理解において刑罰の対象となる行為を識別することができない場合には,罪刑法定主義に反し,憲法31条に反するとする原則のことをいう。
∵ 刑罰法規があいまいである場合は,結局,どのような行為が犯罪となるの
か予測可能性が立たず,また,いかようにも解釈することができるために国家による恣意的な処罰を招くからである
(5) 罪刑均衡の原則
罪刑均衡の原則とは,刑罰の内容又は程度が犯罪の害悪に見合った合理的なものであることを要するという原則をいう
(⇒罪刑均衡の原則によれば,犯罪と刑罰との不均衡が顕著の場合には,罪刑法定主義に反し憲法31条に反する)
∵ 罪刑法定主義からすれば,国家の刑罰権は恣意的なものでなく犯罪の害悪に見合った合理的な場合にのみ発動される必要があるところ,国会が恣意的に特定の犯罪類型のみ犯罪の害悪の内容に見合わないものを定めた場合には,憲法31条に反する
第3 刑法の適用範囲
1 時間的適用範囲に関する原則
(1) 時間的適用範囲に関する原則
(2) 刑法6条の特則
2 刑法の場所的適用範囲
(1) 国内犯の処罰
(2) 日本国民の国外犯の処罰
(3) 日本国民以外の者の国外犯の処罰
(4) 日本の国家的利益を害する国外犯の処罰
(5) 日本国公務員の国外犯の処罰
(6) 包括的国外犯処罰
第2編 犯 罪
第1章 犯罪の概念
第1 犯罪の概念と犯罪の成立要件
1 犯罪の概念
① 社会学の犯罪の定義
犯罪とは,社会生活上の利益・秩序を侵害する高度の害悪性を持つ行為をいう
(←刑法は,社会学の犯罪の定義をさらに絞り込んで,『当罰性』と『可罰性』がある行為に限定している)
② 刑法上の犯罪の定義
犯罪とは,構成要件に該当し,違法かつ有責な行為をいう
* 補足説明
行為が『可罰的』というためには,現に法律によって刑罰を科することができるものである必要があるが,これは罪刑法定主義からいって当たり前のことにすぎない。そうすると,いかに法秩序に違反し責任があろうとも,そもそも法律によって構成要件化されていない場合は,可罰性がなく犯罪となる余地はない。他方,社会学の犯罪の定義にあたり構成要件に該当すればすべて処罰するというわけにはいかず,これをさらに絞り込むために,『当罰性』という概念が重要と考えられる。
『当罰性』とは,刑罰という制裁に相応する性質があることをいう。そして,刑罰の制裁に相応する性質があるというためには,①法秩序に違反すること(違法であること),②違法行為をしたことについて,その行為者を非難することができること(有責であること)―が必要である。
分かりにくいと思うが,構成要件がコップであり,違法性が水であり,責任が黒色の着色料と考えてみよう。そうすると,犯罪というためには,コップに黒い水が入っていなければならないのである。もとより,黒い水があってもコップがなければ犯罪とならない。いかに悪い行為(黒い水)であっても国家政策の見地から処罰しないこともあるからである。反対に,コップだけあって,中身が入っていない場合やコップに水が入っているものの,黒色の色がついていない場合にも犯罪にならないということである。例えば,人を殺した場合には,一見してコップ(刑法199条)があることが明らかである。ところが,例えば,正当防衛として人を殺したという場合には違法性がなく,「コップはあるが水はない」という状態となる。また,実は,心神喪失状態にあったという場合には,「コップの中に水は入っているが黒い色はついていない」という状態となる。私たちの社会生活の中では,コップがあるだけで犯罪と思っている人が多いがこのような形式的な思考は誤っているのである。私たちは,コップがあるかというだけではなく,「黒い水が入っているか」ということにも着目しなければならない。そして,量刑を決めるにあたっては,コップの中に水がどの程度入っているのか(違法性の強弱),コップの水の黒色の色の強さはどれくらいか(責任の程度)にも着目して実質的に判断をしなければ到底正しい量刑を図ることなどできないというべきである。
2 犯罪の成立要件
(1) 構成要件該当性
構成要件とは,違法・有責な行為を類型化したもの
(2) 違法性
構成要件は,違法行為を類型化したものといえるから,構成要件に該当する以上,違法性が推定される。しかしながら,構成要件はあくまでも類型にすぎないから,その類型の射程距離に入ってくるものでありながら,現実には違法性が欠ける場合がある。そこで,構成要件該当性が認められる行為であっても,違法性を真に備えているかを,さらに,法秩序全体の見地から具体的・実質的に検討する。
(3) 有責性
有責性とは,構成要件に該当し違法な行為がある場合に,その行為を行為者がしたことについての非難を行為者に帰することができるか(帰責という)という問題をいう
帰責するためには,Ⅰ行為者が,事の是非善悪を弁識し,これにしたがって行動する能力(責任能力)を有することが必要となる。また,Ⅱ行為者がその行為を認識・認容しているか(故意があるか)―が必要というべき
| 名称 | 根拠 |
| 構成要件該当性 | 罪刑法定主義から導かれる要件。国民の行動の自由を保障するためにいかなる行為が犯罪として可罰的か告知する |
| 違法性 | 刑法の機能が法益の保護を目的としていることから導かれる。真に社会的に有害かを吟味するための要件 |
| 有責性 | 刑法の自由保障機能の一部である責任主義から導かれる。刑罰とは,サンクションを予告して国民に対して心理的プレッシャーを与えようとするもの(心理強制説)であるから,社会的に有害である行為でも行為者を非難できることが必要となる |
3 処罰条件及び処罰阻却事由
第2 犯罪概念の基底としての「行為」
1 「行為」の意義と機能
① 犯罪という概念の基本要素(罪数の基準)
② 人の単なる反射運動や内心の意思・思想などを初めから犯罪概念の外に置き処罰の範囲を限定する
2 「行為」の概念とその要素
実務では,刑法上の行為において不可欠の要素として次の点を考慮する
① 意思支配可能性
行為とは,意思によって支配可能な人の態度をいう
∵ 人の行為は,たしかに,因果法則の支配(自然現象)の影響を受けるものの,逆に,人は自らの意思で因果の過程を作り出してそれを支配することができる。そうすると,支配が可能であるのに支配しないで,あえて因果法則に身を任せるという形で行為が行われることもある(不作為による行為)
② 外部性
行為は,社会生活において何らかの独立した意味(社会的意味を区別することができるという意味)を持つ外部的態度である必要がある。
第2章 構成要件
第1 構成要件の機能と構成要件要素
1 構成要件の意義と機能
① 社会的機能(=保障機能)
構成要件は,違法・有責な当罰的行為のうちから犯罪となるものを選び出し,その他のものを除外する機能を有する
② 理論的機能(=違法性・有責性推定機能)
構成要件は,これに該当する行為については,一応,違法・有責であると推定させる機能を有する
2 構成要件該当性の判断
まず,構成要件の確定をする必要がある。構成要件の確定とは,構成要件の内容自体を法解釈により確定することをいう。
3 構成要件要素
(1) 客観的構成要件要素
客観的構成要件要素とは,その存在が外見的に認識されうる要素をいう
① 行為(構成要件的行為)
② 行為の主体
③ 行為の客体
④ 行為の結果(構成要件的結果)
ⅰ 結果犯・挙動犯・結果的加重犯(結果との関係での分類)[1]
(ⅰ) 結果犯とは,一定の結果の発生を構成要件要素として規定している犯罪のことをいう
(ⅱ) 挙動犯とは,行為者の一定の身体的動静のみが構成要件の内容となっており,一定の結果の発生が構成要件要素とされていないものをいう
(ⅲ) 結果的加重犯とは,行為者が一定の故意に基づく犯罪行為を行った後,その行為からその故意を超過する重い結果が生じたことを構成要件として規定しており,その重い結果が生じたことをもって基本となる犯罪より重い刑が定められている犯罪をいう
ⅱ 侵害犯・危険犯・形式犯(法益の侵害の程度による分類)[2]
(ⅰ) 侵害犯とは,保護法益を現実に侵害したことが構成要件要素となっている犯罪をいう
(ⅱ) 危険犯とは,保護法益侵害の危険を生じさせたことが構成要件要素となっている犯罪をいう。このうち,具体的危険犯とは,法益侵害の具体的危険,すなわち,現実に危険が発生したことを構成要件要素として規定している犯罪をいう。また,抽象的危険犯とは,法益侵害の抽象的危険,すなわち,一般的に法益侵害の危険があると認められる行為があれば,それだけで犯罪が成立するものをいう
(ⅲ) 形式犯とは,犯罪が成立するためには,法益侵害の抽象的危険すらも必要とされない犯罪をいう
ⅲ 即成犯・継続犯・状態犯[3]
(ⅰ) 即成犯とは,構成要件的結果の発生によって法益侵害が発生し犯罪も既遂となるものをいうが,その後,行為者の関与なくして法益侵害状態が因果法則(自然状態)によって継続することをいう
(ⅱ) 状態犯とは,構成要件的結果の発生によって法益侵害が発生し犯罪も既遂に達するのは即成犯と同じであるが,その後,行為者の(意思に基づく)行為によって,法益侵害状態が継続するものをいう
(ⅲ) 継続犯とは,構成要件的結果の発生とともに,法益侵害も発生し,犯罪は既遂となるが,その後も犯罪行為が継続している間,終始法益侵害の状態が継続し,犯罪の継続が認められるものをいう
⑤ 因果関係
結果犯に限り,行為と結果の因果関係が必要となる
(2) 主観的構成要件要素
主観的構成要件要素とは,行為者の内心に関するものであり,したがって,外見的には認識することができない要素をいう
① 故意・過失
故意とは,犯罪事実(客観的構成要件要素)に該当する事実を認識・認容していることをいう
過失とは,不注意により,犯罪事実の認識又は認容を欠いて,一定の作為・不作為をすることをいう
ⅰ 故意・過失の体系的地位
故意・過失は責任要素だが,それにとどまらず違法性の大小を決めるという機能もある
ⅱ 過失は単なる主観的構成要件要素か
過失とは,主観的要素と客観的要素の面を両方含んだ構成要件要素である。
つまり,刑法の「過失」とは,不注意により犯罪事実の認識・認容を欠いたという純然たる内心の態度とそのような内容によって一定の作為・不作為を行ったという外部的態度の両方を含めているものと考えられる。したがって,「過失」は,「故意」のように主観的構成要件的要素という性質を有するが,それのみに限られるわけではなく,単に行為者の内心にのみ関わる要素と理解することには問題がある
② 目的犯における目的
目的犯とは,一定の行為の目的が構成要件要素とされている犯罪のことをいう。目的とは,一定の事項を成し遂げようとする意欲のことをいう
∵ 『目的』が要求される趣旨は,故意があるだけでは,違法性が希薄な行為について特別の違法性を基礎付けたり,行為の有責性を一層強めたりするという点にある
③ 傾向犯における傾向など
傾向犯とは,行為者の特定の心情又は内心の傾向を構成要件要素とし,行為がそのような主観的傾向の表出とみられる場合に限り,犯罪が成立することをいう
4 構成要件の確定に関する特殊問題
(1) 規範的構成要件要素
規範的構成要件要素とは,法解釈によってその要素の内容を確定することには限界があり,ある事実がその要素に該当するか否かについては,最終的に裁判官がその当時の社会常識によって規範的・評価的な価値判断を行って決定しなくてはならない部分を含んでいる構成要件要素のことをいう
* 規範的構成要件要素は罪刑法定主義からいって問題であるが,事柄の性質上又は複雑な社会事象に対処するためにこれを排除することはできない。そこで,価値観の多様化も踏まえた裁判官の客観的かつ厳密な判断が必要といえる
(2) 開かれた構成要件
開かれた構成要件とは,犯罪要素のすべてが余すところなく規定されているわけではなく,規定されていない部分については,その適用にあたり裁判官による補充が予定されているものをいう。典型例は,過失犯(『過失』の内容,特に客観的注意義務違反の内容)と不真正不作為犯(『作為義務』の内容)
* 開かれた構成要件要素も明確性という視点からすれば,罪刑法定主義からいって問題がある。ただし,過失の注意義務の内容を余すところなく規定するのは,実際は不可能であるから,このような定め方もやむを得ないと解される
(3) 修正された構成要件
修正された構成要件とは,未遂犯及び共犯の構成要件をいう
| 基本的構成要件 | 刑法43条で修正!! | 刑法60条で修正!! |
| 人を殺した者 | 人を殺す行為の実行に着手してこれを遂げなかった者 | 二人以上共同して人を殺した者 |
第2 実行行為Ⅰ(総説)
1 実行行為の意義
実行行為とは,法益侵害の現実的危険という実質を有し,特定の構成要件に形式的にも実質的にも該当すると認められる行為をいう
2 実行行為の実質
① 法益侵害発生の現実的危険が低い場合は構成要件該当性を否定できる
② 実行の着手時期を特定する場合,実行行為の実質は重要なメルクマール
第3 実行行為Ⅱ(不作為犯)
1 真正不作為犯と不真正不作為犯
2 不真正不作為犯の実行行為性
不真正不作為犯の実行行為性を肯定するためには,個々の構成要件の解釈により,作為犯の構成要件であっても明らかに不作為を排除する趣旨が示されていない限り,不作為による遂行も含む趣旨と解することができる。そうだとすれば,刑法上の大多数の作為犯について実行行為性を肯定することができるとも思える。
しかしながら,不真正不作為犯は,不作為と構成要件的結果との間に因果関係があれば,直ちに実行行為性を認められるというわけではない。
なぜなら,通常,不作為は,作為と比較して消極的な形態であるから,違法性が少ないと解されるからである。そもそも,作為犯の構成要件は,典型的行為形態として違法性の強い作為を予想しているから,不真正不作為犯を認めるには,その不作為が作為に匹敵する強い違法性をもっている必要がある(構成要件的同価値性)。
そこで,不真正不作為犯の構成要件該当性をみるには,構成要件的に同価値と評価しうるほどの違法性があるかも検討する必要がある
3 不真正不作為犯の成立要件
不真正不作犯が成立するには,①法的な作為義務の存在と②作為の可能性・容易性が必要と解する
(1) 法的な作為義務
ア 形式的な説明
法的な作為義務,すなわち,義務の履行を法的に強制できるものでなければならず,かつ,行為者に作為犯の構成要件的結果の発生を防止すべき作為義務が認められなければならない。
∵ 下命に違反して作為に出ないことは,作為と匹敵する違法性あり
イ 実質的な説明(保障人的地位)
法的な作為義務は,実質的には,社会生活上その者に当該法益の保護が具体的に依存している必要がある。
① 保障人的地位にある者の作為義務
他者の法益保護をすべき地位を,近親関係により又は自ら引き受けた場合
② 先行行為に基づく作為義務
自己の行為によって結果発生の危険を生じさせた者は,その発生を防止すべき法的義務を負う
③ 管理者の作為義務
物の管理者は,自己の管理する物から,他人の法益を侵害する危険が生じた場合には,その危険を除去すべき義務を負う。その危険の原因が自己の責に基づかないものであっても同様といえる
(2) 作為の可能性・容易性
不真正不作為犯が成立するためには,単に作為義務の履行が可能であるというだけでは足りず,その行為者にとって作為が容易であることが必要である
⇒ 作為の容易性とは,自ら重大な損失や危険を受けることなく,比較的容易に結果防止のための作為をすることができるという場合に,初めて,作為の容易性を認めることができる。
* 作為の容易性と作為義務の強さは,相関関係で決められる
| 作為が容易な場合 | 作為義務が弱くても成立 |
| 作為が困難な場合 | 強い作為義務が必要 |
(3) 判例の分析
① 排他的な支配あるいは支配領域性(他には,消化したり救助したりするものがいないという点)
② 先行行為を自分で作っていること
③ 先行行為を自分で作っていないとすれば,親や建物の管理人といった社会継続的な保護関係が重視されている
(4) 西田説(排他的支配領域性説)[4]
ア 意思に基づく排他的支配がある場合
不作為が作為と構成要件的に同価値と評価されるには,不作為者がすでに発生している物理的な因果の流れを自己の掌中に収めることが必要
⇒ 意思に基づく排他的支配の獲得が本質的
イ 意思に基づく排他的支配がない場合
意思に基づくという部分が欠けるために,それを補充するため,親子関係や建物の管理者・警備員であるなどの社会継続的な保護関係が必要と解する
⇒ 規範的要素を考慮してよいのは,意思に基づかないものの客観的な排他的な支配が設定されている場合の帰責の可否の場合のみということになる
第4 実行行為Ⅲ(間接正犯)
1 間接正犯の意義と本質
間接正犯とは,他人を道具として利用し,実行行為を行う場合をいう
Cf. 正犯の概念と間接正犯
正犯とは,自ら犯罪を実行したものをいうが,自ら犯罪を実行したといえるためには,自己の犯罪意思を実現するために自ら事態の成り行きを操作したという事実(行為支配)が必要と解される。そうすると,間接正犯は,道具理論によって「道具」の利用と評価されてきたが,その実体は正犯である以上,当然に要求される行為支配性をいうと考えられる。
2 間接正犯の成立要件
① 故意
② 他人を道具として利用し,特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思
③ 行為者が被利用者の行為をあたかも道具のように一方的に支配・利用し,被利用者の行為を通じて構成要件的行為を行ったこと
3 間接正犯の類型
(1) 被利用者の行為が,刑法上の「行為」とはいえない場合
最も典型的な「道具」
① 被利用者が意思能力を欠いている場合
被利用者が意思能力を欠いている場合,すなわち是非弁識能力を全く欠いている場合
② 被利用者が意思を抑圧されている場合
意思能力があっても,被利用者が利用者によって意思を抑圧されて犯罪を行った場合には,やはり当該犯行は被利用者にとって意思支配可能といえないから,刑法上の「行為(意思に基づく身体の動静)」といえない
(2) 被利用者が一定の主観的構成要件要素を欠いている場合
被利用者には,自己の行為が犯罪を構成するという認識がないから,利用者の「道具」と評価することができる
① 被利用者が構成要件的故意を欠く場合
典型例 Xは,Yを殺害するために毒入り餃子を郵便で送りつけた場合
注意点 ① 構成要件的故意を欠くとは,間接正犯者(X)が実現しようとした犯罪事実についての故意を欠くという意味である。したがって,被利用者が他の犯罪事実についての故意を有していても間接正犯は成立する
② 被利用者には,過失があれば過失犯が成立するが,これは,被利用者が間接正犯の「道具」であることを妨げるものではない
② 目的犯において,被利用者が目的を欠く場合(目的のない故意ある道具)
典型例 教材用と称して,行使の目的を欠く印刷業者に偽札を作らせる場合がこれにあたる
(3) 被利用者の行為は構成要件に該当するが,正当行為等の理由により,違法性を欠く場合
被利用者は,自己の行為が犯罪を構成するという認識がないのであるから,やはり「道具」といえる
典型例 警察官Xは,Yを監禁するために,留置係のAを欺いて,「覚せい剤の取調べを明日もするので,留置してほしい」と依頼し,Aが,Yを留置したような場合が考えられる。この場合,Aは,正当行為の認識によって違法性の認識を欠いているから,間接正犯の道具として評価することができる(Xは,監禁罪)。
第5 因果関係
1 因果関係の意義と問題点
刑法上の因果関係とは,発生した構成要件的結果の事実を行為者の実行行為に帰属させる役割を有する
2 条件関係
(1) 因果関係の断続[5]
因果関係の断絶とは,実行行為から結果に向けて因果の流れが進行中,行為者の行為とは無関係の偶然の事情が介入し,それによって当該結果が発生してしまった場合をいう
Ex. 甲がAを殺害しようとAに毒を飲ませたところ,それが身体に回らない
うちに,乙がAを刺して殺した
(2) 条件関係の存否の判断の注意点
ア 「甲の行為がなかったならば」という判断をする場合,甲の行為を「除いて」考えるだけであって,その条件以外に現実に存在しなかった事実を仮定的に「付け加えて」判断することは許されない[6]
Ex. 甲は,自動車を運転中,道路上で寝ていたAをひいて死なせたが,もし甲がひかなくても,Aは対向して走ってきた乙の自動車にひかれて死亡したとみられる場合
イ 実行行為が不作為である場合には,「一定の期待された作為がなされたならば,その結果の発生は阻止できたであろう」という関係が必要となる[7]
3 因果関係に対する法的限定の要否
(1) 条件説
ア 条件説の基本的視座
条件説とは,条件関係の公式以上に法的な観点から因果関係に絞りをかけることを否定するというものである
イ 不都合性について
因果関係が認められる範囲が広くなる点は,因果関係を否定することで解決すべきでなく,故意や責任を否定することで足りる
ウ 因果関係の中断論[8]
因果関係の中断論とは,因果の過程の進行中に,第三者の故意に基づく行為又は自然力が介入した場合には,実行行為と結果との因果関係は中断し,因果関係の存在が否定される
Ex. 甲が殺意をもってAに切りつけ重傷を負わせたため,Aは入院することになったが,入院中に同室者乙とトラブルになりAが乙に刺殺された場合
(2) 相当因果関係説
4 因果関係に関する判例の検討
判例は,因果関係の問題が個別的色彩の強いことにかんがみ,具体的な事例判例の集積を通じてその立場を明らかにする態度をとっている
(1) 条件関係の判断に関する基本的な思考方法
① 当該実行行為が結果に対する直接の原因である必要はないし,また,唯一の原因である必要もない
② 当該実行行為がたとえ単独では,結果発生をもたらし得ないものであっても,他の条件とあいまって結果を生じた場合であればよい
③ 当該実行行為が,他の条件と比して,条件としては間接かつ劣勢のものでもよい
(2) 被害者の特異体質・隠れた病変が存在する場合
∴ 因果関係は否定する余地はない(ただし,因果関係の断絶に注意すべき,このケースでは,因果関係の中断が生じる余地はない)[9][10][11]
⇒ 判例は被害者の素因がある場合に一貫して因果関係を肯定してきたが,行為自体が危険であったり,被害者が高齢ないし病弱などのケースが多い!!
(3) 被害者の行為が介在する場合[12]
ア 回避・逃走行為
(ア) 逃走などの回避行為の途中,被害者が無意識のうちに誤って転倒
∴ 因果関係はある
∵ 被告人の暴行がもたらす危険の範囲内であって,通常生じ得る事態
(イ) 被害者が意識的に選択した逃走手段によって生じた結果
考慮要素
① 逃走手段自体の危険性
② 逃走手段事態の異常性
③ 被告人の行為の備える危険の範囲内(誘発しているといえるか)か
⇒ 当初の行為の危険の強さの程度,追跡や新たな暴行が行われる切迫性などを考慮し,被害者の置かれた心理的状況なども検討すべき
*最決平成15年7月16日刑集57巻7号950頁(逃走中の高速道路侵入事件)
● 高速道路への侵入は極めて危険である上,本件では急傾斜の法面やフェンスのため,立入り自体が容易ではなく,また被告人らが追跡をしているが見失っているので,客観的事情を重視すると,被害者の介在事情は異常で予測不能
× 当初の行為の危険の強さの程度,追跡や新たな暴行が行われる切迫性などを考慮し,被害者の置かれた心理的状況なども検討すべき
○ 因果関係を否定されるような異常なものとはいえない
∵① 多数人による激しい暴行を受け,逃走はしたが自動車で追跡されると考えて必至の心理状態であったことなど,被害者の置かれた具体的状況を考慮すると,被害者の本件逃走行為はやむを得ず選択したものと認められる
② 因果関係が否定されるには,被害者が被告人らによる暴行,追跡行為の心理的・物理的影響が断ち切られるほどの安全圏まで逃走している必要がある(最決平成15年の射程距離の限界)[13]
イ それ以外の行為
考慮要素
⇒ 被害者の介入については,様々な態様がある!!
① その行為の種類態様
② その介入原因
③ 行為者の行為との関連(被告人の指示に直接由来している,指導者が受講者を見失ったために初心者の受講者がパニックとなった)
④ 行為者との人的関係(医者と患者,指導者と受講者など)
(ア) Xの行為が結果発生の蓋然性が客観的に低く,被害者の行為とシンクロして結果が発生したケース
基本的視座
被告人の行為の危険性が実現する過程の範囲内とはいえないような,異常かつ結果への影響力が大きい事情が介在した場合,因果関係は否定されることになるが,被告人の行為と介在行為の結びつきの有無・程度や各行為の結果発生に対する影響(寄与)の関係によって判断することになる
*最決平成4年12月17日刑集46巻9号683頁(夜間潜水事件)[14]
⇒ 因果関係が否定される可能性が高いので慎重な判断が必要!!
(イ) Xの行為が結果発生の蓋然性が客観的に高く,その後に被害者の行為が結果発生を助長したケース
Ⅰ 典型ケース
基本的視座
死亡の結果をもたらすような重大な損傷を加え,死因がそれに基づく場合,当初の行為から通常生じ得る結果と認められ,「行為に内包する危険が現実化した」という公式が妥当する
⇒ 因果関係が認められるのが当然!!
* 介在事情の具体的態様や被告人の行為との関連,寄与度や予測可能性の有無は原則として問題とならないことに注意すべき
* 16年判例のケースでは,被告人の行為が被害者の医師の指示の不遵守を誘発したとの影響を及ぼしたとはいえないが,誘発させたかはここでは何のメルクマールにもならない
*最決平成16年2月17日刑集58巻2号169頁(医師の指示の不遵守事件)
Ⅱ 限界ケース(16年判例の射程外)
事例 XはYに対して死亡の結果をもたらし得るような重大な損傷を与えた。Yは,治療を受ければ確実に治癒すると見込まれていたが,Yはエホバの証人の信者であったので,輸血を拒否すべく診療を拒否したために死亡した[15]
(4) 行為者の事後行為が介在する場合[16]
⇒ 2つの行為の関係(実行の着手の認定)や因果関係の錯誤がむしろ問題!
∴ 因果関係は否定されない
*最決昭和53年3月22日刑集32巻2号381頁(熊撃ち事件)
事例 自己の過失により瀕死の重傷を負わせ,故意の第2行為により死亡させたもの(業務上過失傷害(×致死)罪と殺人罪の併合罪)
● 弁護人は,業務上過失致死と殺人未遂の併合罪と主張
∵ 被害者の死期を早めた点では南港事件と類似する
○ 第1の過失行為と死亡結果との因果関係を否定し,第2行為を殺人罪
∵ 射殺行為が介在したという異常性及び行為の寄与度の大きさ
*東京高判平成13年2月20日(ベランダ転落死事件)
事例 Xは,包丁で妻の胸を数回突き刺した(第1行為)。そして,包丁を台所に置きに行く際に,妻が9階のベランダの手すり伝いに逃げ出そうとした。そこで,Xは,連れ戻そうとして掴みかかった(第2行為)。ところが,これを避けようとした妻が転落し死亡した[17]
(5) 第三者の行為が介在する場合
判例は,行為の一定の類型的危険性が存在し,その危険が結果へと現実化したと評価される場合に因果関係があると解している
ア 第三者の行為が過失行為であるとき[18]
∴ 判例は因果関係を否定しないことが多い
考慮要素 当初の行為と介入行為のそれぞれの態様と結果への影響度,当初の行為と介入行為の関連(誘発関係など)を考慮,特に第2事故が発生する蓋然性を時間帯や道路状況に応じて判定し,第1行為の持つ危険性の範囲を画定することが重要である!!
典型例 医療行為,自動車事故,鉄道事故など
*最決平成18年3月27日刑集60巻3号382頁[19]
⇒ 路上転倒かトランク内かという危険度の差があるとはいえ,危険が及ぶような態様で道路上に被害者を置いたという点で二重礫過の事案と共通する
イ 第三者の行為が故意行為であるとき
∴ 判例の中に因果関係を否定したものがあるため,最も問題となる
考慮要素 各行為の結果発生に対する影響(寄与)の度合いが最も重要であり,支配・利用・誘発などの関係の有無,介在行為の故意・過失や異常性も考慮
(6) 客観的帰属論[20]
ア 客観的帰属論の構造と機能
客観的帰属論は,3本柱から成り立っている。すなわち,①条件的因果連関,②危険創出連関,③危険実現連関―である。
イ 危険創出連関について
危険創出連関とは,当該行為が構成要件結果に対して,許されざる危険を創出した,と行為の時点で判断されるような行為と結果の連関が存在することをいう
ウ 危険実現連関について
危険実現連関とは,創出された危険が事後的に結果に実現した時にはじめて行為に結果が帰属されることをいう
エ まとめ
結果の行為への客観的帰責は,個別的・類型的に規範的に決定されるとする理論で,帰責限定理論が多く主張されている
*危険の創出や危険の実現を否定する理論
| 危険減少論 | 一見,結果に対して原因を与えているように思えるが,その行為をした結果,本来発生すべき危険を減少させて,それとは異なる結果を発生させる場合は,帰責できないとする理論 |
| 日常行為論 | AがBに包丁を売ったが強盗の道具に使われてしまい,しかも,そうなることを未必的に思っていても帰責を否定する理論 |
| 注意規範の保護目的論[21] | 2人の自転車乗りが無灯火で走行中,先行者が通行人と衝突したが,後行者が灯火していれば事故を防げた場合でも,後行者には過失は認められないとする理論をいう |
| 自己答責性論[22] | Aが激しい嵐の日に船頭Bに対して無理に頼み込んで出向したが船が転覆してAが死亡したケースでは,Bに帰責できないとする理論 |
| 遡及禁止論 | 他人の故意行為が介入したときは,因果関係が遮断される見解 |
* 客観的帰属についてのコメント
⇒ 山中の所論にかんがみ少し補足説明をしておこう。
1 客観的帰属の体系論的位置付け
まず,客観的帰属論の位置づけであるが,松宮説によれば,実行行為,結果,因果関係,客観的帰属-となるのであろうが,山中説によれば,実行行為,結果,客観的帰属-という理論構成になると考えられる。
もっとも,山中説も条件関係を問う必要があるとしているのであるから,松宮説に依拠して説明するのが分かりやすいであろう。
客観的帰属論の問題意識はある程度は明確である。というのも,従来,因果関係論においては,事実的因果関係と規範的因果関係が混同して用いられてきたわけである。相当因果関係説がそれであり,事実的な因果の存在が問われているはずであるのに,予見可能性を問題にしているという点でちぐはぐな点があったことは否めないわけである。
そこで,事実的な因果関係は条件関係説で終わらせて,規範的な因果関係は『客観的帰属』の問題と位置付けるのが非常に分かりやすいといえる。民事における医療訴訟などでも言われていることであるが,因果関係というのは,事実的な因果関係というよりも,むしろ,その結果をその行為に規範的に帰責してもよいのかという観点が重視されるようになってきている。規範的な評価の側面を重視し,因果関係という概念の制約から解放をしたのが客観的帰属であると位置付けることができると考えられる。
2 客観的帰属論の内容
客観的帰属について説明しよう。客観的帰属については,危険創出連関と危険実現連関-の2つがある。
(1) 危険創出連関
まず,危険創出連関では,行為自体の危険性を問題にしている。
たしかに,結果が発生していても行為自体に危険性がないというのであれば,帰責されないのは当然のことである。
この点,非常に理解が難しいのだが,答案上問題となるのは,山中282のいう『危険状況創出連関』に限られるものと考えられる。なぜなら,山中の問題とする『直接的危険創出連関』というのは,要するに事実的な危険性の有無を問題にしているところ,この判断はすでに実行行為性の判断で終了していると考えられるからである。
そうすると,答案上では,危険状況を創出する危険性があるかどうか-が問われることになるが,これは,法的な評価の問題であるから,現実の判断には困難が伴うものと考えられる。
理論的には,許された危険の理論が参考となる。要するに,行為者が許された危険の限度での危険しか発生させていないと規範的に評価されるのであれば,それは危険を創出したとはいえないと考えられる。
したがって,ここでは,いかなる程度に達していれば,「許されない危険」といえるのかが問題とされることになる。もっとも,現実的なあてはめで許されるか否かという観点のみで判断すれば足りるかというとそうでもないであろう。
すなわち,トランク事件を考えれば明確なとおり,監禁致死罪の規範の保護範囲として,どこまでの行為が致死の因果を認める行為か-という観点も必要と思われる。
それゆえ,ここでいう許された危険というのは,適用が問題となっている保護規範,例えば,監禁罪であればそれについて許されるか-という視点から判断されるということになると思われる。
(2) 危険実現連関
ア ざっくりとした整理
次に,危険実現連関について説明すると,これは,実行行為に内包する危険が現実的に実現化したといえるか-が問われると考えられる。したがって,かつての前田3原則がよりよくあてはまる問題といえるのであって,格別の説明を要しないであろう。
もっとも,ここで最も問題とされる危険実現否定のツールが遡及禁止論と自己答責性の理論-の2つであろう。要するに,他人の故意行為ないし過失行為,あるいは被害者の自由な意思が介在していると考えられるものについては,帰責を否定されるというわけである。なお,山中285をみると非常に細やかな類型に分けられているが,結局のところは,帰責を認めるものは,前田3原則の因果の過程をより詳しく説明しているにすぎず,他方,帰責を否定するものは結局のところ,上記の2つの理論で説明することができるものが多いと考えられる。したがって,これらの類型論にはそれほど有意義なものはないと考えられる。
イ 「誘発」という考え方
もっとも,因果関係を認める場合の因果の認め方の論証には注目すべき点が多い。
まず,山中は第1行為が第2行為を誘発したか否かで場合分けをしている。
(ア) 誘発していないケース
この点,第1行為が第2行為を誘発したわけではないケースの典型例として挙げられるのは大阪南港事件である。これは,前田3原則の観点からしても,介在事情の異常性として考慮されると考えられる。
このように見てくると,判例が利用する「誘発」という概念も前田3原則はよく整理していることが明確なように思われる。
このように,『誘発していない』ケースでは,客観的な因果性の程度,要するに寄与度がいずれが高いか-という観点から判断すればよいので,その因果性の判断はある程度割り切ったものとなり,それほどの困難はないと考えられる。
(イ) 誘発したケース
次に,『誘発した』ケースについて考えてみよう。
この点,第1行為が第2行為を誘発したというのであれば,結局のところ,結果に対する間接的な因果性は認められるということになる。
たしかに,このような類の事例では,大阪南港事件のように,客観的な両者の行為の寄与度を問題とすることにあまり意味がない。なぜなら,仮に第2行為の寄与度の方が高いと判断されても,そもそも第2行為は第1行為により誘発されたというのであれば,それは結局,第1行為の寄与度の方が高いという判断につながるからである。
(ウ) 誘発の判断基準
Ⅰ 判断基準
このように考えてくると,問題とされなければならないのは,『誘発』の程度ということになろう。
誘発の程度は,①介入の経験的通常性,②行為者がその潜在的危険をとくに認識・利用しているか-で判断することになろう。
Ⅱ 患者の治療妨害事件
この点,患者の治療妨害事件については,かかる誘発の程度が高い事案と位置付けることができる。
この事案では,もともと,第1行為,すなわち,行為者の暴行それ自体が被害者に死の現実的危険性を生じさせる寄与度の高いものであったという事情に加えて,そのような治療の拒否が行われるという行為が第1行為により誘発されるのも,さほど経験的通常性がないとまではいえない-という判断がなされたものと考えられる。
なお,この事例で注意すべきなのは,誘発の程度が高いか否かというのは,あくまでも付随的に位置づけであるという点であり,そもそも第1行為の客観的な寄与度あるいは原因力が高いということが判断には決定的な影響を与えているものと考えられる。
Ⅲ 高速道路侵入事件
この点で,誘発されたか否かが最も問題となるといえるのが,高速道路侵入事件と思われる。
この事案では,被害者は自動車に轢かれて死亡したのであるから,死亡の原因となったのは,自動車の運転手や高速道路に侵入した被害者自身の寄与度が圧倒的に高いといえる。逆にいえば,当初の暴行の寄与度は客観的にはそれほど高くないと考えられるわけである。
しかるに,当初の行為者に帰責することができるか-という点が問われなければならない。一般論でいえば,当初の暴行行為の寄与度は客観的には乏しいというのであるから,高速道路侵入事件は最高裁の事例の中でも因果関係が否定されても良かった事例であったとも位置付けることができよう。
この点,第1行為が被害者の高速道路の侵入を「誘発」したといえるかが問題となるわけであるが,上記のように,②の行為者が潜在的危険を利用していたとはいえないことになるので,問題となるのは①の介入の経験的通常性ということになるだろう。
では,誘発のメルクマールとして,介入の経験的通常性があるといえるかが問われる。この点については,物理的・心理的に準強制状態にあったことがその判断に重要である。また,その逃走路が唯一のものであれば,そのような逃走経路を辿ることも経験的通常性があるということになると思われる。
前田3原則でいえば,高速道路に侵入するということも異常とはいえないということになろう。
要するに,一般人の視点からみれば,高速道路に逃げるというのは,アンリーズナブルということになるが,リーズナブルか否かのみで判断されるわけではなく,当時の被害者の心理状態も考えて,当時,行為者の心理に与えられていた強制状態にかんがみれば,そのようなアンリーズナブルな行動も経験的通常性はあるという判断となろう。
ウ 心理的なつながり
これ以外に山中の指摘として傾聴に値すると思われるのが,第1行為の物理的因果によって第2行為が誘発された場合と第1行為とは物理的な因果性はまったくないが,心理的なつながりから第2行為を誘発したというケースを分けているという点である。
たしかに,前者は因果関係を認めることに異論はないが,特に,後者は心理的なつながりのみで第1行為に帰責するということは多いに問題があるのであって,類型化することによって高速道路事件の問題点を浮き彫りにするという観点からも一定の意味はあるように思われる。
3 まとめ
以上から,危険実現連関においては,次のことを考慮すべきである。
まず,①結果に対して第1行為がどれくらいの物理的因果を与えているか-である。物理的因果が強ければ文句なしで帰責して構わない。大阪南港事件がそうである。
次に,②物理的因果性が弱い場合には,第1行為が物理的に第2行為を誘発していないかを問うべきである。結局,「物理的」に第2行為を誘発したと評価できるのであれば,因果性を認めても構わないであろう。
次に,③同様に物理的因果性が弱い場合において,第1行為が心理的に第2行為を誘発するという場合である。この場合は,少なくとも心理的に強制している程度が問題とされるであろう。例えば,高速道路事件のように心理的強制が多ければ帰責も考えられるが,心理的強制の程度が弱ければ帰責は無理であろう。
なお,最後に留意しなければならないのは,現実の事例というのは,これらの複合形態により結果が発生するということが多いということである。例えば,夜間潜水事件では,たしかに,行為者の見失うという行為は,見習い指導者のミスを誘発する物理性があると言われればそうであるが,これも必ず誘発するというわけでもない。ただ,見習い指導者は行為者とはぐれて心理的に不安にもなるのであるから,心理的にミスをある程度は強制されているともいい得るわけである。判例は,こうした観点から帰責を肯定したものと考えられる。
第6 構成要件的故意Ⅰ(総説)
1 構成要件的故意の意義と体系的地位
(1) 故意は,その本籍を責任の分野に有している(責任要素)が,犯罪の成立要件を考える上では,まず,構成要件の要素(主観的構成要件要素)として考慮する(構成要件的故意がなければ構成要件該当性が否定される)。
(2) 構成要件的故意が肯定すれば,責任の要件の段階で,『違法性の意識』の観点も加味して,責任要素として故意(責任故意)の有無・程度を検討する
2 構成要件的故意の要素
構成要件的故意の要素が認められるには,行為者が自己の犯罪事実を認識し,かつ,これを認容していること―が要素となる
⇒ 行為者の認識した事実をスクリーンに投影することができるとすれば,それが当該の犯罪の構成要件に該当する客観的事実であることが必要
*行為の時点で現実的心理として故意が存在する必要
(1) 犯罪事実の認識・認容
ア 知的要素
構成要件的故意が認められるには,行為者が自己の犯罪事実を認識し,かつ,将来の構成要件的結果の発生やそれに至る因果関係の経路についての予見が必要(これをまとめて,『犯罪事実の認識』という)
イ 意思的要素[23]
犯罪事実の実現を積極的に意欲している必要はないが,少なくとも,犯罪事実が実現するならば,そうなってもやむを得ないと認容していることが必要
⇒ 認容説からは,認定された現実的心理の事実について,認識的要素と意思的要素を法的に評価して故意と認めるに足りるかが問題となる[24]
(2) 認識・認容の対象となる犯罪事実
ア 対象:客観的構成要件に該当する事実
原則:すべての認識が必要
構成要件的行為,行為の主体(特に身分),行為の客体,行為の結果,因果関係,行為の状況など客観的構成要件要素に該当する事実
例外:因果関係についての認識(因果関係の詳細な認識は不要)
因果関係の認識は,日常の生活経験に基づいて通常その行為からその結果が生じるという程度の因果関係の大綱の認識で足りる
イ 規範的構成要件要素の認識の程度[25]
刑法的評価の基礎となる社会的な事実関係について,一般通常人が知っているような意味・性質の認識が行為者にあったことが故意の要件(素人間の並行的評価)
Ex.「わいせつ」(175条)な文書販売の故意があるというためには,行為者が素人判断にせよ,その本についてみだらな性描写があるという程度の認識を有していることが必要であり,かつ,それで十分と解される
3 確定的故意と未必の故意
(1) 確定的故意と未必の故意との区別
確定的故意とは,行為者が犯罪事実の実現を確定的なものとして認識し,これを認容している場合をいう
未必の故意とは,行為者が犯罪事実の実現を可能なものと認識し,これを認容している場合をいう
*犯罪事実の実現が確定的と認識したかがメルクマール
BUT.両方とも故意の一種であり犯罪の成否には影響がない(量刑には影響)
(2) 未必の故意とその認定(状況証拠からの事実の推認[26])
① 凶器の種類や形状
② 犯行の態様
③ 攻撃の方向・強さ・執拗さ
④ 被害者に生じた傷害の部位・程度,犯行の動機など
4 法的評価における留意点
| ケース | 問題点 | |
| ① | 認識した結果発生可能性が低い | 認識した可能性の程度[27] |
| ② | 激情犯の場合 | 認識した意思の明晰性 |
| ③ | 自動車危険運転 | 被害対象の具体性 |
| ④ | 薬物犯罪の場合 | 対象物の属性認識の質と量[28] |
| ⑤ | 不作為犯の場合 | 行為意思が捉えにくい時があるので,意思的要素が問題になる場合が出てくる |
第7 構成要件的故意Ⅱ(事実の錯誤)
1 事実の錯誤の意義と問題点
発生した犯罪事実について故意の成立を認めることができるか,すなわち,発生した犯罪事実について認識・認容があったと評価することができるか。
問題は,認識していた犯罪事実と発生した犯罪事実との間にどの程度の一致が認められると構成要件的故意の成立は認められるか
2 事実の錯誤の態様と分類
(1) 具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤
(2) 客体の錯誤と方法の錯誤
(3) 因果関係の錯誤
因果関係の錯誤とは,行為者が認識したところと異なった因果の経過をたどって,結果的には,予期した構成要件的結果が発生した場合をいう
* 因果関係の認識は,大綱の認識で足りるので通常錯誤は生じない
* 仮に錯誤があってもその錯誤は重要でなく,故意の成否に影響を与えない
(4) 早すぎた結果発生
ア 定義
早すぎた構成要件の実現には,広義と狭義の定義がある。広義の早すぎた構成要件の実現とは,行為者が意図した結果の発生時点よりも早期に結果が発生してしまった場合をいう。これに対して,狭義の早すぎた構成要件の実現とは,実行の着手前に,意図した結果が発生した場合をいう
イ 問題の整理
基本的に,まず,実行の着手が認められるかを判断することになる。もし,この時点で実行の着手が認められないということになると,未遂罪も成立しないということになるので,予備罪を検討するほかはなくなる。したがって,実行の着手をどのように認定してゆくかが深刻な問題として提起される。そして,実行の着手が認められた場合は,広義の早すぎた構成要件の実現の問題となる。したがって,これは因果関係の錯誤のうち,時間的経過においてそれが早く実現されたものにすぎないから,因果関係の錯誤の問題として処理される
ウ クロロホルム事件の理解
この判例は,本来の実行行為以前の行為であっても,それと密接性がある行為があり,その時点で既遂の故意があれば,あとは因果関係の錯誤の問題として故意既遂罪の成立を認める趣旨
⇒ 判例は,危険性の存在だけで無限定に実行の着手を認めたものではなく,関連性や場所的時間的接着性によって,一定の限定を加えようとする趣旨
* 第1行為と第2行為との関連性が低い場合は,第1行為の時点で実行の着手を認めることはできない
エ 問題の位置づけをめぐって
狭義の早すぎた構成要件の実現をめぐっては,学説によってその位置づけがバラバラである。混乱するので整理してみよう。まず,私見は,構成要件的故意を認めるという見解に与している。したがって,構成要件的故意を認めない結果無価値の見解からすれば,少なくとも構成要件レベルでは,故意犯と過失犯との本質的な違いはなくなるということになる。これに対して,私見によれば,故意犯と過失犯は構成要件レベルでも違いが生じるということになる。そうだとすれば,第1行為の時点で過失犯の構成要件に該当するといっても,それは故意犯として構成要件に該当するわけではない。したがって,故意犯としての実行行為足り得るかという視点から論じられることになる。要するに,行為無価値的な見解からは,実行行為性の問題と位置付けられることになる。
これに対して,結果無価値論を前提とすれば,故意犯と過失犯には構成要件レベルでは違いがないということになる。そうすると,第1段階では,少なくとも過失行為の構成要件該当性はあるということになるはずである。そうすると,もうそれだけで構成要件レベルの問題はクリアされてしまうのである。そうすると,結果無価値論の立場からすれば,実行行為には何も問題はなく,後は故意があるか,という故意論の問題として処理されるということになる。ただし,この立場の理解が難しいのは,実務上故意の存在時点は実行の着手時点でなければならないということになっている。しかしながら,学者はその点をアバウトに理解しており,第2行為時点でもう故意があるのが明らかであるから,単に因果関係の錯誤として問題に思わないようである。私見がもし結果無価値論に与するとなれば,やはり第1行為時に実行行為性を認めるのであれば,第1行為時に故意が必要なはずであり,この時点でないのであれば,やはりせいぜい過失致死罪が成立にすぎないと思う。その時点で因果関係の錯誤の話しにするというのは違和感がある。この意味で結果無価値論的視点からの学説には解せないところがある。
* 事案の整理
| 殺人予備と過失致死にとどまるケース | 殺人と因果関係の錯誤となるケース |
| 妻Xが夫Yを殺す目的で毒入りワインを用意し戸棚にしまっていたところ,知らぬ間に夫が帰宅し勝手にワインを飲んで死亡したというケース | 最決平成16年3月22日刑集58巻3号187頁のように,行為者は,準備(予備)行為のつもりだが,その時点で結果発生の具体的危険性が生じた場合 |
| このケースでは,夫がワインを飲もうとした時点で殺人の実行の着手が認められる。しかしながら,実行の着手の時点で,妻には夫を殺す故意がない。 | 判例は,実行の着手を認めるのに犯罪計画という主観的なものまで考慮するので,その結果,実行の着手ありなら,故意は当然あるとなってしまっている |
*客観的に実行行為があり,その実行行為性の認識=故意があるのであれば,あとは因果関係の錯誤の問題にすぎない[29]
3 事実の錯誤の処理に関する一般的基準
(1) 事実の錯誤に関する学説
① 抽象的符合説
② 法定的符合説(⇒故意責任の本質とよくマッチしている)
③ 具体的符合説
(2) 事実の錯誤に関する判例・多数説の基本的立場
「法定の範囲内において一致すること」が必要
4 具体的事実の錯誤と法定的符合説
(1) 具体的事実の錯誤の処理をめぐる法定的符合説の問題点
犯罪成立しすぎで気の毒?
(2) 学説
① 数故意説(判例[30])
およそ「人」を殺す意思で,「人」の死亡又は死亡の危険の結果を生じさせ
た以上,認識していた犯罪事実について故意犯が成立するが,発生した犯罪事実についても,発生した死亡又は死亡の危険の結果の数だけ故意犯が成立
∵ 法定的符合説は,故意を構成要件の範囲で抽象化しているから,「一人の人を殺す」という形で限定を加える理由は乏しいとする(むしろ,客観面の実行の着手があるかや,量刑の問題として考慮すれば足りるとみている)
② 一故意説
5 抽象的事実の錯誤と法定的符合説
(1) 構成要件の重なり合いの基準
原則:故意否定
例外:「構成要件の実質的な重なり合い」(判例)
(2) 構成要件の実質的な重なり合いの認められる類型
① 基本構成要件と加重・減軽類型としての構成要件との関係がある場合
Ex. 殺人と同意殺人
② 一方の構成要件が実質的に他方の構成要件を包含する関係がある場合
Ex. 殺人と傷害致死,強盗と窃盗,強盗と恐喝,窃盗と遺失物横領
③ 客体の類似性,客体を除く他のTbの同一性,保護法益の同一性,罪質の同一性,法定刑の同一性の観点を総合的に判断
Ex. 虚偽公文書作成罪と公文書偽造罪,覚せい剤輸入罪と麻薬輸入罪,関税法上の覚せい剤輸入罪と麻薬輸入罪,覚せい剤所持罪と麻薬所持罪
(3) 抽象的事実の錯誤の類型とその処理
① 認識犯罪事実<発生犯罪事実
∴ 認識していた軽い犯罪事実のTb該当性あり
② 認識犯罪事実>発生犯罪事実
∴ 軽い発生犯罪事実についてTb該当性あり
③ 認識犯罪事実=発生犯罪事実
∴ 発生した犯罪事実についてTb該当性あり
第8 構成要件的過失Ⅰ(総説)
1 過失犯の意義と処罰
過失とは,犯罪事実の認識又は認容のないまま,不注意によって一定の作為・不作為を行うことをいう
2 過失犯の成立要件
(1) 過失犯の成立要件をめぐる問題点
210条の過失致死罪の構成要件は,「過失により人を死亡させた者」である。
この点,過失犯の重要な構成要件である『過失』は,その内容は具体的に規定されていない(開かれた構成要件)。構成要件の具体的要素は,判例や実務により補充されている
(2) 過失の具体的要素
過失とは,不注意によって一定の作為・不作為(過失行為)をすること
ア 不注意(注意義務を怠ること)⇒主観的Tb
不注意というためには,①当該状況の下で行為者に注意義務が発生しており,かつ,②行為者が注意義務を怠ったこと(注意義務の懈怠)が必要。さらに,③行為当時,行為者が注意義務を履行することが可能な状況も必要
Cf. ①の注意義務の内容
Ⅰ 結果発生を予見すべき義務(結果予見義務)
Ⅱ 結果の発生を回避すべき義務(結果回避義務)
Ⅲ 結果発生の予見可能性及び回避可能性
Cf. 新過失論
旧過失論と新過失論の対立は,結果予見義務か結果回避義務のいずれに重点を置くかという問題といえる。この点,新過失論は,過失は責任要素だけでなく,構成要件要素又は違法要素であるとして,注意義務については,結果回避義務を重視する立場といえるが,実務は結果回避義務を中心に判断している
イ 一定の作為・不作為(過失行為)⇒客観的Tb
過失行為とは,注意義務を怠ってした一定の作為・不作為をいう
(3) 過失犯の判断手順
|
①
|
②
|
||||
③ このような行為をしていれば,結果回避可能
と判明する
|
④
* 行為者は,結果回避義務を怠って,一定の行為をしたため,
構成要件的結果を発生させたとして,過失犯の成立が認められる!!
3 過失犯の成立要件に関する個別問題
(1) 予見可能性について
過失犯について予見可能性の有無は,重要な争点となる。そこで,予見可能性の有無が問題となる
ア 予見可能性判断の基準者
予見可能性の有無は,一般人の能力を基準として判断される
∵ 構成要件的過失は,その性質上あくまでも客観的見地から判断される
イ 予見の対象の具体性
a 問題意識
結果に対する予見可能性はどの程度のものである必要があるといえるか。この点に関して,予見は将来の事柄であるから,正確な予見を要求するのは不合理であり,ある程度抽象化して考える必要あり
b 抽象化の程度
例えば,過失致死の場合,およそ「人が死ぬ」ことについて予見が可能であったかについて問題にすれば足りる
∵ 故意の法定的符合性とパラレル
c 因果の経過
因果の経過についての予見可能性も,ある程度抽象化したもので足りる
(2) 注意義務について
ア 注意義務の具体的内容と発生根拠
実務上過失犯の大半を占める自動車事故に関する業務上過失致死傷事件においては,注意義務の具体的内容は,①減速徐行義務,②前方注視義務,③運転避止義務,④車間距離保持義務,⑤左右道路安全確認義務―のように類型化されている。
イ 結果予見可能性と結果回避義務との関係
結果の予見可能性がある場合は,原則として結果回避義務が生じるといってよいが例外的に予見が可能であっても,結果回避義務が生じない場合がある。例えば,患者の死亡がある程度の確率をもって予想される手術の場合,医師は,患者の死亡という結果発生に対する予見可能性があるといえるが,常に手術を回避するべき義務が生じるというべきではない。このように,予見可能性があっても,当該業種に必要な規則と注意とを遵守している以上,結果回避義務が生じない場合がある。これを『許された危険』といい,信頼の原則は,許された危険の一つの内容といえる
4 構成要件的過失の特殊形態
(1) 業務上過失
業務とは,本来人の社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為のうち,他人の生命・身体などに危害を加えるおそれがあるものをいう(211条)
(2) 重過失
重過失とは,通常の過失に比して,容易に結果の発生を予見することができ,かつ,容易に結果の発生を回避し得るのに,その注意義務を怠って結果を発生させた場合をいう
∵ 重過失は,結果予見の容易性や結果回避の容易性が理由
第9 構成要件的過失Ⅱ(過失犯に関する実務的諸問題)
1 信頼の原則
(1) 信頼の原則の意義と由来
ア 抽象的な定義
信頼の原則とは,「他人が予期された適切な行動に出るであろうことを信頼するのが相当な場合は,たとえその他人の不適切な行動と自己の行動とがあいまって法益侵害の結果を発生させたとしても,これに対しては過失責任を負わない」という法理をいう
イ 交通業過事件に限った定義
信頼の原則とは,「交通関与者は,他の交通関与者が交通規則その他の交通秩序を守るであろうことを信頼するのが相当な場合には,たとえ他の交通関与者の不適切な行動と自己の行動とがあいまって法益侵害の結果が発生したとしても,これに対しては過失責任を負わない」とする法理をいう
∵ 交通環境の整備や交通道徳の普及など一定の社会的環境が成立したという条件の下に,他の交通関与者が交通秩序を守ることについて信頼するのが客観的に相当と認められる場合は,他者の不適切な行動とあいまって事故が発生し,しかも当該事故発生の予見可能性自体は否定することができない場合であっても,結果回避義務の存在を否定する
(2) 信頼の原則と判例の立場
判例(最判昭和41年6月14日刑集20巻5号449頁)においても定着
(3) 信頼の原則の適用条件
① 行為者において,他の交通関与者が交通秩序に従った行動をとることへの現実の信頼が存在していることが必要(具体的事故の発生を未必的にせよ認識している場合は,注意義務が発生する)
② 信頼は,当該具体的交通事情から見て客観的に相当といえる必要がある
(Ⅰ 信頼の対象が歩行者という『人』である場合,Ⅱ 相手車両が交通法規に反する異常な行動をしている場合―は,信頼の原則の適用は許されない)
(4) 信頼の原則の他の分野への適用
Ex. 共同作業を前提とする危険な事務を遂行するような場合(相互に各人の結果回避措置を信頼しなければ事務は成り立たない)
2 段階的過失
(1) 段階的過失の意義と問題点
段階的過失とは,同一人の過失が2個以上段階的に積み重なって結果が発生した場合をいう
問題意識
段階的過失とは,結果と因果関係のある2つの過失がある場合,それが段階をなしている場合,いずれを過失犯として取り上げるべきかという問題
(2) 段階的過失に関する学説
① 直近過失1個説(遡及禁止理論の影響を受けた学説)
直近過失1個説とは,結果に直結する最後の過失(「直近過失」という)だけが,過失犯を構成する過失であると考える立場をいう
∵ 過失犯を構成する過失は,結果に対し直接の危険性を有するものでなければならないとしたうえで,同一人の過失が数個段階をなして存在していても,そのうち結果に対して直接の危険性を有する過失といえるのは,直近過失の過失行為のみ
② 過失併存説(因果性は程度問題という認識を押し進める立場)
過失併存説とは,結果と因果関係を有する過失は,いずれもが併存的に過失犯を構成する過失になり得ると考える立場をいう
∵ いずれの過失も,過失の具体的要素を具備しており,結果と因果関係を有する以上,過失犯を構成する過失を直近過失にのみ限定する根拠は乏しい
(3) 段階的過失の実務的意義と検討
● 過失併存説
× 事故と関連の薄い落ち度まで取り上げられ,争点が拡散する
↓
● 直近過失1個説は,効率的な審理が可能(多くの裁判官が共感)
× 前者の過失行為が結果への寄与度が高い場合に不合理な結果
↓
○ 原則として,過失併存説によって複数の過失の併存を許容しながら,直近過失1個説の趣旨にかんがみ,単なる縁由又は背景事情にすぎないと認められる過失行為は,訴因から除外していくべき
3 監督過失
監督過失とは,直接に結果を発生させる過失をした行為者に対して,これを監督すべき地位にある者がその過失を防止すべき義務を怠ったことを理由に過失責任を問われるという場合をいう
Ex. 最判昭和63年10月27日刑集42巻8号1109頁,最決平成2年11月16日刑集44巻8号744頁)
第3章 違法性
第1 違法性と実質とその判断
1 違法性の概念
違法性とは,行為が実質的に全体としての法秩序に反することをいう
2 違法性の実質
(1) 形式的違法性と実質的違法性
形式的違法性とは,行為が形式的に刑法上の行為規範に違反することをいう
実質的違法性とは,形式的違法性を基礎にして,さらに違法性の実質を追求することをいう
(2) 結果無価値論と行為無価値論
① 結果無価値論
② 行為無価値論
* 違法性の実質としては,結果無価値の要素と行為無価値の要素を否定できない。したがって,実質的違法性の中身とは,社会的相当性を逸脱した法益の侵害又はその危険性といえる
3 違法性の判断
(1) 違法性判断の構造
(2) 違法性の判断対象と判断資料
(3) 違法性に関する規範=全体としての法秩序
(4) 違法性の判断の特色
① 違法性の判断は,客観的になされる必要があり
② 違法性の判断は,存否のみならず強弱の程度についてもなされる
4 違法性阻却事由
(1) 違法性阻却事由の意義と基本的特質
ア 違法性阻却事由の意義
違法性阻却事由とは,構成要件に該当する行為について違法性の推定を覆して,行為を適法なものとする特別の事情のことをいう
イ 基本的特質
実質的違法性が阻却されるには,その行為が社会的相当性の範囲内にある,すなわち行為が社会倫理秩序の枠内にある必要がある
∵ 違法性が阻却される場合であっても構成要件該当性は認められる。そうすると,法益侵害の発生又はその危険という要素は存在するというべきであるから,違法性がないとすれば,行為に社会的相当性があるからというべき
(2) 違法性阻却事由の種類
① 正当行為(一般的正当行為)
② 緊急行為
第2 正当行為
1 法令行為
(1) 職権行為・権利行為
2 正当業務行為
3 労働争議行為
4 被害者の承諾
(1) 被害者の承諾の意義とその法的効果
被害者の承諾とは,法益の帰属者(法益の主体)である被害者が,自己の法益を放棄し,その侵害に承諾又は同意を与えることをいう
① 承諾がないことが構成要件要素となっている場合
② 被害者の承諾のあることが構成要件要素となっている場合
③ 何の影響もなし
④ 被害者の承諾が違法性の存否・強弱に影響を与える場合
(2) 被害者の承諾が違法性阻却事由とされる根拠[31]
被害者が保護されるべき利益を自ら放棄しているという面は確かに重要であるが,その承諾を得た動機・目的や,被害者の承諾を得てなされた侵害行為の手段・態様・程度をも総合的に考慮した結果,その行為が社会的に相当であると認められて初めて違法性が阻却される
(3) 被害者の承諾が違法性阻却事由と認められるための要件(実務)
① 承諾は,被害者自ら処分しうる個人的法益に関する必要
② 承諾自体が有効なもの,つまり判断能力のある被害者の真意に出たものである必要
* 真意に出たといえるかは,『法益関係的錯誤説』によって判断すべき
法益関係的錯誤説とは,処分する法益の存否,種類,質・量についての錯誤がない場合については,同意を有効とすべき学説のことをいう
∵ 同意とは,自己の法益の処分といえるから,処分する法益の認識について錯誤がないか否かを判断すべき[32]
* 『法益関係的錯誤説』の緊急状態仮想による同意の例外
法益関係的錯誤説によったとしても,緊急状態を仮装することによって得られた同意は無効とする議論をいう
∵ 緊急状態を仮装するのは,同意は強制と同じで不自由な同意だから
③ 承諾は行為の前に存在する必要
④ 承諾は外部的に表示されており,行為者は承諾を認識する必要あり
⑤ 承諾に基づいて行われる行為態様自体,社会生活上是認できる相当なものである必要
5 推定的被害者の承諾
6 治療行為
7 義務の衝突
8 安楽死・尊厳死
第3 正当防衛
1 緊急行為の本質とその基本的問題点[33]
必要性→緊急の場合は国家による救済は不可能
相当性→私人による法益侵害行為を広く許すと法秩序を害する
2 正当防衛の意義と本質
判例は,正当防衛を緊急行為の1つと理解しており,その緊急行為性を体現している要件が侵害の急迫性であると考えている(読本Ⅰ123)。正当防衛の本質をこのように位置付ければ,急迫性とは,実質的に見て保護の必要性がある緊急行為であるといえるか,つまり,生命や身体等に対する差し迫った緊急状態にあり,かつ,その緊急状態が法的な保護に値するか-を吟味する要件と解釈することができるわけである。
3 正当防衛の成立要件
(1) 急迫不正の侵害
ア 『急迫』の侵害
急迫とは,法益の侵害が現に存在しているか,又は間近に押し迫っていることをいう
問題意識 不正の侵害を事前に予期していた場合にも,急迫性はあるか
① 急迫性は,侵害が「意外な」ものであることを要求しない
∵ 予期された侵害を避けるべき義務を課する趣旨ではない
② その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思の場合
∴ 急迫性は否定
∵ 法の自己保全という本質に反する
イ 『不正』の侵害
不正とは,法秩序に反すること,すなわち違法と同義をいう
ウ 『侵害』
侵害とは,法益に対する実害又はその危険を生じさせる行為をいう
エ 緊急救助
* 急迫性についての考察
第1 はじめに
侵害の急迫性の要件について,判例を踏まえて考えてみよう。なお,以下の叙述は,筆者が院生時代に執筆したものに加筆したものであるから,理解の内容については,若干心許ないところがあるが,容赦されたい。
第2 検討
1 正当防衛の原理的根拠
まず,判例は,正当防衛を緊急行為と位置付けており,その解釈から導かれるのが急迫性の要件である。したがって,急迫性とは,法益侵害が現実に存在しているか,又は間近に差し迫っていることをいうものと考えられる。
具体的には,Yが侵害行為に着手し,又は着手に密着した状態に達していることが必要である。
2 急迫性の要件の論拠
(1) 急迫性の解釈
急迫性の要件との関係で重要であるのは,行為者の当該行為が緊急行為といえないのではないかという場合の理解である。すなわち,正当防衛が緊急行為とされ違法性が阻却される原理的な論拠は,「侵害が急迫であるため公的な救助,つまり警察に連絡する暇がなく,侵害者は法益を守るためには反撃的防衛行為をもって対抗するしかない」という緊急行為性に求められている。
したがって,法益侵害の危険が抽象的に存在しているにすぎない場合は,まず,警察官に対して助力を求めるという対処策が考えられるわけである。
読本Ⅰ123では,例えば,積極的加害意思で侵害に臨んだといえるかが争点となった事案であっても,以下のように場合分けすることができると指摘している。
* 読本Ⅰ123が提唱する類型
① 予期された侵害に出向いて積極的な加害行為を行った事例
② 侵害を予期しつつもその侵害を回避しないで待ち受けて積極的な攻撃を加えた事案
③ 相手から先に攻撃されてから積極的に反撃を開始した事案
この点,上記のうち,②と③については,「緊急行為性がない」といえるのかについては,①と比較して慎重な検討が必要であると考えられる。そして,判例や学説上でも,「積極的加害意思がある場合は急迫性を欠く」という問題の立て方がされる場合が多い。
しかしながら,行為者の内心の事情を探るということにはそれほどの意味はなく,むしろ,被告人の攻撃準備の有無・程度,被告人の攻撃の時期・内容,侵害に臨んだ理由,相手からの侵害の予期の確実性,相手方の攻撃に至る経緯などの客観的事情を総合的に判断して,緊急行為性があるといえるか,突き詰めれば,反撃的行為をもって対抗するしか手段が残されていないのか-を問題とすべきものと考えられる(読本Ⅰ123)。
(2) 考える視点として重要であるもの
以下で筆者がかつて検討したものを修正しつつ検討してゆきたいと思う。繰り返しになるが,最も重要であるのは,なぜ故に正当防衛は違法性を欠くのかという原理的根拠である。
この点は,学説においては,利益衡量説に法確証の原理を加えたもので説明する見解が多いということになるが,かかる原理的な理解は判例の緊急行為性とは理解の仕方が異なるということにも留意しておくべきであろう。すなわち,学説は,急迫不正の侵害をする者に対してフォーカスをあてていると考えられるのに対して,判例はむしろ,防衛行為をする側にフォーカスをあてていると考えられる。判例と学説の対立の出発点は,原理的な理解の違いに由来するものも少なくないわけであり,いかなる原理に理論的根拠を求め,侵害の急迫性を理解するのか-を明確にする必要がある(読本Ⅰ124)。
3 考え方
上記の類型において考えると,「侵害を予期していたか」という観点から,①②グループと③グループに分けることができる。当然のことであるが,侵害を予期してないのであれば,緊急行為性があるといわれる可能性が高いであろう。問題は,「侵害を予期している」場合ということになる。
(1) この点について考えると,侵害を予期していたのであれば,そのような不正の侵害は,いわば「分かっていたこと」が現実化したにすぎないということになる。そうだとすれば,緊急行為性,突き詰めれば,防衛行為をするしか方法がない-といえるかについては,疑問が生じてくる。具体的には,Ⅰ警察に通報して警備してもらう,Ⅱ襲われる前に避難する-というように,防衛行為をする以外の方法がいくつかうかんでくるわけである。
(2) では,上記Ⅰ及びⅡを侵害の被害者である防衛者に対して求めることが,正当防衛の論拠や他の保護されるべき利益との関係で相当といえるかについて考えてみよう。
ア Ⅰについて
たしかに,自力救済禁止の理念からすれば,例えば,Xが「Aに襲われる。殺されるかもしれない」と考える場合は,警察に保護してもらうというのが現実的であろう。したがって,Xに対しては,警察に連絡して保護してもらうことができるのであればそうすべきなのが適切であろう。
このような視点からすれば,「侵害を予期していること」及び「警察に保護してもらうことが現実的に可能」という事実が揃えば,正当防衛の違法性を阻却する原理である緊急行為性が妥当しないということになると考えられる。したがって,この場合は急迫性が否定されると考えられる。ただし,国家機関に対して助力を求めることが事実上できない場合や期待できない場合に関しては例外的に侵害を予期している場合であっても,国家機関に対して助力を求めずに正当防衛を行うことができると考えてもよいであろう。
以上をまとめると,「侵害を予期していること」に加えて,「警察に連絡して保護を求めることが現実的に可能」という事実があれば,急迫性は否定される。
イ Ⅱについて
では,襲われる前に避難を求めるということも,「防衛行為をする以外の方法」にあたるのであろうか。
(ア) 危険に自ら接近する場合
たしかに,避難をすれば不正の侵害から逃れることができるのであれば,緊急行為性を否定する事情にはなり得ないわけではない。例えば,台風が接近していたとしても,あらかじめ天気予報でそれが予測できており,遠くの実家に避難していれば,その避難した人にとっての緊急状態というのは存在しないといえるわけである。しかしながら,突き詰めて考えると,以下の点も考慮しなくてはならないように考えられる。すなわち,ある危険があるとしても,「自分から危険に近付く場合」と「向こうからいわば危険が近付いてくる場合」を分ける必要があるという点である。
例えば,Xが危険であると予期しながら,危険が存在する場所に向かうということは,いわば,危険を自分で招いていると評価することもできる。そうすると,「危険な場所にはいかない」という防衛行為をする以外の方法があるということになると考えられる。したがって,自ら危険に近付くという場合は,緊急行為にあたらないので,急迫性が否定されることが多いと考えられる。
(イ) 危険が向こうからやってくる場合
これに対して,危険が向こうからやってくるという場合はどうであろうか。防衛行為をする以外には避難をするしかないのであるが,逆に考えると,防衛者はどこに避難すればよいのであろうか。上記では,台風からの避難の例を挙げたが,このように都合のよい場所に避難する場所がある-という者はそれほど多くはないと考えられる。そうだとすれば,Xの自宅に深夜2時ごろ,突然電話がかかってきて,「お前を殺してやる」と言われた場合に避難をしなければならず,Xは侵害者に対して反撃を加えることは許されないという結論が妥当であろうかということを考えてみる必要がある。この場合は,深夜であるから,そもそも人間が移動するにはあまり向いていない時間である。例えば,Xが自動車を有していればよいが,自動車をもっていなければ遠くに避難するといっても無理である。では,徒歩で真夜中に逃げることを求めてもよいものであろうか。考えてみれば,殺害を意図する者からすれば,対象者を「監視されている」という心理状態に置き,自宅から避難するところを殺害するという例も少なくないとされる。突き詰めれば,自宅から避難を求めるとかえって,危険を助長するということになることも考えられる。
このように考えれば,自宅から避難をしてもらうという場合は,「防衛行為をする以外の方法」にあたらないと解される。したがって,この場合は,Xが侵害を予期している場合にあたるが,自宅から避難をしなかったということをもって急迫性の要件が否定されるということはないと考えられる。この場合は,警察に通報をすることが現実的に可能であったかが問われるということになると考えられる。
(3) まとめ
まとめてみると,侵害を予期している場合は,一般論として防衛行為をする以外の方法を採りやすいということができる。したがって,緊急行為とは言いがたいことが多いので,急迫性が否定される可能性があるわけである。
突き詰めると,防衛行為をする以外の方法とは,警察に保護をしてもらうということのみが考えられる。しかも,この保護してもらうことが現実的に期待できる場合のみ,防衛行為をする以外の方法にあたると考えられる。逆にいえば,警察がすぐに自宅に来て保護をしてくれないというような事情がある場合は,抽象的に保護の可能性があったとしても,もはや防衛行為をする以外には方法はないという事態に立ち入っていると考えることができる。
4 侵害予期の程度
このように,「侵害を予期している」場合は,侵害を予期していない場合と比較して,急迫性が否定される可能性が高まるわけであるが,では,どの程度,具体的に侵害を予期している必要があるのであろうか。
防衛行為をする以外の方法とは,警察に保護を求めることであるから,警察に24時間警備をしてもらえることの具体的な侵害の予期でない限りは,「侵害を予期している」とするべきではないと考えられる。仮に,抽象的な危惧感で警察に通報したとしても,現実的な保護は期待することができないことから考えても妥当であろう。したがって,侵害の予期とは,定義付けすれば,「相手の攻撃の内容を十分予想し,かつ,その攻撃を確実なものとして予期している」ことをいうと考えられる。逆にいえば,それに達しない程度の侵害の予期は,刑法上の意味のある「侵害の予期」とはいえないと考えられる。
5 判例の理解の仕方
典型的なケースでは,積極的加害意思が認められた最決52年のケースであてはめてみよう。このケースでは,これまでの検討から理解できるように,『積極的加害意思』があるから急迫性が否定されたという論理関係にないことをまず確認しておく必要がある。
積極的加害意思の有無というのは,「法益侵害が間近に差し迫っているが,他方で相手方の攻撃の内容を十分予想し,その攻撃を確実なものとして予期していたケース」であることが,「なんとなく」多い,という意味にすぎないわけである。たしかに,複雑な説明を避けるという意味では,『積極的加害意思』というテクニカル・タームとしての意味は認められるが,その使用がブラック・ボックスに入ったものにならないように留意しなければならない。
このケースでは,対立セクトの攻撃が予想され,鉄パイプなどを準備していたところ,1回襲撃がなされ,再度の襲撃も必至という事情があったとされている。このような点に照らすと,たしかに,一度襲撃があったとしても,Xが被ったダメージの程度が軽微である場合は再度の襲撃はあり得るところであるし,それを裏付けるような過激派の一派であるという事情もある。そうすると,少なくとも,Yが侵害行為を行う高度の蓋然性が認められるといえ,急迫不正の侵害が間近に差し迫っていると評価することは可能である。
ところが,他方で,本問の場合は,襲撃が予想される程度がかなり高いことが分かる。すなわち,侵害の内容としては,前回と同様の態様で対立セクトの学生から襲撃を受けることを容易に認識しているといえる。また,事案の概要からは定かではないが,『再度の襲撃が必至』という客観的事情があったものと予測される。このような事実関係の下においては,Xは侵害行為を具体的に予想していたといえよう。このことは,Xが襲撃に備えて武器を準備していたことからも明らかということができる。
そうだとすれば,防衛行為をする以外の方法として,公的助力を求めればよかったわけであるから,緊急行為とはいえないと考えられる。突き詰めると,Xは,なぜ警察に通報しなかったのかを考えれば,「自分でYを成敗してやりたかった」からと考えられる。そうすると,Xの防衛行為は,正当防衛を藉口した単なる加害行為にすぎないと理解される。
このような理論的な意味で判例は『急迫性』を否定したものと考えられる。
6 侵害を予期していないケース
(1) 基本的な視点
侵害行為を予期していない場合は,上記では,一般的に急迫性は認められやすいと述べたが異論のないところと考えられる。すなわち,寝込みを襲われたのと同じように,防衛者にとって不意打ちであることが多いからである。
そうだとすれば,侵害を予期していなかったといえる場合ではあるが,積極的な加害にでた場合という上記③のケースをどのように理解すればよいのかを考えてゆく必要があろう。
(2) この場合は,各自の検討に委ねることにしたいが,判例は,防衛の意思を欠くという手法で処理をしているものと考えられる。いずれの要件によって,処理をするかは重要であるが,それ以上に重要なのは原理的に正当防衛といえるかをまず確定して考えることである。そうすると,寝込みを襲われたものの,防衛者として侵害者を退治する余裕があるところ,よく見れば,防衛者が個人的に恨みを持っている人物が侵害者であるから,この際,この機会に殺してしまおうと決意したという場合が典型例である。原理的に考えれば,このような場合は,そもそも客観的に緊急状態に陥っていることは間違いがないが,主観的には緊急状態に陥っていないという場合である。この点について,考えれば,強盗罪の反抗抑圧の論点と理論構造がよく似ている。つまり,一般人を基準に考えれば,緊急行為が許されるにもかかわらず,その防衛者が強じんな人物であったために,防衛行為を許してはならないということになるかが問題である。
考えてみれば,これは緊急行為が認められる必要がある。というのも,急迫性の論点で考えれば,「防衛行為をする以外の方法」があれば緊急行為とはいえなくなるのであるが,逆にいえば,それは避難することを含まないわけである。
これとの均衡から考えると,いくら肉体が貧弱な侵害者であったとしても,防衛者に避難を求めることができないのは当然のことと考えられる。では,防衛者にとっては,肉体が貧弱な侵害者であれば,「攻撃を受けることを受忍すべき」といえるかを考えれば,いくら圧倒的な体力の差があったとしても,防衛者が不正な侵害を受忍すべきとまではいえないはずである。したがって,結局,正当防衛を認めるというのが理論的に正しいと考えられるわけである。判例もこれを裏付けるように,侵害を予期していない場合の積極的加害行為は,防衛の意思の問題と理解しながらも,防衛の意思をほとんど無内容にとらえることにより,簡単に防衛の意思を認める傾向にある。付け加えると,このように,防衛の意思を無内容にとらえることに批判的な学説もあるが,これは,行為無価値とか結果無価値という理論的な対立に目を奪われるあまり,正当防衛の原理的根拠を失念した議論といわざるを得ず,主張自体失当である。
(3) まとめ
ア 以上の視座からすれば,侵害を予期していないという事実があれば,原理的には正当防衛を認めてよいはずであり,それにそった形で刑法上の要件を解釈して,あてはめてゆくべきと考えられる。
イ まとめると,侵害を予期していない事案を処理するにあたって問題となるのは,基本的には正当防衛が認められると考えつつ,本当に急迫不正の侵害があるといえるか,すなわち,「侵害行為の有無」が重要な解釈論上の位置付けとなると考えられる。この場合は,「侵害行為が始まったと評価できるか」,あるいは,「侵害行為が終了していないか」という認定が重要であろう。
ウ 敷衍して説明すれば,侵害を予期していない場合は,基本的に正当防衛が認められるに決まっているわけである。したがって,「急迫性」とか,「防衛の意思」を長々と検討する者は,「正当防衛の理論的論拠を理解していない」と評価される恐れがあることに十分留意すべきである。
侵害を予期していない場合は,そもそも,侵害が始まっているのかが論点となることがある。これは,急迫性の定義にも現われているように,急迫不正の侵害は将来に対するものであっても,「高度の蓋然性」があればよいわけである。したがって,将来の急迫不正の侵害があったとされる場合はこの点を検討する必要があると考えられる。
エ 次に,相手方が侵害行為が終わっていないかという視点である。問題を作る側からすれば,侵害を予期していない場合に,いかにも侵害行為が存在するケースを出題するとは考えられない。つまり,いかにも侵害行為があるように思われるときは,「実は,侵害行為は終わっているのではないか」ということを疑うべきなのである。過去の侵害行為に対する正当防衛を認める意味はないであろうから,過去の行為であれば,原理的にも正当防衛と認められないのは明らかといえよう。この場合は,再攻撃が始まる可能性なども考慮して総合的な判断をしてゆくことが望まれよう。
第3 結語
以上のように,正当防衛の検討は,原理的にまずどうであろうかを検討し,問題があると思われる事実関係を問題にする要件はなにかという観点から検討してゆくことになると思われる。正当防衛は,ケース全体を通しての規範的,実質的判断であるにもかかわらず,「要件を表面的にしか理解」(読本Ⅰ125)していない者が多すぎるとされるので,特に留意すべきといえよう。
(2) 防衛の意思
ア 防衛の意思の要否
判例は,必要説に立っているが,その内容を希薄化する傾向にあり,その関連で今日では必要説と不要説の際は実質的には差異がなくなりつつある
イ 防衛の意思の具体的内容[34]
防衛の意思とは,自己が急迫不正の侵害にさらされていることを意識し,かつ,その侵害を排除するために加害者に立ち向かう意識をいう
∵ ● 急迫不正の侵害を認識しているだけで足りる
× あえて防衛の意思を必要とする意味なし
↓
● 積極的で明確な動機・意図が必要
× 正当防衛は本能的に行われるのでこのような意思はないのが通常
↓
○ 侵害に対向して権利を防衛するために出たという性質を行為に付与するような内心の状態で足りる
ウ 積極的加害意思[35]
積極的に加害行為に出たという防衛行為を藉口して実際は殺人をしたというようなケースでない限り,防衛の意思は攻撃の意思と両立するので,防衛の意思が否定されることはない
エ 『攻撃の意思』と各侵害の急迫性の要件及び防衛の意思の要件との関係
● 攻撃の意思の問題はすべて防衛の意思の要件の関係のみで認めるべき
× 防衛の意思の要件と侵害の急迫性の要件を同一平面でとらえている
↓
○ 反撃行為以前の加害意思⇒急迫性の問題
反撃行為以前の加害意思なし⇒防衛の意思の問題
∵ 両者は,その要件を検討すべき時点を異にしている(防衛の意思の要件は,反撃行為の実行時が問題とされるのに対して,急迫性の要件は,反撃行為以前の段階,つまり反撃の予備又は準備段階が問題とされる)
(3) 反撃行為
防衛行為は,侵害者に対して向けられた反撃行為である必要があり,第三者に向けられる場合は正当防衛とはならない
論点 行為者としては反撃行為の意図で行った行為が結果として第三者の法益を侵害してしまった場合
● 緊急避難説
× 緊急避難とするのは誤想防衛との関係で権衡を失する
○ 一種の誤想防衛と扱ってよい
∵ 認識と客観的事実との間に錯誤が存する場合として,誤想防衛に類似
(4) 防衛行為の相当性
ア 定義
「やむを得ずにした」とは,急迫不正の侵害に対する反撃行為が,自己又は他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること,すなわち,反撃行為が侵害に対する防衛手段としての相当性を有することをいう
イ 考慮要素
① 侵害にさらされている法益の種類
② 侵害行為の態様や激しさ
③ 侵害者の凶悪性・危険性
④ 侵害行為による被害が事後において回復可能か
⑤ LRAはあるか
4 正当防衛に関する2つの実務的問題
(1) 自招の侵害(自ら招いた正当防衛状況)と正当防衛
ア 挑発行為が故意
正当防衛に名を借りて相手方を侵害しようとし,故意に相手を挑発するような場合は,侵害の急迫性の要件を欠く
イ 挑発行為が過失
自ら目に多相手の侵害に対して反撃行為を行うことが正当防衛権の濫用に当たると評価される場合を除いて原則として正当防衛が許される(権利を濫用したかは,侵害行為が予想以上に重大であったかによる)
(2) けんかと正当防衛
部分的には防衛行為の観を呈していても,全体的に観察する限りは,それらの行為も全体として攻撃行為の一環をなすのが通常
⇒ 急迫性や防衛の意思を欠いて正当防衛の成立は否定されるべき(ただ,判例は,状況の変化があった場合には正当防衛成立の余地を認めている。例えば,初めは素手で殴り合っていたのに,突然一方がナイフを出してきた場合)
(3) 最決平成20年5月20日刑集62巻6号1786頁
ア 事案
道路上において,自転車にまたがっていたVと,たまたま徒歩で通りかかったAが言い争いになった。Aは,いきなりVの左ほおを手けんで1回殴打して,直後に逃走した。これに対してVは,自転車でAを追跡し,殴打現場から90メートル離れた先の歩道上でAに追いついた。Vは,自転車に乗ったまま,水平に伸ばした右腕で,プロレスのラリアットのような形で被告人を強く殴打した。Aは,前方に倒れたが,起き上がり,携帯していた特殊警棒でVの顔面を数回殴打し,傷害を追わせたもの
イ 判旨
「Aは,Vから攻撃されるに先立ち,Vに対して暴行を加えているのであって,①Vの攻撃は,Aの暴行に触発された,その直後における近接した場所での一連,一体の事態ということができ,Aは不正の行為により自ら侵害を招いたものといえるから,②Vの攻撃がAの前記暴行の程度を大きく超えるものでないなどの本件の事実関係の下においては,Aの本件傷害行為は,Aにおいて何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえないというべきである」
ウ 調査官解説の要点
自招侵害について,学説では,①防衛の意思がない,②急迫性がない,③侵害が不正ではない,④防衛のための行為とはいえない,⑤防衛行為としての相当性がない,⑥権利の濫用である,⑦社会的相当性に欠ける,⑧原因において違法な行為である―とする見解がある。
自招侵害について,調査官解説は,「事案によって,そのポイントとなる点が必ずしも同じとはいえず,特定の1つの要件で説明しようとすることは必ずしも実際的ではないように思われる」と指摘している。そのうえで,調査官解説は,上記の学説の中では,急迫性を否定する②の見解が有力であると指摘するが,「侵害行為の程度がそれに先立つ自招行為によって通常想定される程度を大きく超えていなければ急迫性がないのに,大きく超えている場合は侵害自体があることは予期していたとしても急迫性があると説明し,急迫性を量的な概念のように用いることとなるなど,やや技巧的な面がないとはいえない。また,侵害行為に急迫性がないというためには,被告人において侵害行為を予期していたことが重要な意義を有するものと考えられるが,予期といっても,時点によってその程度は異なり得るものであるし,本件事案についてもいえるように,情況を総合しての評価的な認定にならざるを得ない」と指摘している。そして,このような観点からすれば,「急迫性の要件は判断基準としては,必ずしも有効ではない」としている。
本判決は,正当防衛の各要件のうち,いずれが欠けるとの理由付けをしていない。そして,より実際的な判断の枠組みを示している。
すなわち,①不正の行為により自ら侵害を招いた場合―は,特段の事情のない限りは,正当防衛が認められる情況ではないと理解していることになる。そして,①の要件に該当する場合であっても,②相手方の攻撃が被告人の暴行の程度を大きく超えるようなときは,その特段の事情があるものとして,正当防衛を認める余地があると理解している。調査官解説は,要件①について,「正対不正の関係ともいうべき正当防衛を基礎付ける前提が基本的に欠けているといえるから,このような思考方法は,正当防衛の規定の趣旨に沿ったもの」と評価している
5 過剰防衛
(1) 過剰防衛の意義
(2) 過剰防衛の類型
ア 質的過剰
イ 量的過剰
(ア) 定義
量的過剰とは,当初は防衛の程度の範囲内にある反撃であったが,反撃を続けるうちに,相手方の侵害が止み又はその程度が著しく弱まったのに,なおそれまでと同様の反撃を続けた場合をいう
問題意識 正当防衛行為⇒過剰防衛行為への移行をどのように擬律するか[36]
前後に分断することなく,その一連の行為を全体として防衛の程度を超えたものとして扱い,全体として過剰防衛の成立を認めるべき
(イ) 考え方
侵害行為の終了後に行われた反撃行為については,正当防衛はもとより過剰防衛も論じつ余地はないとの考え方もある。しかし,このように厳格に考えると,当初の正当防衛行為から勢い余って過剰な行為に及んだ者にとって,酷な結果となることが多い。そこで,判例は,「侵害行為の継続性」の認定を緩やかにすることにより対処している。具体的には,実質的には侵害行為の終了後に引き続き行われた反撃行為を,それ以前の正当防衛行為と全体的に観察して1個の過剰防衛の成立を認めるものと理解
20年6月25日判例は,時間的,場所的には連続していても両者の間には断絶があり,急迫不正の侵害に対して反撃を加えるうちに,その反撃が量的に過剰になった者とは認められない場合,具体的には,正当防衛行為から勢い余って過剰な行為に及んだとはいえない場合には,両暴行を全体的に考察して1個の過剰防衛の成立を認めるのは相当ではないとの考え方を前提とする(調査官のコメント)
(3) 過剰防衛の効果(36条2項)
6 誤想防衛・誤想過剰防衛
(1) 誤想防衛の意義と類型
| 急迫不正を誤信 | 反撃行為が変な方向へ | 過剰性の認識なし |
| 誤想防衛の典型 | 侵害者に対して反撃行為を行うつもりが,客体の錯誤又は方法の錯誤により第三者に対して反撃行為をした場合[緊急避難説もあるが実務は誤想防衛説が相当] | 典型的な過剰防衛の事案ながら,反撃行為について過剰性の基礎となる事実についての認識がない場合 |
(2) 誤想過剰防衛
(3) 誤想防衛・誤想過剰防衛の処理
7 盗犯等防止法における正当防衛の特例
第4 緊急避難
1 緊急避難の意義と法的性質
2 緊急避難の成立要件
(1) 現在の危難
(2) 避難の意思
(3) 避難行為の相当性
ア 補充の原則
イ 法益権衡の原則
3 「業務上特別の義務がある者」についての緊急避難の特則
4 過剰避難・誤想避難
第5 自救行為
1 自救行為
2 自救行為の許容性とその要件
① 権利に対する侵害がなされていること
② 被害回復の緊急性があること(法律上の救済を待っていては,時期を失して当該権利の回復が事実上不可能となるか又は著しく困難であるか)
③ 自救の意思があること
④ 自救行為自体相当性を有していること
3 自救行為に関する判例
第4章 責任
第1 責任の本質とその判断
1 責任の意義と責任主義
(1) 責任の意義
責任とは,違法行為をしたことについて,その行為者を非難しうること,すなわち,行為者に対する非難可能性をいう
(2) 責任主義
責任主義とは,違法な行為について行為者に避難を加えることができるときに初めて犯罪は成立し,その責任の限度で刑罰を科することができるという考え方をいう
① 帰責における責任主義
帰責における責任主義とは,主観的かつ個人的責任がなければ帰責しえないという考え方をいう(⇒結果責任及び団体的責任の排除)
Ⅰ 主観的責任
主観的責任とは,行為者に責任能力及び故意・過失があって,行為者を非難できる場合のみ責任を課し得るという考え方をいう
Ⅱ 個人的責任
個人的責任とは,個人はその犯した犯罪についてのみ責任を負い,他人が犯した犯罪について責任を課されることはないとするものをいう
② 量刑における責任主義
2 責任の本質
(1) 道義的責任論
道義的責任論は,責任の本質は,犯罪は人間の自由な意思決定により行われるところ,そのような悪い意思決定を行ったことについて道義的に非難される点にあるとする
∵ 19世紀的思考が前提(=非決定論が前提)
(2) 社会的責任論
社会的責任論は,責任の本質は,行為者の性格の社会的危険性にある
∵ 20世紀的思考が前提(=決定論が前提)
(3) 人格責任論(折衷説)[37]
第一次的には,行為者人格の主体的現実化としての行為に着眼すべき
第二次的には,行為者の主体的選択により形成された潜在的な人格体系があり,そのような人格形成をしたから行為者を非難できると解する。前者を行為責任,後者を人格形成責任といい,二つ併せて人格責任という
3 責任のとらえ方=規範的責任論
4 責任の判断
(1) 責任の判断対象と判断資料
① 責任能力
② 責任故意・責任過失
Ⅰ 責任故意について
責任故意とは,行為者の違法性の意識又は違法性の意識の可能性を有していたかという規範的側面について検討をすることをいう[38][39]
Ⅱ 責任過失について
一般人に予見可能性が認められ,かつ注意義務を負わせることができたとしても,当該行為者が一般人よりも能力が劣るため,結果の発生を予見できず,また注意義務を尽くすことができないのであれば,その者に非難可能性を認めることはできない
③ 期待可能性
期待可能性は量刑考慮の事情にとどまる
④ 行為者の人格形成に関する一切の事情
第2 責任能力
1 概論
責任能力とは,行為者の有責に行為をする能力のことであり,行為者を非難する前提となっている。このことは,刑法39条をみてみても理解することができる。すなわち,刑法39条は「心神喪失者の行為は,罰しない」と規定しているところ,これは正当防衛や緊急避難のように行為の客観的な側面に着目して可罰性を否定するのではなく,むしろ,行為者の主観面に着目して可罰性を否定していることが分かる。そうすると,行為者が一定の能力に満たない場合には刑罰を課すことができないとすることを前提としていることが理解できるわけである。
ただし,刑法の規定をみてみても,その一定の能力とは何かは明らかにはならない。そこで翻って考えてみると,刑法というのは故意処罰の原則を採っている(38条1項)。その論拠は,故意の場合は,「犯罪事実を認識して規範の問題に直面したにもかかわらず,あえて犯罪行為に及んだ」から強い非難が成り立つからである。これとの関係でいえば,①犯罪事実を認識する能力がない場合,②犯罪事実を認識してもその認識に従って行動することができない場合―は,上記の命題が成り立たないということになる。したがって,そのような場合には非難が成り立たないことが分かる。そこで,心神喪失者の定義というのは,この点を反映させ,「精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力がなく,またはこの弁識に従って行動する能力のない状態」と理解されている。
責任能力の判断については,①生物学的要素と②心理的要素があるというように説明されている。もっとも,上記①は,心理的要素の原因と位置付けられているものにすぎない。したがって,「精神の障害」があるとされていても,それが当該犯行について因果性を与えていない場合も考えられる。そうすると,例えば,「統合失調症であれば,心神喪失にあたる」というような命題を承認することはできないということになる。あくまでも,①事物の理非善悪を弁識する能力があるか,②弁識に従って行動する能力があるか―という点を中心に判断してゆくのが,責任主義に忠実であると考えられる。
判断の構造としては,中心に,上記①と②があるところ,そのいわば間接事実的な位置付けとして,Ⅰ「精神の障害」とⅡ「行動の了解可能性」があるという関係と理解しておけばよいであろう。すなわち,上記Ⅰが統合失調症のように強度なものであれば,その実証的研究からも行為者の行動に影響が与えるものであると一般に理解されていることから,上記①及び②について消極な判断を導きやすいものと考えられる。また,行動が合理的で了解可能ということは,規範を認識しつつ犯罪を行う行為としての合理性を問題にしているわけであり,「了解可能であれば,犯罪をしようという意思に従って行動する能力はあった」と位置付けられるのであるから,上記②を積極方向に導くという要素と理解することができよう。おおむね,以上のような構造を理解して細かい点について理解してゆくと良いであろう。
2 最判平成20年4月25日刑集62巻5号1559頁について
(1) 判旨
① 責任能力判断の前提となる生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度について,精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所はその意見を尊重して認定すべきである
② 統合失調症の幻覚妄想の強い影響下で行われた本件傷害致死の行為について,それが犯罪であることを認識し,後に自首しているなど,一般には正常な判断能力を備えていたことをうかがわせるからといって,そのことのみによって,その行為当時,被告人が心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めることは困難である
(2) 本判決の趣旨
そもそも,この判決は,「生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素(弁識能力と制御能力)に及ぼす影響の有無及び程度については,あくまで証拠に基づく判断である必要がある。したがって,その証拠の評価についても合理性が要請されるものと考えられるという趣旨を判示したものである
(3) 統合失調症に罹患している者の責任能力
ア 心神喪失
①統合失調症の程度が重症であるか,②統合失調症による幻覚,妄想などの病的体験に直接支配された犯行である場合
イ 心神耗弱
アほどではないが,①病状と病状への犯行に対する影響を加え,②犯行動機の了解可能性,③犯行に至るまでの事情,④犯行の態様,⑤犯行後の言動,⑥犯行当時についての記憶,⑦病前の性格と犯行との関連性などの記述的要素を認定する
⇒ 規範的な立場から評価を加えて,弁識能力・制御能力の有無・程度を確定し,心神喪失・心神耗弱を認めるかどうか判断される
* ただし,諸事情を総合考慮するといっても,統合失調症の患者については,動機が了解可能のように見えて,実際は不合理なこともままあるとか,知能・知識,記憶は障害されていないことが多い,犯行後の罪障感が同様の形で行為時に存在したとも言えないなどの指摘がなされている
(4) 補足説明
上記の判旨のみをみてみても,何が問題とされているかが分からないと思われるが,要するに,本件では,A鑑定とそれに対するB意見,C鑑定,D鑑定の3つの鑑定があったが,A鑑定は心神耗弱状態であり,C及びDは心神喪失とするものであった。ところが,原審は基本的にC鑑定及びD鑑定を基本としつつ,犯行当時の記憶があることなどを「二重見当識」,すなわち,妄想などの誤った見当識を持ちながら,正しい現実的な見当識が併存されていることであるから,記憶があっても心神喪失としていたが,この部分だけ信用することができない-として,いわば鑑定の結果をつまみ食いしたものと考えられよう。そして,このようなつまみ食いをしたのも問題であるが,全体として,重い統合失調症という事実認定を前提としつつ,責任能力はあるという判断につながっており,これが全体として合理的ではない矛盾を抱えたものとなったという評価になったと思われる。
本件の調査官解説は,「統合失調症が行為に及ぼした影響の有無・程度との関係に配慮して犯行前の生活状態,犯行の動機・態様などの事情を評価すべきものであることを示した」としている。分かりにくいが,本判決の事案も考慮して考えれば,統合失調症が重く生物学的には,行為に及ぼした影響も無視できないということを前提としつつも,その他のいわば付随的な事情をいくつも並べることによって責任能力を肯定するのは,全体として,証拠評価が不合理なものとされる可能性があることを示したものと考えられるものと思われる。要するに,犯行前の生活状態や犯行の動機・態様が責任能力肯定方向に傾いても,生物学的要素でマイナス評価が付けられているのであれば,それで全体的に責任能力ありというのは困難とする趣旨ではないかと思われる。
なお,精神疾患・障害を有する場合,事件に至る経緯を理解するうえで心理学的解釈の範囲では不十分であり、精神的医学の知見が必要となる。このことは、事件の背景、動機、着想、計画性、犯行時の精神状態(意識状態や精神病状態を含む)などにあてはめられる。さらに、事件後の様子についても、整合性を持った説明が行えるかが重要である。
第3 原因において自由な行為
1 構成要件モデル
構成要件モデルとは,実行行為時に責任能力が必要であるという同時存在の原則を維持しつつ,実行行為の設定を原因行為時にまで遡及させる見解をいう
⇒ この見解は,実行の着手時点を前倒しする見解ということができるわけであり,構成要件該当行為に密着する行為に実行の着手を認め,その時点で責任能力があれば,責任能力の問題は生じないとする見解と思われる
2 責任モデル
責任モデルとは,同時存在の原則の例外を認めるという見解のことであり,結果発生に直接原因を与えた行為が開始された時点をもって実行の着手と理解し,それに対する責任を原因行為時にまで遡及するモデルのことをいう
3 私見
原因において自由な行為の議論は,責任能力の問題とされながら,現実には,実行の着手時点をいつ認めるのかということであると思われる。まず,構成要件モデルというのは,結局,責任能力が認められるか否かは,実行の着手時点で問題にされるところ,実行の着手時点を前倒しすることができるのであれば,被告人が責任能力がある時点において実行の着手を認めれば足りるという見解であると思われる。要するに,構成要件モデルというのは,責任能力の議論とはいい難いということになると思われる。
この点について,現実に問題となるのは,①過失犯と②途中から責任能力を喪失するということであると思われる。すなわち,殺人をしようということで酒を飲んで殺したという教室設例では,被告人を故意犯とすることはできないのであるところ,結局,過失犯を問うことしかできないというのが常識的であろう。そうすると,被告人が酒を飲んだということについて過失,すなわち,客観的注意義務違反が認められるかということを,自身が酒を飲むと悪い癖があるということを認識しているかどうか-などの事情から決められるということになると思われる。後者は,殴っているうちに心神喪失になるということであるが,現実には心神喪失ないし心神耗弱というのは実務上認定が厳しいので,そもそもこのような事実認定になるということがほとんどない。仮にあったとしても,上記の理論からいえば,実行の着手時点において責任能力が認められれば十分であるという見解を前提としているのであるところ,この事例では,実行の着手時点では十分責任能力があるというのであるから,完全責任を問うということは何ら問題がないものというべきものと思われる。
次に,責任モデルという見解は,この問題を実行の着手の問題ではなく,純粋に責任の問題として位置付けようという見解であると思われる。要するに,実行の着手がなされていないにもかかわらず,それよりも前に被告人が責任能力があったことで帰責を正当化しようという試みと位置付けるものと考えられる。考えてみると,この見解は結果無価値と非常に親和性が強い。つまり,結果無価値では,過失行為と故意行為には,客観面では違いがないという統一的なものと考えており,客観的な危険が発生しない限り実行の着手は認めないという見解であると思われる。
そうすると,原因において自由な行為の理論というのは,結果無価値から,より先鋭的に問題となるということができるように思われる。なぜなら,行為無価値については,故意行為については,犯罪計画も考慮しつつ実行の着手を前倒ししてゆくということが考えられるのであるから,行為無価値からは,実行の着手を責任能力が認められる時点まで前倒しすることが理論的に可能であるので,あまり深い問題意識とはならないものと思われる。たしかに,原因行為という言葉自体も,構成要件モデルからはそれがそもそも実行の着手と言うことになるのに対して,実行の着手時点を前倒しすることができない結果無価値からは,「原因行為」という不思議な言葉を使用せざるを得ないということになると思われる。逆にいえば,結果無価値が実行行為性を純粋に客観的に判断しようという点がそもそも無理であるということのようにも思われる。
なお,近時の見解のベースとなっているのは,「行為と責任の同時存在の原則を維持しつつ,行為概念を拡張して,原因行為から実行行為まで一連の過程を1つの意思決定に貫かれた1つの行為とみて,責任能力は必ずしも実行行為のときに存在する必要はなく,原因行為時をも実行行為時をも包括する「行為時」に存在すれば足りる」とする見解である(条解148)。条解では,行為概念が拡張されていると指摘されているが,これは,突き詰めれば,実行行為が続いている間すべてにおいて責任能力がなく,その前の方の段階のみで責任能力があればそれで十分としている方にこそ意義があるわけである。要するに,学説チックな言葉で説明すれば,責任能力は原因行為との間に存在すれば足りるということであろうが,実務上の言葉に変換すれば,責任能力は実行の着手時にあれば足りるということになり,最後まで間断なく連続している必要はないという趣旨と理解できるのであろう。
このように,原因において自由な行為に議論というのは,真の問題の所在を明確にしないまま,漠然とした議論をしているために,どの基本書を見ても,叙述が分かりにくいうえに,論者の実行行為性やあるいは結果無価値,行為無価値などによっても,大きく結論が異なりうる論点であるということを認識しておく必要があると思われる。
第4 違法性の意識と法律の錯誤
1 違法性の意識
(1) 違法性の意識の意義と問題点
行為者が自己の犯罪事実を認識・認容しながらも,何らかの事情によって違法性の意識を有しないまま実行行為を行っている事例もまれではなく,かかる場合,行為者に対する非難可能性を肯定することができるのか
(2) 違法性の意識の要否をめぐる学説の状況
① 違法性の意識必要説(厳格責任説)
違法性の意識は,責任故意の要件と解する
∵ 道義的責任論(19世紀的思考)を徹底させる立場
② 違法性の意識不要説[40]
違法性の意識の有無は,犯罪の成否に無関係であるとする
∵ 法の不知は害する
③ 違法性の意識の可能性必要説(制限故意説)
違法性の意識そのものは犯罪成立の要件ではないが,違法性の意識の可能性は,責任故意の要件とする(⇒ 違法性の意識の可能性すらない場合,すなわち,違法性の意識を欠いたことについて相当の理由がある場合は責任故意が阻却される)
(3) 検討
● 厳格故意説
× 確信犯を処罰できない
↓
● 違法性の意識不要説
× 責任主義の原理に抵触する疑い
↓
○ 違法性の意識の可能性必要説が正当
∵ ① 違法性の意識がなかったとしても,行為者が犯罪事実を認識・認容している場合は,違法性の意識を喚起する可能性があったということができる。
② また,犯罪事実を認識・認容し違法性の意識を喚起しながらあえて犯罪行為を行ったことと,行為者が犯罪事実を認識・認容しつつも違法性の意識を喚起しなかったことは,非難可能性という観点からみると本質的な違いはない
2 法律の錯誤
(1) 法律の錯誤の意義
法律の錯誤とは,行為者が錯誤によって違法性の意識を欠いた場合をいう
① 法の不知
自己の行為が違法であるかを当初から全く意識しなかった場合をいう
② あてはめの錯誤
刑罰法規の解釈を誤った結果自己の行為は許されていると誤信した場合をいう
(2) 法律の錯誤の効果(制限故意説)[41]
① 違法性の意識を欠いても,犯罪の成否には影響しない
② 違法性の意識の可能性すらなかった場合には責任故意が阻却される
(3) 違法性の意識の欠如と「相当の理由」
ア 法律の不知の場合
⇒ 原則として違法性の意識の可能性は肯定される
イ あてはめの錯誤の場合
① 公的機関の意見を信頼した場合
② 私人の意見を信頼した場合
3 事実の錯誤と法律の錯誤の区別
(1) 区別の一般的基準[42]
基本的な違い 違法性の意識を喚起しうる事実認識を有していたか,換言すれば,違法性の意識を可能とする程度の事実の認識を有していたか否か
| 事実の錯誤になる場合 | 法律の錯誤 |
| 一般人ならば,違法性を意識しうる程度の事実の認識すら欠いている場合をいう | 一般人ならば,違法性を意識しうる程度の事実の認識を有する場合をいう |
(2) 法律的事実についての錯誤
事実の錯誤には,純粋の事実に関する錯誤と法律的事実の錯誤があるが,後者であっても,一般人ならば,違法性を意識しうる程度の事実の認識を欠いているから,故意は阻却される
4 違法性阻却事由の錯誤
(1) 違法性阻却事由の錯誤の意義
(2) 違法性阻却事由の錯誤の効果
事実の錯誤説
∴ 違法性阻却事由の錯誤についても,「事実の錯誤」として故意は阻却
∵ 違法性を否定する事実を錯誤により認識することによって,事実の錯誤の根拠である違法性の意識を喚起する余地を欠いている
(3) 誤想過剰防衛・誤想過剰避難
第5章 未遂
第1 未遂Ⅰ(総論)
1 未遂犯処罰の意義と根拠
2 未遂犯の成立要件
(1) 実行の着手
ア 実行の着手の意義と要件
① 構成要件的故意が必要
Ex. 例えば,実弾の入っている拳銃を他人に向けて構えた行為について見ると,それが殺人の故意でなされたのでなければ殺人罪の実行の着手は認められない。つまり,戯れでけん銃を向けただけである場合は,実行の着手は認められない
⇒ 故意の存在は実行の着手時を問題にすべき!!(故意の内容いかんによって,いかなる罪の実行の着手かが決まる)
② 犯罪実現の現実的危険性を含んだ行為の開始があったこと(実質的客観説)
* 行為計画の考慮
⇒ 行為計画の考慮をしなければ結果発生の危険を認定できない
* 行為計画の考慮の具体例
| 強姦の目的で被害者を自動車に引きずり込む行為であっても,行為者が車内で強姦する計画であれば危険の発生を肯定することができるが,市街地のホテルに連れ込んでから,強姦する計画である場合 | スリ行為の場合も,外形的には同じような行為であっても,それはアタリ行為をするにすぎない計画である場合 | 殺人の場合でも,クロロホルム事件にみられるように,着手の存否は,当該行為が一連の殺害計画の中で結果とどの程度の接着性を有するものであるかということが考慮されている |
| ストレートに結果に至る危険を肯定することはできない | 実行の着手は否定されている | 犯罪計画を考慮すれば着手が否定されることもあり得るわけ |
イ 間接正犯における実行の着手時期
① 利用者標準説
② 被利用者標準説
③ 個別化説
* 書研は,被利用者標準説が妥当とする。
● 利用者標準説
× 例えば,直ちに窃盗を命じることで窃盗の実行行為とは疑問
↓
● 個別化説
× 理論的には正しいが,間接正犯の特殊性を考慮するべき
↓
○ 原則:単独犯行と同様に,被利用者が犯罪実現の現実的危険性を有する行為を開始した時点をもって実行の着手時期と解すべき
例外:利用行為時と被利用者の行為時で犯罪実現の危険性に差異なし
∵ 被利用者の行為そのものは,多くの場合,被利用者の意思に基づくので,利用行為を終了したからといって,現実的危険性が生じたとはいえないのが通常
* 毒物を郵送し郵便局員を道具とした場合,古い判例は,郵便局員が被害者に対して毒物を交付した時点で実行の着手を認めている。だが,書研は,当時の郵便事情にかんがみると妥当だが,今日では配達されるのが普通であるから,小包郵便に付した時点で実行の着手が認められる可能性ありとする
(2) 構成要件的結果の不発生
3 未遂犯の処分
第2 未遂Ⅱ(中止未遂)
1 中止未遂の意義と法的性格
責任減少説が妥当(書研)
2 中止未遂の成立要件
(1) 中止の任意性
「自己の意思により」とは,自発的な意思によること,すなわち中止が任意のものであることを意味する。そして,任意性が認められるには,外部的事情を行為者がどのように受け取ったか,その受け取り方を客観的に判断して任意性の有無を判断すべき(折衷説)
| 障害未遂 | 中止未遂 |
| 外部的事情がその行為者に対してある程度必然的に中止を決意させた場合 | 外部的事情に触発されたにせよ,自由な意思によって中止した場合 |
(2) 中止行為
① 結果発生阻止のための真摯な努力をしたこと
| 結果に向けて因果が進行していない | 結果に向けて因果が進行している |
| かわいそうになって姦淫を中止 | ナイフでAの胸を刺した場合 |
| 以後の実行行為中止で足りる | 結果発生阻止のための積極努力必要 |
*積極的な努力とは,「素人ならば素人なりにできるだけ精一杯の努力をした」といえることが必要である。
② 構成要件的結果の不発生(結果が発生した場合は量刑で考慮される)
問題意識 中止行為と結果の不発生に因果関係がない場合
∴ 行為者が結果発生阻止のため真摯な努力をしたのであれば,あえて因果関係を要求するまでもない。
∵ 責任減少説が背景にあると思う
第3 不能犯
1 不能犯の意義と本質
不能犯とは,行為者としては,犯罪を実現する意思で行為をしたが,その行為の性質上,犯罪実現の現実的危険性が極めて希薄であるため,実行の着手が認められず,未遂犯にならない場合をいう
2 不能犯と未遂犯の区別
(1) 不能犯に関する問題点
犯罪の実現が不能であったかはいかなる観点から判断すべきか
(2) 不能犯と未遂犯との区別に関する学説
具体的危険説
行為当時行為者が特に認識していた事情及び一般人であれば認識し得た事情を基礎に,(行為者の立場から)行為の時点に立って,(また,)一般人の立場から事後的かつ客観的に犯罪実現の危険性の有無を判断すべき
∵ 実行行為の実質をなす法益侵害の現実的危険性は,必ずしも物理的・化学的な危険性を意味するのではなく,所与の具体的状況の下において,社会一般人の目から見た危険性を意味すると解する。
仮定的蓋然性説
結果発生の可能性判断は,結果が発生しなかった原因・事情を究明し,いかなる事情の変更があれば結果が発生したかを特定する。そして,その事情の変更の可能性はどの程度の蓋然性があったかを具体的事情によって判断するという判断枠組みをいう。この見解によれば,蓋然性がない場合は,危険性を否定して不能犯とすべきことになる
* 例えば,教室設例の空ベッド事例は,そこに人がいるという事情変更があれば結果が発生したのであるから,そこに人がいた可能性を検討することになる。そうすると,例えば,そこの家は,別荘であり1年に1度しか利用されないという事情があれば蓋然性は否定され不能犯になるのに対して,被害者がたまたまトイレに行くためにベッドを離れていたにすぎないという場合は,可罰的未遂を肯定するべきということになると思われる。この判断は,難しいと思われるが,要するに事情変更について異常性が低いと評価される場合は,蓋然性ありと判断されることが多いと思われる[43]
第6章 共犯
第1 共犯総説
1 共犯の意義と種類
(1) 必要的共犯
必要的共犯とは,構成要件の性質上,初めから2人以上の行為者による実現を予定して規定されている犯罪をいう
| 集団犯 | 対向犯 | |
| 定義 | 同一目標に向けられた多数人の集団的行為を独立の構成要件とする犯罪をいう | 2人以上の行為者の互いに対向した行為の存在することが要件とされる犯罪をいう |
| 具体例 | 内乱(77),騒乱(106) | 収賄・贈賄(197,198) |
(2) 任意的共犯
任意的共犯とは,単独犯を予定して構成要件が定められている犯罪を2人以上の者が実現する場合をいう
2 必要的共犯の処罰と任意的共犯に関する規定の適用(対向犯に任意的共犯に関する刑法総則の規定は適用されるか)
(1) 対向する行為者双方が処罰される場合
∴ 適用の余地なし
(2) 対向関係にある行為者のうち,一方の行為者についてのみ処罰する場合
∴ 任意的共犯の規定の適用は法の趣旨に反する
第2 共同正犯
1 共同正犯の意義とその基本的課題
「犯罪の共同実行」とはどのような行為について認められるか
⇒ 犯罪の共同実行のいかなる点に正犯性を認めるべき基礎あるか
2 共同正犯の「正犯」性―併せて共謀共同正犯の成否について
(1) 共同正犯の「正犯」性
● 一部実行・全部責任の原則
× 強盗の役割をくじ引きで決めて,見張り役になった者が幇助とは奇妙。
また,計画を立てただけの者も教唆と幇助になるのみで社会常識に反する
○ 『共謀への加担』という事実を通じて実行行為担当者を介して犯罪を自ら実行したものと規範的に評価できる
∵ 「犯罪の共同実行」の本質は,相互に利用補充しあって自己の犯罪を実現しようとする犯罪共同遂行の合意を行い,そのような合意に基づいて実行行為が行われるという点にある
⇒ 正犯性を実質的に定義すると,「正犯とは,自己の犯罪意思を実現するために自ら事態の成り行きを操作・支配し,それによって所期の犯罪を実現したもの」となる。そして,共謀者は,他の共同正犯者と相互に利用・依存関係を形成し,実行担当者の行動を方向付け,操作・支配する
*正犯性の根拠
| 形式的客観説 | 主観説 | |
| 共同正犯の「正犯性」 | 実行行為の一部を形式的に分担したという点[44] | 共同正犯者が犯罪遂行に関する共謀に加わったという事実に求めるべき[45] |
* 実務的には,実行行為を自ら分担したか否かは共同正犯の成否に関しては,必ずしも本質的ではなく,犯罪の実体として犯罪共同遂行の合意としての共謀が存在し,かつ,行為者がこれに加わった事実が認められるかが本質的というべき
* 正犯と共犯の区別については,大きくは主観説と客観説に分かれている。
この点,主観説が判例であり,客観説には形式的客観説と実質的客観説に分かれる。前者に与すれば,共謀共同正犯否定説につながる。これに対して,実質的客観説という見解もある。この見解は,構成要件の実現過程における重要な役割であるかどうかによって,正犯と共犯を区別しようとする見解である。この見解によれば,結果に対する重要な役割の有無によって,正犯と共犯の区別が導かれるということになる。
(2) 共謀共同正犯について
| 否定説の論拠 | 反批判 | |
| ① | 60条には,「実行した」と書いてあるので,実行行為の一部分担が必要 | 「犯罪の共同実行」の本質は,共謀に基づく実行にある |
| ② | 単独犯に例えると,犯意を形成したのみで処罰するのに匹敵し危険である | 実行行為までなされないと可罰的とならないから前提を欠いている |
| ③ | 教唆犯として構成すれば十分である | 犯罪の実態に合わない主張である |
*共謀共同正犯否定説は,特に,上記①の点をとらえて罪刑法定主義違反と主張するのである。すなわち,60条の「実行」を形式的に実行行為と理解して,事前謀議への参加に過ぎない場合は,共同実行したとはいえない。にもかかわらず,共同正犯で処罰するのは罪刑法定主義違反と主張する。したがって,ここでの理由付けは,「実行」が形式的な実行行為概念を意味するわけではないと反論してあげる必要がある
3 共同正犯の成立要件
* 主観説
| 客観面 | 共謀に基づいて,共謀者の全部又は一部の者が実行行為を行ったこと |
| 主観面 | 共謀(犯罪共同遂行の合意) |
* 客観説・重要な役割説(前田440)
| 客観面 | ① 共謀に基づいて,共謀者の全部又は一部の者が実行行為を行ったこと
② 共同実効性を認められるだけの重要な役割を果たしていること |
| 主観面 | 故意 |
* 学説の位置づけについて
学説は,今日でも実行行為の一部分担を正犯性の論拠として,それに匹敵する関与があったということで共謀共同正犯を『例外的』に許容するとする。
しかしながら,共謀共同正犯の『正犯性』は,共謀への参加に求められるのであるから,実行共同正犯と共謀共同正犯を区別することは意味がない
* 近時は,実質的客観説によって,「重要な役割」の要件を実質化しようとする立場が学説上の通説となっている
(1) 共謀
ア 共謀の意義・内容
共謀とは,犯罪の共同遂行に関する合意をいう
* 共謀の要素
| 犯意の存在 | 意思の連絡の存在(犯意の合致) |
| 共同犯行の意識とは,各関与者が他の者と協力し,特定の犯罪を「自己の犯罪」として共同遂行しようという認識のことをいう | 意思の連絡が要件とされるのは,共同犯行の意識を各人の内心でバラバラに持っているというだけでは不十分である。そこで,共同犯行の意識について相互に意識の連絡が存することが必要 |
| 正犯意思の共犯における表れといえる | 契約の成立時期に似ているといえる |
| 犯罪の共同遂行に賛成していない場合は,犯意に欠ける | 犯罪計画の重要部分を知らされていない場合は意思の連絡があったとはいえないと解される[46] |
* 共謀の形成過程と共謀との関係
⇒ 共謀は,実行行為の時点で形成されていればよく,時点や形成の経過をいちいち問題としない
① 共謀は,事前の共謀によっても成立する(故意と異なる点)
② 共謀は,黙示的な意思の合致で形成されてもよい[47]
* 黙示の共謀が認められる典型例は,実行共同正犯における現場共謀
* 実行共同正犯ではない典型的な共謀共同正犯の場合は黙示の共謀は認められにくいが,例えば,スワット事件のように,共謀共同正犯とはいえ,共謀者も実行正犯者と行動を共にしているから,実行共同正犯に似た面がある
③ 共謀は,順次共謀(持ち回り決議[48])でよい
④ 順次共謀は,フリーメーソンのような広がりを持っているので,共謀者でありながら,その実行担当者を知らないということが考えられるが特に犯罪の成否には影響しない
* 共謀の内容の具体性
① 犯罪の中核的部分についてさえ,細かい部分が知らされていなくても,意思の連絡は認められる[49]
② 「特定の犯罪」とは,社会的事実として特定された犯罪のことをいう[50]
(2) 共謀に基づいて,共謀者の全部又は一部が実行行為を行ったこと
* 共謀内容の変遷(東京高判昭和60年9月30日刑月17巻9号840頁)
A⇒(Xのいない間にカネ盗もう)⇒B(Xを眠らせてでもカネ盗もう)⇒C(Xを強姦してでもカネ盗もう)⇒D(Xを殺してでもカネ盗もう)
Aに対して強盗殺人罪の共謀共同正犯として結果を帰せしめることができるかが問題となるところ,共謀が成立するためには,①犯意の存在と②意思連絡が必要といえる。この点,本件では謀議の形成過程において,共謀の内容が変遷した結果,犯罪遂行の手段や罪質を中心となる基本的部分に食い違いが認められると考えられる。したがって,Aは,Dが実行した共謀に基づく犯罪について,その中核部分について認識していたとはいえないから,意思の連絡が認められないと解すべきように思われる
| 1 Xと直接接触のあった本件関係者は,B,Cのみであった(実行の中心人物であったAと直接の接触はなかった)。そうすると,Xに共謀があるというためには,①XとB,Cとの間の謀議,及び,②B,CとA以下の者との間の謀議の二段階に分かれた順次共謀という形態をとることになる。
2 順次共謀が成立するには,各段階の謀議内容の間に同一性,連続性が保たれている必要がある。本件は順次共謀の成否が問題となるが,①Xの関与している謀議は,プリンスホテルにおけるXとBとの間の謀議の1回にすぎない。また,②X以外の者による(Aが中心となってなされた)謀議は,Ⅰプリンスホテルから帰ったBと組事務所に居たA以下の者との間の謀議,Ⅱ成増エレベーター内におけるB,A,C,D間の謀議,Ⅲ上板橋集結の前後におけるA,C,D,E,F間の謀議の3回である。 ①の謀議と②Ⅱの謀議との間に関しては,②Ⅰの謀議による拉致の失敗が介在している。また,②Ⅱの謀議と②Ⅲの謀議との間には,いわゆる「総長命令」が介在している。そうすると,①の謀議と②Ⅱの謀議との間に,同一性,連続性は認められない。 |
4 共同正犯の効果
各自が結果全体について責任を問われる
* 実行担当者の行為が「共謀に基づく行為」と評価することができない場合
⇒ 予備罪の成立の可能性(ただし,予備というには,犯罪遂行の決意が外部から認識できるような客観的な明白な行動の存在が必要であり,頭の中で犯罪の企画を考案しているのみで予備罪の成立を認めることのないように注意!)
* 共謀の射程について[51]
5 共同正犯に関する訴訟法上の諸問題
(1) 共謀と訴因
① 実行行為の要件と共謀の要件はいずれも厳格な証明が必要
② 共謀形成の過程は,共謀の間接事実にすぎないから,例えば,共謀の行われた日時・場所は,訴因の特定に不可欠な要素ではない
③ 訴因の中で共謀の日時が明らかにされているのに,それと異なる日時を判決で認定する場合は,不意打ち防止の観点も入れて考える必要がある
(2) 共謀の認定
⇒ 犯意の存否の要素が最も問題となることが多い
* 共謀の犯意の存否のチェック・リスト
| A | 当該関与者は,犯罪事実の実現を希望する理由を持っていたか―特に,犯罪事実実現に関して利害関係を持っていたか |
| B | 領得罪などのように財産的利益の取得を内容とする犯罪では,取得した利益の分配を受けているか,分配を受けた割合はどの程度か,事前の相談の際にそのような利益の分配についての約束があったか |
| C | 謀議の際,関与者の意見が合意成立にどの程度の影響力を持っていたか |
| D | 謀議に際し,関与者が自ら実行担当者になり得る可能性はあったか |
| E | 実行行為そのものは担当しないが,実行行為に必要かつ密接な行為(見張りなど)をしていたか |
| F | 組織犯罪(ヤクザのこと)は,組織の拘束性の強さ,当該関与者の組織における地位はどのようなものか |
*Fは,犯意の成立は容易なので,意思連絡の方を重点的に検討
6 スワット事件について(最決平成15年5月1日刑集57巻5号507頁)
(1) 概説
スワット事件では,①『共謀』が黙示的なものでよいか,②組長を銃刀法違反の正犯とすることができるか-という論点が問題とされる
(2) 共謀が黙示的なものでよいか
ア 問題の所在
共謀が明示なものに限られ黙示的なものでは足りないのではないか-という疑問が生じるのかは,説明が難しい。
まず,重要な役割説(実行行為概念を実質的にとらえることにより,共謀共同正犯の可罰性を肯定するアプローチ)からは,実質的に被告人がその犯行にあたり重要な役割を演じたかが問題となる。したがって,特に意思連絡が明示的か黙示的かという形式が問題となることはない。
実務上は,共謀を共同遂行の合意と定義しているので,共謀とは,犯行の時点までに形成された内心の意思状態にすぎないということになる。そうだとすれば,意思連絡とは,被告人個人が内心の意思状態を形成するプロセスにすぎないということになる。したがって,意思連絡が明示的か黙示的かは本質的な問題とはならないと考えられる。
これに対して,判例上は練馬事件大法廷判決をどのように理解するかという問題点が存在しており,黙示的な共謀が認められるのかという共謀の形式が問題となる余地が存在している。すなわち,「練馬事件判決は,最高裁が共謀共同正犯理論について初めて正面から本格的な判断を示したものであるが,同判決は,その中で,『共謀共同正犯が成立するには,2人以上の者が,特定の犯罪を行うため,共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し,各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし,よって犯罪を実行した事実が認められなければならない』旨判示した・・・この判示部分は,共謀共同正犯の成立を認めるためには一定の内容のある具体的指示ないし打ち合わせ行為などによる明示的な意思連絡が必要であるとしているように読める」(調査官解説)とする。そして,練馬事件の調査官解説は,共謀を単なる意思の連絡あるいは,共同犯行の認識と解してきたこれまでの判例は練馬事件判決によって修正されたと思うと説明している。
たしかに,練馬事件は共謀を主観的にとらえていることは疑いがないように思われるが,共謀,すなわち,犯罪共同遂行の合意と定義している立場と比較しても,より具体的な部分が詰められた犯意の存在が求められているように読むことができる。そうすると,たしかに,少なくとも意思連絡が黙示的では足りないということになると解する余地がある。
イ スワット事件の立場
スワット事件では,練馬事件判決について事案が異なるといっており,本件の事案の下では,黙示の意思連絡で足りるとして処理されている。調査官解説は,練馬事件は,当該被告人が,犯行時犯行場所におらず実行行為者と行動を共にするようなこともなかった事例であるのに対して,本件は,被告人が犯行時に犯行場所付近で,実行行為者と行動を共にしている-という点を強調する。
調査官解説は,黙示の意思連絡がラディカルに問題となるのは,「被告人が犯行現場付近に赴くなどしていない場合」と指摘している。この点,調査官解説は,「全くの意思連絡のみで,犯行のいかなる部分についても明示の意思連絡がなく,共謀共同正犯が問われるような事態は通常は余り考え難い」と指摘する。
ウ 私見
このように考えてくると,私見は以下のように考えるべきであると解する。
すなわち,主観説を前提とすれば,共謀とは犯意の合致があればよいということになるが,そもそも,被告人が黙示の意思連絡しかしていないということになると,主観説のアプローチに置き換えたとしても,そもそも,被告人に犯意が生じているか,一定の犯罪を中核部分とする合意があるのか-ということ自体に疑問が生じるケースが多いように思われる。そのようにみると,あまり,意思連絡の態様が明示的か黙示的かは問題ではないように思われる。
(3) 組長を正犯とすることができるのか
ア 概説
調査官解説の思考過程をみると,まず,共謀があるかどうかを考えて,そのうえで正犯意思があるか否かを検討するというアプローチを採っているように思われる。すなわち,まず,共謀があるといえるかという見地からは,犯意の合致があるかどうかを問題にする。そして,共謀が肯定される場合は正犯意思があるかどうかを問題にするというアプローチをとっていることは明らかである。そうすると,判例は,「確定的に認識・認容していた」という故意論を意識したとみられる説示があるが,これは正犯意思についての説示とみられるものと思われる。
イ 判例の要素
判例が,組長が「概括的とはいえ確定的に認識・認容していた」とする点は,組長は,スワットの誰かが必ずけん銃を所持しているという限度で確定的な認識を有していた-ということである。本決定は,事実関係を総合的に考慮して,最終的には,実質的には,まさに被告人がスワットらに本件けん銃を所持させていたと評しうるとの評価に立っている。
⇒ 組長のけん銃所持の認識が未必的である場合は,「その評価は相当に弱まり,本決定の結論を維持し得たかは,かなり疑問」(調査官解説)とする
* この点について,仮に正犯意思の有無について故意論的な評価も加えているというのであれば,調査官解説がいう結論を維持できないというのは,正犯は無理であり,幇助犯が成立するにとどまるという理解ではないかと思われるが,定かではないように思われる。
* 調査官解説は,「東京に遊行に赴いたのが被告人ではなく,その親族であり,同親族を警護していたスワットがけん銃等を所持していた場合,大阪にいる被告人が,終始何ら明示の指示はせず,単にけん銃等所持を認識し認容していただけで共謀共同正犯に問われるか」という論点について,「かなり問題」と否定的に解している
* 調査官解説は,正犯性を認めうるかの論点について,スワット事件が,「実質的には,正に被告人がスワットらに本件けん銃等を所持させていたと評し得る」という点が,「間接正犯類似的説明に通じる部分があることも注目される」とする
* 深澤裁判官の補足意見が参考になる。「被告人と実行行為者間に,・・・具体的な謀議行為が認められないとしても,犯罪を共同して遂行することについての合意が認められ,一部の者において実行行為が行われたときは,実行行為に直接関与しなかった被告人についても,他人の行為を自己の手段として犯罪を行ったものとして,そこに正犯意思が認められる本件のような場合には,共謀共同正犯が成立する」という。これをみると,共謀については簡単に認めて,後は正犯意思で絞るという思考態度がみられる。これまで見落とされてきたように思われるが,正犯意思の有無の方が共謀共同正犯の判断としては重要であるといい得るように思われる
第3 共同正犯に関する諸問題
1 承継的共同正犯
(1) 承継的共同正犯の意義と問題点
承継的共同正犯とは,ある者が特定の犯罪の実行に着手し,未だ実行行為の全部を終了しないうちに,他の者がその事情を知りながらこれに関与し,その先行者と共謀のうえ,残りの実行行為を自ら,又は,先行者とともに行った場合をいう
特徴 共謀は,実行行為の中途で成立している
問題点 途中から共謀加担している後行者について,犯罪全体について共同正犯として形責を問えるのかが問題となっている。この点,原則として,後行者との共謀成立後に行われた実行行為についてのみ共同正犯が成立するのが論理的といえる。しかし,一般的に後行者は,先行者の行った行為や結果を認識・認容しつつ,あえて共謀加担することが多いので,このような場合まで限定する必要があるのか
(2) 承継的共同正犯の成立範囲をめぐる学説
全面否定説
全面肯定説
限定的肯定説
● 全面肯定説
∵① 犯罪共同説を採る場合,数人が同一の犯罪を行うのが共同正犯であるから,基本的には,後行行為者に加功前の先行行為者の惹起させた犯罪部分についても帰責されるということが論理的に要請される
② 既存状態の認識と利用の意思
× ① 単に犯罪が不可分というだけでは,個人責任の原則と矛盾する
② 実体法上一罪であるからといって常に分割不可能とはいえず,包括一罪や継続犯のケースでは分割ができる
● 全面否定説
× 後行者の刑責をいかなる場合も共謀加担後に限定することは妥当でない
○ 限定的肯定説
∵ 後行者が先行者の行為及びこれによって生じた結果を自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用する意思のもと,先行者の犯罪に途中から共謀加担し,その行為などを現にそのような手段として利用した場合には,先行者の行為などを実質上後行者の行為と同視してもよいと考えられる。
(3) 承継的共同正犯に関する判例
判例の主流は,全面肯定説を採っているが,限定的肯定説を採るものが増えつつあると解されている。
2 過失犯の共同正犯
視点 過失犯は,『開かれた構成要件』であって,構成要件要素の規定の仕方が緩やかであるから,各関与者について異なった注意義務を認めて単独犯の成立を認めることで処理可能
⇒ 過失犯の共同正犯を認める実益はあまりない!!
(1) 過失の共同正犯が問題となる典型例
甲・乙が対等の立場で共同して作業して事故が発生したという場合は,両名のうち,いずれの過失から結果が生じたのか因果関係が明らかではないケースが多い
(2) 過失犯の共同正犯の成否に関する学説
視点 過失犯の要件事実をどのように把握するのかということと関連が深い
従来の見解 従来は,不注意と結果との間に因果関係があれば直ちに過失犯が成立すると要件事実を構成していた(旧過失論)。そうすると,個々人の不注意という無意識的部分との因果関係があるかという点しか判断の対象とはならないから,過失の共同正犯という観念を容れる余地がなかった。
現在の見解 過失犯にも過失行為という実行行為があると明確に認識されるようになった。そうすると,過失行為についても共同実行の観念を容れやすくなっている
(3) 過失犯の共同正犯に関する判例
実務では,過失犯の共同正犯は,共同の注意義務違反に共同して違反して法益侵害の現実的危険性を有する行為をしたと認められる場合のみ肯定する
⇒ 結果発生の危険が予想される状態の下で,事故発生の具体的対策を行うについての相互利用・補充関係に立って,結果回避のための共通の注意義務を負う者に,共同作業場の落ち度が認められる場合に,初めて過失犯の共同正犯を肯定することができる
3 共犯関係からの離脱(共犯関係の解消)と共同正犯の中止
(1) 共犯関係からの離脱(共犯関係の解消)
| 実行の着手前 | 実行の着手後 | |
| 要件 | 他の共謀者に対して共謀関係から離脱する旨の意思を表明し,残余の共謀者がこれを了承すること | 自己を含め共犯者の誰もが当初の共謀に基づく実行行為を継続することのない状態を作り出すこと |
| 効果 | 共謀関係は解消されて,その後の残余共謀者による犯行は,別個の共謀によるものと評価される | 他の共謀者が実行行為を継続したとしても,その時点意向の実行行為及び結果の帰責は許されない |
| 注意点 | 心理的因果性を除去しているかが本質であるから,離脱の意思とその了承は黙示的なものでよい | 特にすでに実行に着手していることで生じている因果性を除去しているかを中心に検討すること |
4 結果的加重犯の共同正犯
成立する
5 予備罪の共同正犯
成立する
第4 加担犯
1 加担犯の処罰
2 加担犯の従属性
3 教唆犯
(1) 教唆犯の意義
教唆犯とは,他人を教唆して犯罪を実行するに至らしめた者をいう(61条)
*共謀共同正犯との違い
| 似ている点 | 似ていない点 |
| 相互教唆の形で次第に共謀が形成されていく点について | 教唆犯は,「他人の犯罪」に加担するものにすぎない。犯意を欠いているし,犯行の決意から実行までを被教唆者の意思に委ねている点が異なる |
(2) 教唆犯の成立要件
① 教唆行為
教唆とは,犯罪実行の意思のない者に対して,特定の犯罪の実行を決意させるような刺激を言語・動作によって与えることをいう
② 教唆の故意
教唆の故意とは,被教唆者が違法な実行行為を行うことの認識・認容をいう[52]
③ 教唆に基づく正犯の実行行為
④ 教唆行為と正犯者の実行行為との間の因果関係
(3) 教唆犯の処分
61条1項
(4) 間接教唆
61条2項
4 幇助犯(従犯)
(1) 幇助犯の意義
幇助犯と共謀共同正犯との区別は,「他人の犯罪」に加功したという実態があるかで異なるが,具体的には,共謀(犯意の有無の要件)の存否を判断すべき
(2) 幇助犯の成立要件
① 幇助行為があること
幇助とは,正犯者でない者が正犯の実行を援助し,容易にすることをいう
*片面的幇助犯の成立の有無
共謀共同正犯と異なり,犯意の合致が要件とされていないから,理論的に片面的幇助犯を妨げる理由はない
② 被幇助者の実行行為をしていること
③ 幇助行為が正犯の実行を容易にしたという因果関係
*幇助の因果関係
幇助の因果関係とは,物理的に正犯の犯行を容易にしたというだけでなく,心理的に犯行を容易にしたという関係があればよい(幇助の因果関係は,犯意を強化し,犯行を容易にすれば足りる)[53]
(3) 幇助犯の処分
63条
(4) 間接幇助など
62条2項
(5) 不作為による幇助(片面的幇助犯の一種)[54]
Ex.Xが甲社の倉庫に侵入窃盗を行おうとするところ,管理人Yが気付きながらも,Xの行為を放置した場合
| 共謀がある場合 | 共謀(意思の連絡)がない場合 |
| XとYとの間に共謀,特に意思の連絡があれば,Yは,共謀共同正犯となり特に不作為犯がどうのこうのという議論にはならない | ①Yは,片面的幇助犯として問題 |
第5 共犯の身分
1 身分犯の意義と分類
2 共犯と身分の意義と問題点
3 刑法65条と真正身分犯・不真正身分犯
4 真正身分犯と共犯(65条1項)
5 不真正身分犯と共犯(65条2項)
第6 共犯の錯誤
1 共犯の錯誤の意義と問題点
設例① Xは,Yに対して,「A宅に侵入してカネをとってきたらいいよ」と窃盗を唆した。ところが,YはA宅に侵入後Aに発見され,格闘となりAに加療3週間の傷害を加えた
⇒ 抽象的事実の錯誤
設例② Yは,A宅と間違えてB宅に侵入してしまった場合
⇒ 具体的事実の錯誤(方法の錯誤)
設例③ Yは,戸締りが厳重であったためにA宅は諦めたが,偶然通りかかったB宅が戸締り不十分であったので,その場でB宅に押し入る意思を生じた
⇒ 教唆と実行との因果関係が問われる[57]
2 共同正犯の錯誤
(1) 具体的事実の錯誤
全員が共同正犯(書研)
(2) 抽象的事実の錯誤
法定的符合説によると,原則として,発生した重い犯罪についての共同正犯の成立は否定されるが,共謀にかかる犯罪の構成要件と発生した犯罪の構成要件とが実質的に重なり合う限度で共同正犯の成立が認められる
3 加担犯の錯誤
共同正犯の錯誤の場合と同様の処理をすればよい
4 共犯形式の相互間の錯誤
教唆と幇助の錯誤などについては,38条2項から軽い幇助が成立
第7章 罪数
第1 犯罪の成立と個数
第2 犯罪の競合
第3編 刑罰
第1章 刑罰の意義と種類
1 刑の種類
(1) 主刑
① 死刑
② 懲役
③ 禁錮
④ 罰金
⑤ 拘留
⑥ 科料
(2) 付加刑
⑦ 没収
* 第三者所有物との関係
例えば,Aが携帯電話を騙し取るために契約申込書を作成した場合について,V社所有にかかる偽造文書については,「その偽造部分」を没収するということが多い。これは,V社の所有権を侵すのではないかとの疑問も生じるところであるが,「偽造印・偽造証書は,法律において製作・所持を禁止し,何人の所有も許さないから没収できる」とする大審院の判例がある。このように,偽造文書については所持することが法律上禁止されているので,偽造文書についての所有権については保護する必要はないと考えられる。したがって,偽造部分については第三者が所有していても没収することができる。具体的には,「偽造である」というスタンプを押すことによって行われている
第2章 刑罰の適用
第1 刑罰の適用過程
第2 構成要件及び法定刑を示す規定の適用
第3 処断刑の形成
1 処断刑形成の順序
2 科刑上一罪の処理
3 刑種の選択
4 累犯加重
5 法律上の軽減
(1) 必要的減軽
ア 定義
必要的減軽とは,刑法の各条項の中で,刑を必ず減軽しなければならないと規定されている場合をいう
イ 具体例
① 心神耗弱(39条2項)
② 中止未遂(43条ただし書き)
③ 幇助犯(63条)
(2) 任意的減軽
ア 定義
任意的減軽とは,刑を減軽することができると規定されている場合に行う刑の減軽をいう
イ 具体例
① 障害未遂(43条本文)
② 過剰防衛(36条2項)
③ 過剰避難(37条1項ただし書き)
④ 法律の錯誤(38条3項)
⑤ 自首・首服(42条)
[補論 自首についての一考察]
1 定義
自首とは,犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し,その訴追を含む処分を求めることをいう
2 減軽の論拠
犯罪の捜査及び犯人の処罰を容易にさせるとともに,無実の者の処罰の危険を避け,あるいは予備罪について犯行の着手を未然に防止すること
3 自首の要件
(1) 実体的要件
ア 捜査機関に発覚する前の申告であること
自首制度の論拠は犯罪の捜査を容易にさせる点にあるから,捜査機関が犯罪事実をすでに認識しているのであれば,被疑者の申告が犯罪の捜査を容易にさせたとはいえない。したがって,捜査機関に発覚する前であることという時間的制約が課せられており,自首制度の中で最も重要な要件というべきである。
イ 自発的な申告であること
自首が成立するには,「自発的」な申告が必要であるとされている。たしかに,自首制度の論拠からすれば,警察による捜査がすでに開始されており,被疑者が警察の取調べに対して,犯罪事実を申告したとしても,犯罪の捜査はすでに行われているから,犯罪の捜査を容易にした,言い換えれば,犯罪捜査に寄与したと評価することはできない。すなわち,「自発的な申告」でなければ,被疑者の申告が犯罪の捜査を容易にさせるほど,捜査に寄与することはないことから,このようなことが要件の1つにされているものと考えられる。
ウ 自己の犯罪事実について申告すること
自首制度の論拠との関係では,警察の捜査を容易にさせるといえるだけの情報を提供しない限り,犯罪の捜査を容易にさせたとはいえないとの理解が成り立つ。そうだとすれば,被疑者が犯罪事実を申告したというためには,ある程度は具体的な申告が必要であると考えられるのであって,例えば,匿名の申告は,犯人の処罰を容易にさせるものとはいえないので自首制度の論拠との関係では,自首を認めるべきではない。もっとも,形式的には氏名を述べていない場合であっても,主体に関して誤らせる可能性がなければ,主体に関する申告があったものといえ,犯人の処罰を容易にさせるものと考えられる。
(2) 手続的要件
エ 捜査機関に対して書面又は口頭で申告するなど刑訴法所定の手続によること(245条が241条・242条を準用)
6 併合罪加重(併合罪の処理)
7 酌量減軽
第4 宣告刑の決定
第3章 刑罰の執行
第4章 刑罰権の消滅
[1] この分類は分かりにくいところであるので,補足して意見を述べておきたい。これは,非常に形式的な点に着目した分類であると理解するとよいと思う。つまり,結果が構成要件要素とされているか否かというのみによる分類と理解するとよい。そうすると,結果犯はこれが要素とされているのに対して,挙動犯ではこれが要素とされていないということになる。しかし,これは社会学的にみて結果発生がないというわけではない。挙動犯の典型例は住居侵入罪(130条前段)とされているが,社会学的には,自分の住居に侵入されて入られたことによってプライバシー侵害や住居権の侵害という結果が発生したということはできると思われる。しかしながら,立法技術上,住居侵入罪の場合,いかなる社会学的結果を「構成要件的結果」として実体化するかは実は難しいのである。というのも,いったい何をもって外部から認識可能な結果が発生したかは分からないと思われる。もし結果を構成要件要素とすると,例えば,「プライバシーを侵害したこと」とすると,プライバシーが侵害されなければ住居侵入罪は成立しないということになるが,これが立法政策として妥当かという見地から考えると,処罰の範囲が狭くなりすぎるおそれがある。こういう観点から,立法技術の限界から,結果が「構成要件要素」から落とされていると理解すればよい。
[2] この分類についても補足して説明をしておきたい。この分類は,法益侵害の発生について,どの程度の蓋然性を要求するかという問題といえる。つまり,重大な法益侵害の発生が保護法益とされている場合,できればその発生を予防したいという考慮が働くものと思われる。そうすると,結果が重大である限り,結果が発生する危険性がある程度低くても処罰するという立法政策を採ることには合理性がある。例えば,放火の場合は抽象的危険犯とされており,その保護法益は,社会的法益であるとされるところ,一軒の家に放火したところで社会的法益が犯されるとは限らないであろう。そうすると,立法政策としては,一軒燃やして二軒目に燃え移った時点で現住建造物放火が既遂となるということも考えられる。しかし,木造建築物が多い日本では,一軒もやせばそれ以上に燃え移るという危険性がある程度の蓋然性をもって予測されるわけである。こういう見地から,「個別具体的ケース」に応じて社会的法益に対する危険が生じたかを問題にすることなく,「一般論」として危険という見地からこれを禁圧するというものが抽象的危険犯といえる。抽象的危険犯と具体的危険犯の違いは,個別具体的なケースの事情の考慮を許すか否かという点にある。抽象的危険犯は,一般論で危険といえればそれで犯罪を成立させるが,具体的危険犯は,一般論で危険といえるだけでは足りず,本件事案の下で具体的に危険があるといえるかを判断しなければならないということになる。この理由を考えてみると,いずれにせよ相当高度の蓋然性がない限り処罰を許さないというのは,両者とも同じといえるが,やはり結果の発生が重大であるか否かという見地からの違いといえるのではないだろうか。つまり,抽象的危険犯は,結果が重大であるために,相当高度の蓋然性といってもその具体的適用での切迫性はやや薄くても適用してしまうのに対して,具体的危険犯は結果が重大とまではいえないため,危険性の判断について繊細なバランシングを求めるということではないかと思われる。
[3] この分類についても若干の補足説明を行うこととする。これは,立法者の意思を探るのに有益な視点ということができる。まず,即成犯とそれ以外を区別することにより,状態犯と継続犯には,構成要件的結果行為発生後の法益侵害の状態が行為者の意思に基づく行為が介しているということが読み取れるであろう。そうすると,その結果発生後の意思に基づく行為について,果たして処罰する必要があるのか否かという立法政策上の判断を立法者は迫られることになるのである。そして,処罰すべきであるという判断を示したのが継続犯であり,処罰すべきではないという判断が示されたのが状態犯という区別と理解しておけばよい。結局,両者の違いは,立法者の意思はどうであるかとうことを刑法の目的に照らして探究していくことになるが,一応は,結果が発生させた行為によって,その後の侵害状態も評価し尽されているか否かという観点が参考になると思われる。
[4]不作為犯については,結果へと向かう原因力はないので,原則として作為義務は生じないが,Xが結果へと向かう因果の流れを現実的,具体的に支配していると,それは実質的に作為犯と同様の法益侵害に向けて因果関係を設定したことと同じことである。したがって,作為義務の実質的根拠は因果の経過の支配している点にある。因果の経過の支配は,①自己の意思に基づいて排他的支配を設定した場合,及び②意思には基づかないが,因果の流れを事実上支配するに至った場合がある。
[5] 『因果関係の断絶』も分かりにくいので若干の補足説明を行うこととする。本文で述べているように,刑法上の因果関係とは,発生した構成要件的結果を行為者の実行行為に帰属することができるかという問題である。すなわち,実行行為に帰責するためには,その結果が実行行為の物理的な因果法則に従って発生している必要があるということができる。条件関係があるというのは,この物理的な因果法則の影響を受けて結果が発生したというにすぎない。ところが,本文の例では,甲はAに毒を飲ませたものの,その物理的な因果法則が機能しはじめる前に,乙がAを刺してしまっている。そうすると,乙の死という殺人罪の構成要件的結果の発生は,乙の「刺す」という行為の物理的因果法則によって発生したとみることができる。したがって,甲の毒を飲ませるという実行行為とAの死という結果との間には,物理的な因果法則のつながりがないということになるから,条件関係を欠くということになるのである。ならば,「条件関係がない一事例」と説明すればいいのであるが,因果関係の断絶とは,一見するのにAの死の結果に甲の行為が作用しているように見えるが,実はそうでもないということに特殊な意味を見出しているのかもしれない。いずれにせよ,実務上は,「条件関係が否定される一事例」と理解しておけば足りるように思われる。
[6] 条件関係は,「あれなくばこれなし」という定式をあてはめるだけだと勘違いしている者が多いと思われる。これを概念法学的に『所与の公式』と考えれば,上記のように適用に迷うのも肯けるところである。しかしながら,刑法上の因果関係は,あくまでも,構成要件的結果を実行行為に帰責することができるかという問題である。その因果法則を定式化したのが,「あれなくばこれなし」というにすぎない。そうすると,その適用にあたっても条件関係の公式が物理的因果性を判断するツールであるということを忘れてはならない。Aがなぜ死亡したかを考えてみると,Aの死亡に物理的因果法則を与えたのは,甲が自動車でひいたことにあることは疑いがない。では,その後に乙が自動車でAをひいたからといって,いったん甲が与えてしまった物理的因果は突然なくなるのであろうかということを考えてみると,そのように考えるのは誤りであることが明らかである。したがって,条件関係を認めることには,何の問題もない事例を因果関係の本質を理解しない学者が議論しているだけなのである。なお,二重礫過の事案で致死との因果関係が争われる事案は実務上稀ではない。ここでは,XがAを跳ねたが,YもAを跳ねたという事案を想定しよう。この場合,「Xの行為でAが重大な損傷を負い,Yの行為でAは死亡した」と認定されるとする。この点,Yが帰責されるのは当たり前であるが,Xについては,後続車の通行が予測しうる路上に被害者を転倒させるという危険な状況を作出したと認められるのであれば,因果関係が認められると考えられる。しかしながら,因果関係が否定される限界ケースもある。すなわち,第2事故運転者が極めて無謀な運転をしていたので,第1事故によって無防備状態に置かれている被害者を轢く可能性が,通常の歩行者を轢く可能性とほとんど同程度という場合であれば,「第2事故発生の危険」は第1事故の過失行為の危険に内包されるものとはいえないから,第2事故により被害者が死亡したとすれば因果関係は切断されると考えられる。二重礫過は,条件関係の認定が難しいのではなく,むしろ,相当因果関係の認定が難しいといえるので,教科書と受けるイメージが異なるので注意しておく必要があろう。
[7] 不作為の因果関係について,判例は,「期待された作為をしたのであれば,結果の発生を防止することができたと合理的疑いを超えるほどにいえること」を条件関係の適用として問題にしていると思われる。「期待された作為をしていたのであれば」というのは,本来の条件関係の適用のご法度である「仮定の条件の付け加え」ではないかとの疑問が生じるところである。この点,説明は難しいが,そもそも,不真正不作為犯の場合,具体的な作為義務を想定してその作為義務違反があるから,犯罪が成立するという議論となっている。そうすると,具体的な作為を想定してみたところで,その結果を防止することができなかったということになると,実は,翻って想定すべき作為義務が存在しないことになる。したがって,構成要件該当性がこの場合はそもそも否定されてしまうのである。そうすると,不真正不作為犯として問題とされるのは,「(条件関係があることを前提に)結果を防止することができる作為」について,作為義務があったかという点のみである。すなわち,逆に言えば,そもそも因果関係がない場合は,構成要件該当性自体が否定されかねないのであって,実際上,不作為犯の条件関係を問題にする余地はないということができるであろう。
物理的因果性という観点から説明すると,たしかに,不作為であるのに結果に対して物理的な影響を与えたということはできないところ,ここで判断されるのは,すでに設定された何らかの物理的な因果法則が,例えば,Aの死亡に向けて流れている段階で,甲が,「何もしない」ことによって結果を発生させたというようになるようにも思える。しかしながら,これではすでに何らかの物理的な影響がなぜ設定されたということになろう(そして,この点は検察官が「実行行為」として問題とはしていない)。もちろん,この点について先行行為があれば,そもそも生じた物理的な因果則自体,行為者が設定したというものである可能性がある(先行行為による作為義務の発生)。しかしながら,それは実行行為ではないから,その原因設定行為について条件関係を問題にすることはできないのである。割り切ると,結果発生の因果の流れは,「他人」が設定しているのである。そうすると,行為者の実行行為は,何もしなかったという不作為であるところ,これは通常の意味(刑法上の因果関係)で条件関係を問題にすることができないということになろう。そうすると,条件関係の判断も特殊なものとならざるを得ないと解されるのであって,「法の期待する一定の身体運動=作為を行っていたならば,結果が発生しなかったといえるか」を問題とするものと解される。しかしながら,ここでは,客観的帰属に類似する判例理論による評価や相当因果関係説の評価が先取りされている側面があり,条件関係の判断とは,本来は純粋に自然科学的な物理則を問題とすべきものであるのに,不作為の場合は,その条件関係の判断に法的な評価が含まれるという欺瞞があるように思われる。
[8] 『因果関係の中断論』は,近時の判例理論を理解するにあたりその基礎となる理論であるから,注意する必要がある。『因果関係の中断論』と類似する議論として,『因果関係の断絶』という議論があったが,これは条件関係がそもそもないケースということは先述のとおりである。これに対して,『因果関係の中断論』というのは,条件関係の存在は肯定されてしまう場合に,これを法的な観点からしぼれるのかという問題といえる。この点について,『因果関係の中断論』は,『第三者の故意に基づく行為』が介在した場合は,法的評価の問題として因果関係が否定されると考えている。これは,その後,『遡及禁止理論』として発達していくことになる理論の原型ということができる。そもそも,刑法上の因果法則は,もともとは自然科学の物理的因果則があるかが問題とされた。したがって,『因果関係の断絶』では,その物理的因果則がまったくないというケースであった。これに対して,本件では,Aは甲がナイフで刺さなければ,入院することもなかったから,物理的因果性は認めることができよう。もっとも,ならば単純に乙を処罰すればよいのではないかという疑問がもたれるところであろう。このように,通常では,結果に最も近い人間が帰責を受けるということにすれば足りるというのであって,それを超えて,前者に遡及することはできないのが原則というべきなのである。これは,物理的な因果則の問題のみとしては説明をすることができないのであり,そこで法的な評価を加えた『因果関係の中断論』を取り込んだのが『条件説』ということもできるように思われる。近時の判例理論の動きは,明らかに因果関係の中断論を意識するものといえるから,この点についても注意する必要があろう。
[9] 被害者に特異体質がある場合,相当因果関係説では,しばしば因果関係が否定されると主張され,その後に判例批判が続くのが定石である。しかし,以下のような基本的視座に立って判断するべきと思われる。まず,甲がAを殴ったところ,Aの脳梅毒が憎悪して死亡したという場合を考えてみれば,原則として,因果関係を認めることに問題はないであろう。というのも,判例が「条件説+因果関係の中断論」と仮定すると,本件では第三者の故意行為が介在したという事実はないのであるから,因果関係の判断は,条件関係の有無,すなわち,結果に対して物理的因果性を与えているかという観点から判断されるべきである。したがって,甲がAを殴らなければAが死亡することはなかったと考えるのが普通であろう。これと区別する必要があったのが,原因が別にあるという場合である。つまり,例えば,甲がAの足を蹴った場合に,Aの脳梅毒が突然憎悪したというのであれば,そもそも因果関係の断絶が起きているといえる。あくまで判例が肯定するケースは,実行行為と特異体質があいまって結果が発生したものに限られるのである。上記のケースの場合,客観的帰責には何も問題がなく,甲はAを傷害する故意があったことが明らかであるから,相当因果関係ある重い結果との間で主観的帰責をされることには何も問題がなく傷害致死の成立を肯定し,後は量刑の問題と思われる。折衷的相当因果関係説の欺瞞はこの点を考えるとよくわかる。つまり,折衷的因果関係説では,「一般人はAが梅毒に犯されていたということを予見することができるか」が争点となるが,これでは,傷害致死の主観的帰責の問題において,重い結果の認識は不要とした意味がなくなると思われる。結局,折衷的因果関係説は,上記の主観的帰責についての論点の「敗者復活戦」として主張された側面が否定しがたい。
[10] 仙台地判平成20年6月3日は,「本件暴行は,密室内で自分より体が小さく力の弱い女性である被害者に対し,背後から蹴り付けたり,頭部を掴んで金属製ドアに複数回打ち付け,続けざまに手拳で両頬や腹部を殴打するなどという執拗で相当に強度の危険なものであり,そのため,被害者は,強い恐怖を感じ,大声を出して裸足のまま約158メートルもの距離を必死に走り,通行人に助けを求めている。相当強度の暴行を立て続けに加えられた被害者が,恐怖心から必死に逃走するのは当然のことであり,その逃走行為が被害者が有していた冠状動脈異常に作用して死因となった急性循環不全を引き起こしたものである。世の中には,心臓等の持病を抱えて脆弱な体質ながら通常の社会生活を送っている者が少なからず存在しており,本件のような暴行及びその後の逃走行為がその持病等に作用して死亡の結果が生じることもあり得ることであり,被告人が被害者の冠状動脈異常を認識していたか否かに拘わらず,本件暴行により恐怖を覚えた被害者が逃走し,それが被害者の冠状動脈異常に作用して急性循環不全を誘発したのであるから,本件暴行と被害者の死亡との間には因果関係があるといえる」とする。
[11] このような判例を支える根拠として,行為者にも被害者にも支配できない特殊な事情による結果を被害者に帰属させることが公平に反する以上,行為者の行為に帰属させるべきとする佐伯説の根拠付けの試みが見られる。
[12] この問題の基本的視座も,「条件説+中断論」から考えると有益である。まず,本件は,一見するのに中断論の適用場面にも思えるが,中断論が適用されるのは,「第三者の故意行為が介在した場合」とされている。ここにいう第三者には被害者は含まれないと解される。けだし,中断論は,「他に刑罰を帰責するものがいる」ことが前提となる理論であるところ,被害者の行為が介在してもそれは自傷行為にすぎず被害者に帰責する余地はないといわねばならないからである。そうすると,中断論は適用できない。そうすると,後は条件関係があれば肯定すべきと考えれば足りるように思われる。なお,エホバの証人のケースでも中断論の適用を否定すると考えれば,条件関係は十分認められるのであるから,客観的に帰責することは可能のようにも思われる。
[13] 逆にいえば,被告人らの暴行,追跡行為とその心理的・物理的影響の下で当該逃走方法が選択されたと評価できれば,被害者独自の判断による不適切な選択だけから結果が生じたとはいえないことになる。
[14] そもそも,未熟さを自覚している被害者は,指導の下でなければ潜水を行うことはなかったと考えられるので,被害者が端特でも死亡結果を発生させ得る介在事情とはいえないということに注意が必要である。また,被告人が受講者の動向に注意を払うべき義務に反して受講者を見失ったという過失行為が被害者の未熟さの持つ危険を増加・誘発させたと評価することができる。そうだとすれば,被害者の過失行為は,被告人の過失行為の中に織り込まれている危険性の範囲内でそれが現実化したにすぎないということができる。
[15] このケースを論じるにあたっては,事案に即して具体的に思考を段階的に重ねてゆく他はない。まず,この手の事案は「因果関係の断絶」が生じている場合が多い。すなわち,行為による死亡結果発生の危険が治療によって著しく減少し,被害者の行為による異常行動による寄与度の方が高いと認められる場合,行為に内包した危険の現実化と評価できない場合がある。言い換えれば,別の原因で死亡しているので,条件関係がすでにないということであろう。そうすると,「医師の治療によってとりあえず健康状態が維持・回復され,死亡するおそれがなくなったという事実」を認定できるかが問題となろう。この事実が認定できれば条件関係がないといって切り捨てることが可能である。次に,因果関係の断絶はないという帰結となった場合の処理である。この点,「被害者の自由な意思」が介在したと安易にいえないケースがある。すなわち,診療拒否は,興奮や治療のつらさに基づくものが多く,自由な意思に基づくということはほぼあり得ないといってよい。当初の被告人の行為が因果的な影響を与え,診療拒否に至らせることを余儀なくさせるという場合,被告人の行為の危険性には,「被害者が診療拒否をするかも」という危険がすでに内包されているものと考えられる。特に治療が難しい部位であればなおさらであろう。このようなケースは16年判例と同様に当然因果関係があると処理していくことである。次に,自由な意思による診療拒否の場合,特に信仰上の場合が考えられる。この点については,因果関係を否定する見解が学説では多数であるが,相当とはいいがたい。すなわち,平成16年のケースと平成4年のケースでは,被告人の持つ結果発生の蓋然性が異なっている。一応,本設例では,結果発生の蓋然性があるケースを念頭に置いている。そうだとすれば,死亡の結果をもたらすような重大な損傷を加えて,物理的な死因がこれに基づくというのであれば,当初の行為に内包する危険(輸血しなければ死に至る)が現実化したのにすぎないと考えられる。そうすると,介在事情を導いた被害者の意思決定の態様いかんは直ちに因果関係を左右するものではないと考えられる(前田172)。この点について,学説は,被害者の自己答責又は危険引受の法理を根拠とするが,そもそも,犯罪行為が被害者に帰責されるということはあってはならないというのが因果関係の中断論の原理原則であることを失念していると言わざるを得ない。このように考えてくると,学説が論じる議論の射程距離というのは,実は,「被告人の行為が結果発生の蓋然性が低く,被害者の行為とシンクロして結果が発生した」という平成4年ケースに近い事案のみと考えられる。つまり,まずは,被告人の行為の危険性についてどの程度の結果発生の蓋然性が客観的に認められるかということを判断した上で石の筋を検討するということになると思われる。そして,平成4年ケースに近い事案であれば,学説のように因果関係が切断される場合もあろうが,逆に言えば,それ以外で因果関係を切断するのは失着と言わざるを得ないであろう。
[16] この点については,中断論の適用があるかが問題となる。つまり,「第三者の故意行為」の中に,行為者本人も含まれるのかという問題と思われる。しかしながら,この問題は,書研94が位置付けるように,「行為者の事後行為が介在する場合に因果関係は遮断されるか」という問題の立て方よりも,単なる擬律の問題のように思われる。書研が引用するウェーバーの概括的故意の判例は,たしかに,本人の主観では,①殺人⇒②死体遺棄の故意であったが,現実には,①殺人の実行に着手⇒②殺人の結果発生というものにすぎなかった。そうすると,本来①②は,一連一体の一個の行為にすぎないのだから,これを細分化して行為者の故意行為が介在するとするのは適切さを欠いている。むしろ,問題にされるべきケースというのは,①誤って過失致死(結果不発生段階)⇒②殺人―というケースを問題にすべきであろう。私見は,中断論の適用を認めて,この場合,殺人のみ問題にすれば足りると思う。したがって,殺人と過失致傷で足りるのではなかろうか。
[17] この問題を検討するにあたっては,まず,因果関係の検討に先立ち,実行行為の的確な認定が不可欠である。すなわち,検察官はXを殺人罪で起訴するわけであるが,いかなる行為を実行行為ととらえるかが問題となる。すなわち,抽象的に考えれば,第1行為のあとに第2行為が介在しているので,結果を第1行為に帰責することはできず殺人未遂となり,第2行為は殺人罪あるいは過失致死罪と擬律すると考えられるが,これはまず実行行為を明確に定めてから検討すべきことである。東京高判は,第1行為は殺害行為は終了しておらず,同一の犯意が継続しているのであるから,第1行為と第2行為は一連一体の実行行為ととらえている。そうすると,重要なのは,第1行為の時点で殺人罪の実行に着手しているということであり,発生した結果との間に因果関係があるかという点にしぼられてくる。そのうえで考えると,被告人は妻をナイフで刺し,逃げられないようにしつつ,ガス中毒死させる意図があったのであるところ,死の危険が迫った被害者が捨て身で危険度の高い逃走手段を試みるということは,当該行為の危険性に内包されていると評価することができる。したがって,結果は帰責されると考えられる。後は,因果関係の錯誤が問題になるだけと考えられる。この点,木谷78は,「実行行為をどう把握するのか不明確」と批判している。たしかに,実行行為が一連一体といってみたところで,結局は,実行の着手時点を問題にして,その行為の危険性を定めていくというアプローチを採ると,あまり一連一体という意味はないようにも思われる。おそらく,第1行為の時点では故意がないので,そこを誤魔化すために,一連一体といったのではないかとも思われる。もっとも,その後に出されたクロロホルム吸引事件でこの点は解決されているといえよう。そうだとすれば,定石としては,まず,第1行為に実行の着手があることを認定し,かつ,第1行為の終了だけでは実行行為は終了していないということを指摘すればよいであろう。次に,第1行為と結果との間に因果関係があることを問題にすればよいが,因果関係を認めるのはさほど難しくないであろう。そのうえで,因果関係の錯誤の問題とすればよいように思われる。
[18] 『因果関係の中断論』を前提とすると,この場合は,因果関係は否定されないということになろう(『故意行為』が介在していない)。
[19] 最決平成18年3月27日刑集60巻3号382頁は,「被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても,道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる」としている。このケースでは,次の2点が重視されている。
まず,Ⅰ路上で停車中の自動車の後部のトランク内に人を閉じ込めるという監禁行為は,トランクは人を防御する構造にはなく,追突事故に遭えば,ひとたまりもなく死傷の結果が生じるという意味において危険性がある。また,Ⅱ深夜,市街地のコンビニ付近で片側1車線の道路上に停車したという,時間的・場所的に現実的に危険なものであった。そうすると,「XがAを監禁してトランクに入れて,深夜のコンビニ前に停車した」行為の危険性には,第三者の過失行為が織り込み済みになっているものと位置付けられる。このような観点から,危険の現実化という枠組みにおいて因果関係を肯定できるものと考えられる。重判解説は,「本決定を,あらゆる交通事故について因果関係を認める趣旨と理解するのは本決定の趣旨に反する。例えば,従来,行為者が被害者を負傷させた後に,被害者を乗せた救急車が交通事故に遭って被害者が死亡した場合には,因果関係が否定されると言われてきたが,そのような結論は本決定の趣旨と対立するものではない」と指摘している。
そのうえで,例えば,「コンビニ付近の停車」ではなく,「赤信号の点灯のために,交差点手前の停止線で自動車を停止させた」という場合は,因果関係を否定する余地があるとする見解もある。すなわち,「コンビニ付近の停車」は時間的・場所的に危険であったというのであるのに対して,「赤信号で停車する行為」については,後続の運転手が十分な注意を払うことが可能であるから,後続車に追突される危険が織り込み済みになっているとはいえない。そうすると,行為と介在事情の間の関連性は高くない(これは,異常性が高いとする趣旨と解される)ので,因果関係を否定されるとしている。ここで注意しなければならないのは,重判解説が指摘するように,無条件に因果関係を肯定することはできないことに留意したい。
[20] ドイツでは,因果関係という概念の中での判断は条件関係によって完結し,因果関係という概念とは別に,構成要件要素として,客観的帰属という概念を論じるという議論の仕方をしている。もっとも,日本では,これが因果関係という概念の中に位置付けられる方が多いのであろう。
[21] 規範の保護目的論とは,さまざまなバリエーションがあるが,基本的視座は次の2点に置かれている。それが,①危険創出と②危険実現の2つである。危険創出連関とは,法規範に違反した危険な行為がなされたことをいう。行為自体の危険性に着目するものと考えられる。危険実現連関とは,発生した結果がその危険の実現であるといえるかという判断をいう。規範の保護目的論は,上記の2つのツールを使って,「侵害された規範の保護範囲の中に発生結果が含まれていれば,結果の客観的帰属を認める」という判断枠組みが採用されている。規範の保護目的論では,「当該義務行為が行われたとしても同様の結果が発生したという場合には,当該義務違反を規定する規範はその目的を達成できないことにより,その行為者の行為を結果に帰属させることはできない」と考えるという。少し分かりにくいわけであるが,結局,規範が保護しているという範囲内に収まっていればよいということになるであろう。そうすると,教科書に挙げられる典型例から案ずると,法規範の保護の目的に適ったような理想的な行為を想定して,そこからの逸脱を検討するという判断枠組みになるようにも思われる。例えば,トランク監禁事件の判例を思い浮かべると,被害者がトランクに入れられるわけではなく,後部座席に乗っていたと言うケースを想定すると,たしかに,それでも被害者が死亡した場合は,運転手であった被告人に帰責することは保護の目的どおりの理想的な行為をしたとしても,結果の防止はできないので,行為に帰責することはできないということなのであろう。
[22] 結局,「被害者には帰責できない」ので被害者に過失があったとしても,行為者の行為に結果を帰責しないわけにはいかないというのが基本的視座であるが,これを修正する試みということができるのであろう。
[23] 『構成要件的故意』の要素として,犯罪事実の認識という知的要素に加えて,行為者が犯罪事実の実現を意欲し希望しているというような『意思的要素』が必要とされるのだろうか。この点,本来責任要素とされる故意が,構成要件段階にせりあげられているわけであるから,その判断は類型化されているといえるから,ことさらに意思的要素が必要とはせず,システマティックに構成要件該当事実の認識さえあれば足りるとすることもできるように思われる。結局,この問題は立法者が責任要素のどの部分を構成要件化して取り込んでいるのかという問題に置き換えられると思われる。書研は,故意は,責任要素であるところ,犯罪事実を単に認識しているだけでは,責任非難が十分に基礎付けられないから,立法者がこの点を構成要件的故意として取り込まないとは考えられないということになると思われる。
[24] 一般に,「認容」という意思的要素については,認容の具体的な心理状態や認定根拠を示さないで,認識的要素と一括して評価してしまうという判断手法が多い。なお,突き詰めてゆくと,「認識はあるが認容はない」として故意を否定するということは考えられるのであろうか。この点,実例は乏しいが,東京高判昭和62年9月22日判タ661号252頁がその一例である。この判決は,甲乙主導の暴行に加わっていた被告人Xがそれによって重篤な脳障害を負っていた被害者に医療措置を施さなければ死亡することを認識しつつ,これを認容し,甲乙と共謀のうえ,被害者を脳障害により死亡させて殺害したと認めた原審を事実誤認として破棄したものである。東京高判は,「被告人は途中で被害者が死亡するかもしれないことを認識したにしても,行き掛かり上,やむなく甲らに同行していたに過ぎず,死亡を認容していたとは認められない」としている。もっとも,気をつけなければならないのは,この判決は,Xは共同正犯として責任を問われたものであるから,事案の本質は「共謀」の認定にあると思われる。そうすると,本来は共謀の成立の射程は,殺人の部分には及んでいなかったという処理をするものの,共謀を「故意の共同」と考える故に故意の認定を先行させ,認容を否定したものと考えられる。また,この事案は不作為の共犯であるから,より強い意思的要素が求められると解した可能性もありそうである。そうすると,通常の単独犯で「認識はあるが認容はない」と処理する可能性は乏しく,ただ,不作為犯の場合にあり得るであろう。これに対して,共犯の場合は,共謀の成立あるいは射程距離の問題として対処すれば足りるものと考えられる。
[25] 書研にかんがみ若干の補足説明を加える。刑法175条を例に採ると「わいせつな」という点が構成要件要素とされているので,この点についてのわいせつ性の認識が必要であることは明らかであると解される。ところで,刑法175条にいう「わいせつ」とは,いたずらに性欲を刺激・興奮せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものをいう。そして,かかるわいせつ性の判断は,一般社会において行われる良識すなわち社会通念を基準として当該作品自体からして純客観的に行うべきものとされるが,わいせつ性の有無は文書全体との関連で行われなければならないとするのが判例である。さらに,文書のわいせつ性の判断にあたっては,①当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法,②かかる描写叙述の文書全体に占める比重,③文書に表現された思想と描写叙述との関連性,④文書の構成や展開,⑤芸術性・思想性による性的刺激の緩和の程度,⑥以上を総合して文書全体としてみたときに主として読者の好色的興味に訴えるものと認められるかを考慮する必要があるとされている。
そうすると,「わいせつ」について認識しているというためには,本来,行為者が,上記の意味を総合的に判断した結果,わいせつであるということを認識しつつあえて文書を頒布したことが必要ということになる。しかしながら,規範的構成要件要素については,裁判官の規範的・評価的な価値判断を受けなければ,それが,「わいせつ」にあたるかは判明しないのであって,その認識を行為者に求めるのは無理ということができる。
そもそも,一般的に構成要件的故意の認識の対象とされているのは,犯罪事実といえる。これに対して,規範的構成要件の「わいせつ」とは,評価そのものといえる。そうだとすれば,評価の結果を認識することを要求したとしてもどのような根拠でその評価をしたのかを明らかにする必要がある。そこで,その評価の前提としてどのような事実を認識していたかを問題にする必要があると考えられる。そのうえで,法的ではなく社会的なメジャーでわいせつ性の認識があったかをみるのである。
具体的には,「社会的な事実関係において,一般通常人が知っているような意味・性質の認識」が故意の要件となる。これは,①ある社会的事実がある⇒②一般人の知識に依拠したうえで,その社会的事実について,ある社会的な評価がされてその評価を認識していること―になると思われる。換言すれば,法的な評価を行為者に求めることはできないが,社会的な評価は行為者に求めてその社会的な評価を認識していること(意味の認識)が必要という意味に考えればよいように思われる。わいせつ図画頒布罪に即すると,例えば,女子の全裸のみならず陰部をことさらに強調したり,男女が性交したりしているところ,それぞれの性器をエモーショナルに強調する図画であったとしよう。これを一般人がみると,社会的においても,このような図画は,いわゆる『裏モノ』として違法であるということの認識は持っているのが通常と思われる。そうすると,当該図画が詳細な「わいせつ」な定義に該当するかではなく,いわゆる『裏モノ』という社会的意味を認識しつつ,あえて,頒布をしたのかという点が問題とされていると考えられる。この点,判例は評価の前提となる事実さえ認識していれば,問答無用で故意を認めているという誤解がされる場合がある。すなわち,例えば,上記のわいせつ性の判例の判断基準に照らすと,わいせつにあたるかは,女子のヘアが移っているか否かがメルクマールになるものではないことが明らかであるが,世間では,『ヘアさえ移っていなければ,合法』という誤った認識が広がっていた時期があるように思われる。そうすると,前提事実は,「ヘアが写っていない女子の全裸写真」ということになるが,これさえ認識していれば「わいせつ」の故意あるとすると誤解されている。しかしながら,上記のように,社会的意味を認識している必要がある。つまり,社会的意味を認識していない限り,規範的構成要件要素が問題となる構成要件では,故意を欠くのである。即すると,「ヘアが写っていないならば,裏モノにあたらない」と考えていた場合,上記で述べた『裏モノ』で違法という社会的意味を認識していなかったと考えられるわけである。
このように考えてくると,規範的構成要件要素の判断とは,構成要件それ自体ではなく,むしろ,社会的意味の認識があるかという法的評価から離れた社会的評価が必要となるように思われるのであって,その判断はかなりの特色があるものということができるように思われる。書研は,この社会的評価をしてそれを認識しているかを,「素人間の並行的評価」と評するが,たしかに,客観面では,裁判官は「わいせつ」性について法的な評価をしつつ,主観面の検討では,それとは別個に,行為者は,「わいせつ」性について社会的な評価をしてその認識をしているかを検討するわけであるから,判断枠組みがまったく異なっているということができるのである。これをとらえて,並行的評価とするのは的確のように思われる。したがって,法的にわいせつ性を認められても社会的意味でわいせつ性が認められないということは考えることができるように思われる(実際は法的なわいせつ概念も社会通念が基準となるから考えにくいが)
[26] 木谷38は,故意とは,「現実的な心理」であり,この心理状態は「事実」であることを強調する。そのうえで,認定にあたっては,①故意に関係する間接事実⇒②「ひょっとすると死ぬかも知れない」などの結果に対する何らの心理的な「事実」を推認⇒③その「心理的事実」が故意犯に必要な「認識」「認容」に該当するという法的評価―という流れを採る必要があるとする。そして,間接事実から直接法的な故意(つまり①⇒③)を認定するという流し方は相当ではないとする。なぜなら,合理的人間であれば結果発生を当然予見するとしても,まったく軽率にも結果は発生しないと確信する者はいるところ,刑法の解釈ではそのような者に故意を認めることはできないといわざるを得ないからである。つまり,故意の認定の積極方向の間接事実からストレートに故意を認定することはできず,行為者の「現実的な心理」という事実をターゲットにして,それを評価するという流れが必要なのである。たしかに,故意の責任非難は突き詰めてゆけば,「分かっていたのにどうしてやったのか」という点にあり,「分かるはずの状況であった」というにすぎないのでは,責任非難の基礎となる事実の存在が認定されていないので,注意が必要と考える。
[27] 現実的心理という事実の認定についての手順について説明する。この点,現実的心理として捉える順番は明確な方から①意図⇒②確知⇒③結果発生の可能性の認識という順番になる。意図とは,確定的故意に,結果発生の可能性の認識が低くても故意が認められる場合をいい,イメージ的には,「蓋然性よりも低い可能性の認識+積極的認容」といえる。確知とは,結果発生を嫌っていても故意が認められる場合をいい,イメージ的には,「蓋然性の認識+消極的認容」の場合といえる。要するに,上記の2枚のカードの組み合わせが揃えられるのであれば,それを優先すべきであるという発想である。そうすると,「蓋然性よりも低い可能性の認識+消極的認容」というカードが揃ってしまった場合の処理をどのように考えていくべきかがここでの問題といえる。このように考えてくると,故意の要件事実である現実的心理とは,「結果発生の蓋然性の程度と認容の積極さの程度」の相関関係で決まるともいえよう。そこで,ベースラインとしては,行為の客観的内容や危険性を把握し,行為者の認識した結果発生の可能性の程度を検討してゆくことになるが,この2枚のカードしか揃わない場合は,故意は否定されるかも知れないということを念頭に置く必要があるであろう。
[28] 薬物密輸のような事案では,行為者は隠匿された中身を見たことがなく,依頼者からもわずかな説明しか受けていないので,隠匿物の具体的な属性を認識していない場合がある。この場合に大麻密輸罪の故意があるといえるかが問題とされる。ここでは,故意があることを前提に,どのように文章を流したらよいかを説明する。東京高判平成16年3月5日東高時報55巻1~12号10頁は,情況証拠から,被告人らは「大麻を含む違法有害な薬物類」が隠匿されていることを未必的に認識したと推認している。この判断の過程は理解が浅いと誤解しかねないものであるので,慎重に検討する必要がある。すなわち,東京高判の判断の過程は,①依頼が不自然,スーツケースも異様に重い,高額の報酬で隠密に輸入⇒②被告人の現実的心理として「隠匿物は少なくとも『違法有害な薬物類』ではないかと推測した」という事実を認定⇒③認識・認容があると評価―という流れを辿っている。この点,もう少し敷衍すると,①⇒②の認定の過程が極めて重要である。というのも,違法有害な薬物類の認識と評価するには,①で挙げた事実の総合的な評価から,被告人はこのような現実的心理をもったに違いないと推認することはできないからである。たしかに,この程度のものであれば,例えば,わいせつな図画を輸入しようということにも起こり得るのであり,それが違法で有害な薬物と推認するには飛躍があるように思われる。そうだとすれば,この東京高判の判断の過程はどのようなものであったかについては,②は,「現実に被告人自身が推測したという心理的な事実」を根拠にしているといえる。つまり,①⇒②を導いたというよりも,②を直接推認する証拠類(例えば,自白)があったのではないかと考えられるわけである。つまり,判例が現実的心理の事実の認定をしているという部分を理解しないと,①⇒③を推認しているように思えて,しかも本件のように客観的な推認が成り立たない場合には,「判例はなんと権威主義なのであろうか」とか「責任主義に反している」という批判があり得るのである。したがって,②の作業が必要であるということを今一度自覚すべきものである。そのうえで,本件のケースでも,②を独立に認定できる証拠がないのであれば,故意を認めるのは困難なように思われる。
[29] 早すぎた結果実現は,故意が認められるかという問題と思われる。そして,判例のケースでは,実行の着手が認められるとしても,行為者としては,未遂の故意しかなく,既遂犯の故意はなく殺人未遂にとどまるとする見解もあるが,故意は未遂の故意と既遂の故意に分断することはできない。また,第2行為を留保しているからといって,第2行為で結果が発生しなかったというのは,あてはめの錯誤にすぎないとする見方もある。
[30] この点,最判昭和53年7月28日では,「通行人Bに対し・・結果が発生し,かつ,・・因果関係が認められる」から殺人未遂罪が成立するとしているが,松宮教授は,従前,「結果の発生」を要件とすると主張されたことがあったように記憶している。しかしこの説示は具体的事例に即したものであるから,結果の発生まで必要とするものではなく,実行の着手,すなわち結果発生に向けた現実的危険性が生じているのであれば,未遂罪は成立するとみるべきであって,判例が未遂罪を成立させないという趣旨を読み込むことはできないように思われる。
[31] ここでも19世紀的な思考と20世紀的な思考で説明できる。19世紀的な思考を貫けば国家は市民社会に対して必要最小限度の介入しかしない。これは,逆に言えば,個人の意思が尊重される私的自治が優先されるということになる。そうすると,被害者が法益侵害について承諾をしているのであれば,それは意思に基づいているのだから,国家が刑罰権をもって市民社会に介入する必要はないという判断に結びつきやすい。徹底した結果無価値論は19世紀的な思考に近いといえる。これに対して,20世紀的な思考となれば,政府はさまざまな領域で市民社会に介入してくることになる。そうすると,たとえ本人が同意していたとしても,パターナリスティックな視点や社会全体の秩序の維持という観点から,本人の意思を無視してでも刑罰を科すべきときがある。判例の立場は,20世紀的な思考がうかがえる。
[32] 『法益関係的錯誤説』によると,政治家が秘書に,「賄賂をもらったのは,お前ということにして自殺してくれ。その代わり,お前の遺族には後で1億円やる」といったので秘書は自殺をしたが,遺族には1万円の見舞金を支払っただけで終わったとしても,処分する法益には錯誤がないから自殺教唆にとどまるという結論になると考えられる。やり方が卑劣だから処罰するということは妥当ではない。
[33] 正当防衛については,憲法上の正当防衛権という基本的人権を認める者もいる。たしかに,私たちは,基本的な法益侵害状態からの回復の機能を国家に委ねることとしたために,自力救済というのは近代社会においては否定されるものといえる。問題は,生命・財産の維持という点について私人にどの程度の正当防衛権を認めるかである。周知のようにアメリカでは,拳銃の所持が許されている州があるが,これは正当防衛権を広く認めようとする観念があるように思われる。しかしながら,この論点では19世紀や20世紀の視点で語れるわけではない。というのも,どのような政府の役割論を採ったとしても,市民の生命・財産を守るのは国家の役割ということは認められるからである。そうだとすれば,後はどの範囲で正当防衛権を認めるのかというとその国の文化的諸条件が大きく影響してくるものと思われる。
[34] 『防衛の意思』を理解するにあたって留意すべきは,認識的要素と意思的要素に区別するということである。そうすると,防衛の意思の必要性の有無に関わらず,まずは侵害行為を認識しているという点が前提となっている。そのうえで,どれほどの防衛に関する意思的要素が必要かということがここでの問題である。この点,防衛の意思に過度の意思的要素を求めるのは妥当ではない。なぜなら,防衛行為は本能的に行われるのが普通であるから,通常,行為者としては侵害行為を認識さえすればあとは反射的に反撃行為を行うのが通常だからである。そこで,判例は,防衛の意識さえあればよいという点のように意思的要素を稀釈させてしまっている。そうだとすれば,防衛の意思不要説も学説によると思われるが,急迫不正の侵害行為の存在を認識していることを要件とするものが多いだろうから,実際上は,不要説と必要説の差異はないということになる。重要なことは,行為者が防衛行為をするにあたっては,侵害行為の存在を認識しているかという点である。そうすると,偶然防衛のケースでは,防衛の意思不要説からも侵害行為の存在を認識しているとはいえないから正当防衛の成立は認めがたいということになると思われる。
[35] 防衛の意思と加害意思が両立するかは,防衛の意思にどの程度の意思的要素を認めるかに関わっていると思われる。この点,防衛の意思に多くの意思的要素を求めれば,当然加害意思と併存することは難しい。これに対して,判例のように防衛の意思を実質的に中身のないものと理解すると,攻撃意思との両立は肯定しやすい。
[36] 最決平成20年6月25日は,「所論は,第1暴行と第2暴行は,分断せず一体のものとして評価すべきであって,前者について正当防衛が成立する以上,全体につき正当防衛を認めて無罪とすべきであるなどと主張する。
しかしながら,前記1の事実関係の下では,第1暴行により転倒した甲が,被告人Xに対し更なる侵害行為に出る可能性はなかったのであり,被告人Xは,そのことを認識した上で,専ら攻撃の意思に基づいて第2暴行に及んでいるのであるから,第2暴行が正当防衛の要件を満たさないことは明らかである。そして,両暴行は,時間的,場所的には連続しているものの,甲による侵害の継続性及び被告人Xの防衛の意思の有無という点で,明らかに性質を異にし,被告人Xが前記発言をした上で抵抗不能の状態にある甲に対して相当に激しい態様の第2暴行に及んでいることにもかんがみると,その間には断絶があるというべきであって,急迫不正の侵害に対して反撃を継続するうちに,その反撃が量的に過剰になったものとは認められない。
そうすると,両暴行を全体的に考察して,1個の過剰防衛の成立を認めるのは相当でなく,正当防衛に当たる第1暴行については,罪に問うことはできないが,第2暴行については,正当防衛はもとより過剰防衛を論ずる余地もないのであって,これにより甲に負わせた傷害につき,被告人Xは傷害罪の責任を負うというべき」とする。調査官のコメントでは,「おれを甘く見ているな。おれに勝てるつもりでいるのか」という言動などから第2暴行は性質が異なっていると見ているようでである。判例は,素朴な行為1個・2個論によるのではなく,防衛の意思の有無,発言の有無,第2暴行の程度などが判断要素としている点が注目される。
[37] 犯罪理論で判例が採用する折衷的な考え方を前提とすると,行為主義のみを強調する道義的責任論も,性格責任を強調する社会的責任論もいずれも妥当ではない。そうすると,ここでも折衷的な考え方をとることになる。ポイントは,人格責任論は,行為責任と性格形成責任の抽象概念という点であろう。書研では,帰責の問題では,行為責任のみ考慮すれば足りるのであって,性格形成責任は量刑でのみ考慮されるとする。
[38] 責任故意について,まず,故意については,構成要件的故意としてその大部分が構成要件にせりあがっている。そこで本籍地である責任において判断される故意は,構成要件にせりあがらなかった部分に限られる。この点,違法性の意識の認識・有無については,様々な資料がいることから構成要件該当性の判断にはなじまないため構成要件化されていないと解されている。したがって,その事実が違法であることを認識し又は認識し得たかという規範的側面は,非難可能性の問題として検討すれば足りる。
[39] この点について,若干の補足的意見を述べておきたい。実務上は,例えば,現住建造物放火については,放火の故意が争われるということが少なくない。そして,それは,例えば,カーテンに放火をしたところ,カーテンを燃やすという意思しかなかったのであり,したがって,そこから建物に燃え移るという故意はなかったという見解が指摘されることがあると考えられる。この点について,実務的な発想としては,まず,①行為の危険性を特定し,②この①の行為の危険性から推認される行為の意味を特定する。そして,③そのような建物に燃え移るというメカニズムという意味を知っていたというのであれば,それは建物に対する放火の意思があるということになると思われる。実務上は,理論的にはともかくとしてこのような推認構造をとっているものと思われる。ところで,これを理論的に引き直すと,おおむね次のようになるのではないか。まず,理論的には問題とされるのは,「構成要件的故意」のはずであるが,この場合は,構成要件該当行為,すなわち,カーテンに火をつけるという行為についての認識はあったと思われる。そうだとすれば,かかる認識によって構成要件的故意は満たされるように思われる。にもかかわらず,故意が欠ける場合があるかということで問題とされるのは,「責任故意」の有無のように思われる。すなわち,責任故意は,構成要件的故意のように類型化されたものではなく,個別的な事情を斟酌するものである。例えば,30歳の男が自宅の放火しているものの,心神耗弱のような状態にあったので,カーテンから火が燃え移るということメカニズムが理解できない可能性があったと思われる。このような個別事情を責任故意の枠組みの中で判断すべきものではないかと思われる(私見)。
[40] 論理必然ではないが,違法性の意識不要説には20世紀的思考,つまり,社会的責任論が潜んでいると考えられる。すなわち,道義的責任論を徹底すると,違法性を認識していなければ道義的非難は成り立たないように思えるが,社会的責任論は,そもそも自由意思を認めないわけであるから,道義的責任は成り立たず,したがって,行為者の人格形成責任を問うわけである。そうすると,行為者の性格が社会的に危険であれば,それだけで責任非難が成り立つから,行為者が違法性の意識を有していたかは,半ばどうでもいいということになると思われる。
[41] 補足して説明しておくと法律の錯誤があるからといって,直ちに責任故意が阻却されるわけではないという点に注意が必要である。すなわち,法の不知やあてはめの錯誤という法律の錯誤の結果,『違法性の意識』を欠くか否かの問題となる。つまり,法律の錯誤があっても違法性の意識を欠かない場合,本文の定義に照らして考えてみると,そもそも,『法律の錯誤』があったとはいえないのである。結局,法律の錯誤があった結果どうなるかは,違法性の意識論の処理に関わるといえる。
[42] 素朴な疑問として書研のように法律の錯誤と事実の錯誤を分けると,結局,あてはめの錯誤において,錯誤に相当の理由がある場合も事実の錯誤になってしまうのではないかと考えることができる。結論はともに故意阻却というわけであるから,たしかに,区別する必要はないのであるが,少し割り切りすぎとも思える。また,社会的意味の認識という説明概念を用いた方が有用なようにも思える。つまり,違法性の意識が可能な程度の事実認識が必要ということになれば,この事実認識には社会的意味の認識も含まれると解釈すべきであるが,この点を意識的に論じないのは不当なようにも思える。
[43] だが,例えば,急遽出張で1日前から京都の自宅から離れて,札幌にいたと言う場合はどうであろうか。日常的に使用されている建物の本人のベッドで寝ているという事情の変更は異常性が低いと思われるので蓋然性を認めてもよいのであろうか。しかし,1週間前から旅行で札幌に行っている場合はどうかとなると,「偶然トイレに行っていた」というケースからどの程度離れていいのかという問題点は避けて通ることができないように思われる。結局,異常性が低いか否かは一般人の視点から見るほかないように思われるから,実際上,具体的危険説の判断枠組みと異なるところはないようにも思えてきてしまう。このような観点からすれば,あえて仮定的蓋然性説を採用するメリットはないように思われる(蓋然性の具体的な要素が示されれば別であるが)。
[44] 共謀共同正犯について限定的に解する見解も,関係者の行為が単独で分離したときに実行行為と評価することができる必要があるとまではしていない。そうすると,ここでの問題は,全体的考察から見て他の者,特に実行担当者と共同実行したものと認めることができる要件,すなわち,「実行行為の一部」とは何を意味するかが問題とされる必要がある。通説自体も実行行為を分担しないにもかかわらず,正犯性を認める間接正犯があるので,自分の手による実行ということが正犯であることの唯一の根拠であるという考え方は失当である。そうすると,物理的な身体の動作だけでなく,その行動の持つ価値的な意味合いを重視して正犯性を捉えていくという方向性にシフトしていかざるを得なくなる。これを「共謀」という主観面に求めたのが判例であり,「重要な役割」という客観面に求めるのが学説という方向性であろう。なお,重要な役割説に依拠すると思われる斎野268は,「本書は,60条の「実行」に直観的実行行為概念を結び付ける必要はなく,いわゆる実行共同正犯には限定されないと考える。その範囲は,まさに共同正犯として処罰するに値する因果性の存在に由来する。ある種の共謀は,違法結果について共同正犯として処罰するに値する因果性を有する場合があり,それを60条の『実行』と呼びたければ呼べばよいだけのことである」と指摘している。
[45] 共謀共同正犯を考えるにあたっては,個人責任の原則を守らなければならない。個人責任の原則とは,「何人も自己の有責な行為に基づいて発生させた不法な事態についてのみ責任を負う」とする原理をいう。したがって,他人の行為を帰責するにあたって,その行為者に帰責されてもやむを得ない特有の責任を根拠づける事情があって初めて共謀共同正犯の理論による帰責が許される。では,「帰責されてもやむを得ない特有の責任」とは具体的に何であるかが問題とされる。実行担当者は,2人以上の者の間で犯罪を実行することの合意が成立した場合,その合意に基づいて自己の意思で犯罪を遂行することになる。もっとも,その犯罪遂行についての自己の意思は,他の合意者との約束に基づいて形成されたものと考えられる。そうすると,実行担当者は,自らの意思のみで形成した犯意ではないので自己の一存のみで実行の意思を放棄することができないという心理的拘束を受けてしまう。このように,「実行担当者が自らの意思のみで犯罪遂行の因果性をコントロールできない」点を捉えると,他の共犯者は,実行担当者を一種の「道具」として利用しているということになる。これは言い換えれば,他の共犯者は,実行担当者の心理的拘束を媒介に結果に対する因果性を与えていると解することができる。しかも実行担当者は,「自己と志を同一にする者が存在するという事実によって心理的に鼓舞され,その意思の実現を容易にするような支援を受けている」と評価することができる。この点も他の共犯者が,実行担当者に心理的な働きかけをすることによって結果に対して因果性を与えているということができる。このような点に照らすと,全体として犯罪を共同遂行したものと評価することができるというわけである。このように考えてくると,共謀共同正犯とするには,どれくらいの心理的拘束を実行者に与えており,しかも鼓舞させているかという観点も考慮することができるであろう。これは,合意の実現の推進力に着目いていると考えられる。
[46] 共謀共同正犯が認められるには,犯意の存在とその合致が必要ということになる。これは,契約法理に置き換えると,「契約の申込みと承諾があること」に置き換えることができるであろう。すなわち,申込みがない段階で契約が成立しないのは当たり前であるから,そもそも犯意に欠ける場合に共謀共同正犯とならないことも当たり前ということができる。また,意思の連絡についても興味が持たれるのは,重要部分が知らされていない限り,意思の連絡が認められないという点である。これは,契約においても,例えば,不動産取引の場合は契約の要素が成熟するまでは,契約が成立しないと解されていることとパラレルにとらえられるように思われる。つまり,契約の中身がつまっていないということが意思の連絡を拒むという要素となるわけである。この点は,注目されていいように思われる。
[47] 大阪高判平成13年6月21日は,「Xは,Y子を制止しないで,前記のような態度を示している。これは,Xがそのような態度を示すことで,『秋子をこたつの天板に投げつけることによって殺害することを容認した』ものといえる。すなわち,Xは,秋子の実父であるところ,犯行当時,Y子の犯行を制止できるのは,Xのみであることを十分認識しており,また,Xは,Y子が秋子をこたつの天板に叩きつけようとしているのを十分理解し,Y子の『止めへんかったら,どうなっても知らんから。』という発言の意味するところも十分認識し,しかも,Xは,Y子が自分に制止して欲しいという気持ちを有していたことまでをも熟知していたというのである。しかるに,Xは,自らも秋子に死んで欲しいという気持ちから,Y子と一旦合った目を逸らし,あえてY子を制止しないという行動に出ることによって,Y子が秋子をこたつの天板に叩きつけて殺害することを容認したと評価できる。
以上によれば,秋子をこたつの天板に叩きつけるという方法によって,同児を殺害することについて,この時点において,暗黙の共謀が成立したと認めるのが相当」であるとする。
[48] 例えば,Aがメッセンジャーになって,A-B,A-C,A-Dと犯罪共同遂行について合意したとする。この場合は,BCDがA以外にも誰かが自己と共同の犯罪遂行のために結合した者がいることを知っていたときには,ABCDは相互に面識がなくてもAを中核とする共謀の関係に立ったと考えられる。
[49] この点も契約法理に置き換えると,「契約の要素」が詰まっているかというようにいえるように思われる。契約の要素について確定がもたれれば,契約の成立を認めてもよいように思われる。翻って,共謀の成否についていえば,何が中核的な部分かを特定する必要があると思われる。それによって,共謀が成立しているか否かについての認定を左右する。例えば,木谷判決で見られたように,「アイツ,やっちゃおうか」というのが強姦の共謀とみられるかについては,木谷判決はこれを否定していた。たしかに,この時点では,まず,犯意があるかどうか疑問が持たれるところである(和姦の可能性が残っていた)し,意思の連絡という点からみても,いったいどのように強姦するのかという具体的な犯行態様については,未だ確定する前ということもできる(「やっちゃおうか」に対して,「いいですね」と応じた段階であった)から,意思の連絡も認められないということになると思われる。なお,木谷判決の事案で,「アイツ,やっちゃおうか」で共謀を認めると,3人のうち1人は,「オレは本当にいいから」といって立ち去っているというのであるから,意思の連絡の側面を否定するのは難しいので,犯意の存在自体が否定された事例と理解するべきものであろう。
[50] つまり,「何らかの犯罪をする意図」があればよいということになる。これは,詰めて考えてみると,部分的犯罪共同説の重なり合いが認められる限度での広がりのある犯罪ということができよう。
[51] この点について備忘のために思うところを述べることとする。まず,私の理解によると,共謀の射程とは,どの犯意で犯意が合致したのかという問題であり,犯意が合致していない部分に基づいて犯罪が現実化した場合は,それは「共謀に基づく行為」とはいえず,したがって,60条で帰責することはできないと解している。それゆえ,共謀共同正犯では錯誤の場合は犯意の合致がないと解するので,問題とする余地はないと思っている。これに対して,藤木説は,「この種の事案では,共謀と実行との因果関係の確認が第一に重要なことであり,簡単に事を錯誤の問題として片付けることは許されない,ということをはっきり認識しておく必要がある」と指摘している。藤木説は,共謀の射程の問題を共謀と実行との因果関係の問題として把握しており,したがって,錯誤とは異なる理由で共同正犯の成立範囲が狭められることを認めている。注目されるのは,藤木説は錯誤の可能性を認めることである。もっとも,結論において藤木説は,錯誤により故意(?私見は疑問)を阻却する可能性はまったくないと考えられる。すなわち,共謀の場合は犯意の合致が必要であるから,少なくとも構成要件的に重なり合いのある限度で犯意が合致しなければそもそも共謀があることにはならない。そうすると,錯誤においても抽象的事実の錯誤は問題とはならず,問題となるのは具体的事実の錯誤のケースがほとんどであろう。そうすると,「共謀の内容たる合意と法的に合致すると認められる事実である限り」,共謀の内容である共同の意思に基づいて実行されたものとして,共謀者全員に帰責されることになる。したがって,共謀の射程⇒錯誤の順番で流すと論理的には錯誤となるケースはほとんどない。このように考えると,藤木説が安易に錯誤で処理してはならないとするのは真に正しいものがあるといえよう。
[52] 教唆者の故意としては,修正された構成要件事実の認識・認容で足りる。つまり,教唆行為に対応する認識・認容で足りると解する。したがって,構成要件的結果の発生を認容することまでは必要ではない。したがって,未遂の教唆についても教唆犯が成立すると解する。
[53] 幇助の因果性については,①幇助行為と正犯行為・結果との間に物理的因果性及び心理的因果性が欠ける場合は不可罰となる。また,②因果性を肯定しても,そもそも,「幇助」にあたるか,すなわち,実際に犯意を強化し,結果の発生を容易にしたといえるか慎重に吟味し否定されれば,そもそも「幇助行為」がないとすべきである
[54] 不作為による共犯は,必ず片面的共犯となる
[55] 幇助犯の作為義務の根拠が問題となるが,支配的な見解は,『原則幇助犯説』と呼ばれるものである。これによると,窃盗を見てみぬフリをするのは,原則として幇助とされる。つまり,作為正犯(窃盗犯)は,結果発生と直接的な因果関係をもって強い原因力を持つのに対して,不作為による関与は,原因力も弱く従たる役割を果たして,作為正犯の実行を容易にするのにすぎないからとされる。
[56] 札幌高判平成12年3月16日は,「不作為による幇助犯は,正犯者の犯罪を防止しなければならない作為義務のある者が,一定の作為によって正犯者の犯罪を防止することが可能であるのに,そのことを認識しながら,一定の作為をせず,これによって正犯者の犯罪の実行を容易にした場合に成立し,以上が作為による幇助犯の場合と同視できることが必要」とする。
[57] この点,教唆の因果関係は窃盗の犯意を放棄したところで断絶すると解することができる。断絶を肯定すれば,Xに帰責されるのは,せいぜい住居侵入罪までということになると考えられる。これに対して,断絶を否定すると,窃盗教唆を帰責することができる。この点,いったん犯意を放棄したとみられる事実がある場合,犯行態様の程度が一つメルクマールになると解される。これは,共謀の射程の議論に類似しているものと考えられる。すなわち,住居侵入窃盗の場合は同じような性質の住宅を見つけて侵入窃盗の決意を生じたという場合は必ずしもはっきりとした意思の断絶があるわけではない。したがって,因果関係を否定することは相当ではない。これに対して,学校荒らしを教唆したのに,断念後に住居侵入窃盗をしてきたという場合は犯行態様に大きな違いがあり,いったん意思の断絶があると評価しやすいものと思われる。