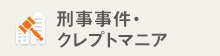公訴提起の手続
第14編 公訴提起の手続
第1 起訴状
1 公訴提起の方式
(1) 要式行為
公訴を提起するためには,裁判所に対して,起訴状を提出(256条1項)
(2) 起訴状の記載事項
① 被告人を特定するに足りる事項(256条2項1号)
② 公訴事実(256条2項2号)
③ 罪名及び罰条(256条)
* なお,規則164条
第2 公訴事実
1 意義―公訴事実と訴因
⇒ 『公訴事実』は,『訴因』を明示して記載する(256条3項)
(1) 公訴事実
公訴事実とは,訴因の背後にある前法律的,歴史的事実の中で,検察官が何らかの犯罪に該当すると主張する事実をいう
* AがBを死亡させた
(2) 訴因
訴因とは,これを犯罪構成要件に当てはめて構成した具体的事実をいう
* Aが殺意をもってBに暴行を加え死亡させた
(3) 起訴状に記載される公訴事実(256条2項2号)
起訴状に記載される公訴事実とは,前法律的,歴史的事実を犯罪構成要件に当てはめ,罪となるべき事実を特定して訴因を明示したものをいう(検察65)
* 訴因と起訴状に記載される公訴事実は,同じ事柄を指し示す術語であるので,両者の区別や相互関係を議論することは無意味(法教298号65頁)
* 刑訴法312条
* 訴因と罪となるべき事実との関係[1]
2 訴因の特定
(1) 意義
検察官は,起訴状に訴因を明示するには,「できる限り」,Ⅰ日時,場所及び方法をもって[2],Ⅱ「罪となるべき事実」を特定する必要(256条3項)
* 訴因の特定の問題が生じる場面
① 起訴段階(256条3項)
② 審理過程における訴因変更(312条1項)
③ 有罪判決における「罪となるべき事実」の摘示(335条1項)
(2) 訴因の特定の程度
ア 訴因明示の趣旨[3]
① 裁判所に対して審判の対象を明らかにする
② 被告人に対して防御の対象を明らかにする
イ 訴因明示の趣旨と特定
(ア) 識別説
識別説とは,訴因の記載は,他の犯罪事実から識別可能な程度に特定されていれば足りるとする見解をいう[4]
∵① 審判の対象を明確にすることが訴因の最も重要な機能
② 訴因の機能は,ある犯罪を他の犯罪から区別する点にある
③ 識別説の程度まで特定されれば,被告人は防御の指針を立てられる
* 『訴因特定必要事項ではないが,被告人の防御にとり重要な事項』
⇒ 審理過程で釈明権を行使により防御の機会を与える
(イ) 防御説
防御説とは,被告人の防御権の行使に支障がない程度まで記載する必要があるとする見解をいう
×① 基準が明確ではない[5]
② 捜査の長期化
③ 裁判官の予断を招く
3 訴因特定の具体的問題
(1) 共謀共同正犯の訴因における共謀の記載
ア 問題の所在
「被告人はAと共謀の上,・・・」という記載で足りるか
イ 検討
*論理的帰結の整理
| 共謀共同正犯・主観説 | 共謀共同正犯・客観説 | |
| 識別説 | そもそも,共謀を犯意の合致と解するので,共謀の日時・場所を特定する余地はない | 共謀を謀議行為ととらえると,日時・場所は問題にできるが,実行者の実行行為の日時・場所が具体的に特定されている場合には,他の共謀と区別できるので特定あり |
| 防御説 | 主観説を前提にすると犯意の合致が示される限り,共謀の日時・場所は防御権の行使にとって重要ともいえない | 共謀の日時,場所,内容を明示・特定を要求する防御説は,共謀共同正犯の法的性質について実体法上,客観説をとらない限り,成り立たないことになる |
* 学説の対立を超えて
共謀共同正犯の肯否ないし理論的根拠をめぐっては,学説上の対立が著しい。しかしながら,裁判員裁判を踏まえれば,このような理論的な対立は立証の目標となる最終目標が異なることを意味することになる。したがって,裁判官,弁護人,検察官は,公判前整理手続において共通の土俵に立った上での立証活動の展開が求められるということになると考えられる。
もっとも,これは判例にすべて従うということを意味しないと思われるが,最も重要であるのは,民法における要件事実的思考(読本Ⅰ119は,要証事実を指向した思考方法という)をマスターするという点である。すなわち,判例と通説が対立しているとすれば,被告人を有罪とするためには,判例からはいかなる事実を揃えればよいのか,逆に通説からはいかなる事実が揃えばよいのかということを理解しておく必要があるということである。したがって,「判例は妥当でなく,通説が妥当である」という主張をするのであれば,通説からは,どのような事実が重要となるのかということを理解しておかなければならない。逆にいえば,揃える事実が異ならないのであれば,実務においては学説の対立は意味が少ないということになろう。これは,当該法律の概念について理論的根拠を原理的に理解しておくことが必要であるということを意味する。
例えば,ここでは,共謀共同正犯において,なぜ共謀があると実行行為に関与しなくても全部責任が認められるのか,という本質論から共謀の要件を理解しておく必要があるわけである。この点,実質的正犯概念を採用し,実行正犯に対して心理的に影響を与えたという点に着目すれば,共謀とは「犯意の合致」があることが重要であるということが理論的に導かれるわけである。他方,同様に,実質的正犯概念を採用しつつも,当該犯罪を実行するについて重要な役割を演じたことに着目すれば,共謀とは「重要な役割をしたこと」と理解されることになるわけである。なお,形式的正犯概念を採用し,正犯が正犯たる所以は,構成要件該当行為を行ったことに理論的根拠を置けば,共謀共同正犯は否定されるということになろうが,逆にいえばこの見解からは,一部でもその者が構成要件該当行為をしているという事実がないかが重要となるわけである。
このような理論的視座が明確であれば,訴因が特定しているか否かについても,前者に立てば帰責の原理的根拠に照らせば,日時や場所を問題にする意味がないということは明らかであろう。これに対して,後者の立場からすれば,客観的に重要な役割をしているか否かが重要なのであるから,その行為をいつ,どこでしたのか-ということは問題にすることが可能である。したがって,後者の立場からすれば,いわゆる防御説に立つということも可能である。もっとも,重要な役割をしているか否かが本質的であるとすれば,重要な役割と重要ではない役割にかかる事実を区別することができれば,場所や日時は識別にとって重要ではないという解釈もあり得るものと考えられる。
いずれにせよ,法律要件というのは,当該法律概念の本質論に遡って理解しておかなければ,その知識というのは「死んでいる」のであって,学術的にはもとより実務でも活かすことができないのである(同旨,読本Ⅰ120)。
(2) 白山丸事件(最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号1633頁)
ア 起訴状の記載
犯行日時・・・「昭和27年4月ころから33年6月下旬までの間に」
犯行場所・・・「本邦」
犯行方法・・・記載なし
イ 判旨
犯罪の種類,性質などの如何により,日時・場所・方法を詳らかにすることができない特殊事情がある場合[6]には,審判対象の限定,防御範囲の提示という訴因特定の目的を害しない限り,幅のある表示が許される
ウ 奥野裁判官補足意見
本件公訴事実は被告人が昭和33年7月8日中国から白山丸に乗船し,7月13日に本邦に帰国した事実に対応する出国の事実を起訴したものと解すべきであり,右帰国に対応する出国の事実は理論上ただ1回あるのみであって,2回以上あることは許されないのであるから,本件公訴事実たる出国の行為は特定されている
エ 検討
① 犯罪類型の特殊性
実行行為の日時・場所・方法が不明であっても,罪となるべき事実の存在自体を起訴当時の証拠で確信の水準まで証明することが可能な特性が認められる
(適法な出国記録がなく,外国から来航した船に乗船して帰国したという事実により犯行の存在を高度に推認できる)
② 立証上の特殊事情
他の事実との識別という観点からは,事柄の性質上,識別が必要となるほかの密出国の可能性は事実上問題となり得ない(覚せい剤事案と異なり,短期間の間に何度も繰り返すことができる犯罪では,当時の交通事情ではなかった)
③ 防御上の具体的な支障がないこと
罪となるべき事実の存在が強く推認されるので,アリバイなどを争うことが無意味であり,被告人の具体的防御に支障がない
⇒ 当該出国に際して,合法的な手続を履践して出国したという事実や,白山丸で帰国したとされる日時の直前に日本にいた事実を立証することは容易
(3) 覚せい剤自己使用罪の問題
ア 特色
① 尿検査により使用の確実な推認が可能
② 自白がない限り,使用日時,場所,方法の特定が困難
③ 犯行の日時・場所・方法は犯罪の成否自体にとって決定的に重要ではない
イ 実務の対応
① 犯行日は,採尿の日又は逮捕の日から遡って数日ないし2週間程度の幅をもった期間とする
② 犯行場所は,その間に被告人が行動した地域を,市町村単位あるいは市町村とその周辺という程度の範囲で示すものとする
③ 使用方法は,「(注射又は服用して)施用し」と記載するものとされる
ウ 吉田町事件(最決昭和56年4月25日刑集35巻3号116頁)
「検察官において起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上,覚せい剤使用罪の訴因の特定に欠けるところはない」
エ 審判の対象が特定されているか
(ア) 問題の所在
問題の核心は,日時・場所などについて幅のある記載がなされたこと自体よりも,幅のある記載によって複数の犯罪行為が成立し得るという点にある[7]
* 覚せい剤自己使用罪と訴因の特定・明示の有無の位置づけ[8]
| 平成14年判例 | 白山丸事件判決 | 吉田町事件判決 | |
| 他の事実との区別 | そもそも,致死的加害行為では他の事実と区別する必要なし | 特定の帰国に対応する密出国は論理的に1回しかあり得ない | 尿の鑑定結果が陽性でも1回の使用には論理的に対応せず! |
(イ) 実務の対応
最終一行為説による対処
⇒ 検察実務では,「尿の提出時に最も近い1回の使用」を基礎したものと説明するのが一般的と言われる(寺崎264)
(ウ) 特定性を説明する学説
● 訴因は不特定とする見解
吉田町事件では,1週間ほどの間に複数回の使用があり得るし,覚せい剤の使用は各仕様行為が1罪を構成するので,複数の罪が成立することがあり得るので訴因は特定していないと解すべき(東大系の問題意識)[9]
×① 訴因に掲げられた期間中における複数回使用の抽象的可能性があることを前提にしても,起訴された行為の識別する方法はあり得る
② 採尿検査の結果があるときは,日時などの概括的記載から被告人の防御に直接の不利益は生じない
△ 最終一行為説(検察実務)
最終一行為説とは,尿の採取に先立つ最後の使用行為を起訴したものであるから,他の使用行為と区別することができるので特定されるとする見解をいう
× その最後の使用行為がいつ,どこでされたのかを述べることができない以上,観念的な説明である[10]
△ 最低一行為説(香城説)[11]
幅のある期間のうちで,少なくとも1回の使用をしたという意味の起訴であるから,他の使用行為と区別されるので特定があると説明する見解をいう
∵ 検察官は1回の使用を起訴している限り,複数回の使用の可能性を心配する必要はないという発想に基づいている
× 証拠上複数回の使用の可能性のある場合に,どの行為を起訴したかが不明になり,他の使用行為と区別することができないので,不特定となる
反論)他の使用行為が想定される場合であっても,検察官が1回の使用しかないと主張する限りは,二重起訴や一事不再理の問題が生じるおそれはなく,その解決のために訴因の識別機能が不十分となることはない
× そのような抽象的な特定は特定とは言わないのでは?
反論)訴因は,検察官の主張であり社会的事実そのものではないところ,複数回の使用があり得ても,そのうちの1個を起訴するのは検察官の訴追裁量の範囲である
⇒ 香城説は,前提としているはずの各使用行為が併合罪になるという枠組みを実際上放棄してしまっており,包括一罪説的な理解にかなり近い
* 最低1行為説のうち,被告人が10月12日午後10時と,10月13日午前2時の2回とも使用した旨を供述している場合は,公訴事実の同一性があるとして訴因変更ができるかが問題となっている。この点,私見ではできるものと解したものであるが,一般的には最低一行為説からすれば訴因変更はできないとなる結論になるという。すなわち,最低一行為説からすれば,鑑定書に現れた期間のうちの最低1回を起訴するという趣旨である。この見解は,詰めれば,その期間内ではそのどの使用行為かは識別しないのであるから,その期間内ではどの使用行為かは問題としない。したがって,訴因変更はできると解するのが私見である。これに対して,反対説によれば,その期間の1回を起訴するという趣旨である。そうすると,その期間に2回があると特定することができるのであるから両立せず,それゆえ訴因変更はできないとする見解であるというのである。ただ,反対説が裁判官らが言っていたものであるが,若干の疑問もありなお検討を有するものと思われる。
参考)大澤説[12]
⇒ 佐藤隆之「傷害致死罪における訴因の特定」平成14年重判181頁と同旨ではないかと思われるので以下で引用
「広島高田覚せい剤自己使用事件でも,・・・訴因の機能との関係でも,検察官は,複数回の使用を主張していない以上,起訴状記載の期間内における,一回のみの覚せい剤の使用を起訴しているのだとすると,審判の対象としては明確だといえ,他方,尿検査の結果覚せい剤が検出されている以上,犯罪の日時,場所および方法の表示に幅があること自体が,例えば,被告人が,使用行為自体を否定したり,法定の除外事由の存在を主張したりすることを直接妨げるわけではないと考えられるため,被告人に防禦上の不利益をもたらすものではない」
* それぞれ鑑定に対応する最終使用を起訴する場合,すなわち一度逮捕されて釈放されたのに再び使用して覚せい剤の鑑定書が2通あるというような場合のみ起訴するという場合である。2つの事実は一度採尿されて,いったん帰されたが,その間に使いつつ逃げていたというような場合に2つ併合して起訴するということがなされている。
* 逆算して考えると,鑑定書から推測される期間は公訴事実の同一性があるという発想に近いということになる(前提が鑑定書1通と場合と2通の場合で異なってくる)。
* 日時を特定している場合はもう両立すると言ってしまうと考えるが,日時を特定していない概括的な場合では両立しないと言ってしまうという運用も考えられる
* 実務では鑑定書の通通分しか起訴をしないという運用で固まっている
(4) 特定の被害者に対する致死的加害行為(最決平成14年7月18日刑集56巻6号307頁)
ア 特色
1回しかあり得ないので個性が強い犯行
イ 事案
被告人Xは,①平成9 年9 月30 日午後8 時30分ころ,福岡市中央区所在のビジネス旅館 2 階7号室において,被害者Vに対し,「同人の頭部等に
手段不明の暴行を加え,同人に頭蓋冠,頭蓋底骨折の傷害を負わせ,よって,そのころ,同所において,同人を右傷害に基づく外傷性脳障害により死亡する
に至らしめた」,②Y,Zと共謀の上,同年10 月1日ころ,福岡県前原市の山林内に,Vの死体を投棄し,もって死体を遺棄した,という傷害致死および
死体遺棄の事実に基づいて,起訴された。
ウ 判旨
原判決によれば,第1 次予備的訴因が追加された当時の証拠関係に照らすと,V に致死的な暴行が加えられたことは明らかであるものの,暴行態様や傷害の内容,死因等については十分な供述等が得られず,不明瞭な領域が残っていたというのである。そうすると,第1 次予備的訴因は,暴行態様,傷害の内容,死因等の表示が概括的なものであるにとどまるが,検察官において,当時の証拠に基づき,できる限り日時,場所,方法等をもって傷害致死の罪となるべき事実を特定して訴因を明示したものと認められるから,訴因の特定に欠けるところはないというべきである
エ 特色
① 被告人が犯行に及んだこと自体は証拠上明白であると判断されるが,犯行の日時・場所・犯行方法・共犯関係などが具体的に明確ではなく,記載が抽象的にならざるを得ない。他方で,これらの諸要素はいずれも審判対象の識別・画定という訴因の第一次的機能の観点からは不可欠な記載事項ではない
② 特定の被害者に対する致死的加害行為という個性のある犯罪事実であるために,区別しなければならない他の殺害行為は存在しない[13]
③ 被告人の具体的防御にも支障がないケース
オ 検討
今後は,1回しかあり得ない特定の被害者に対する致死的加害行為を含む犯罪類型(強盗致死罪)については,他の事実との区別が必要ないことから,審判対象の画定と被告人の防御目標の告知機能が害されない限り,概括的記載が許容される(酒巻)
* ただ,注意すべきは,通常,この種の事案では,日時や場所の記載が困難といえるような事情はまったく存しないことが多い。したがって,「訴因の特定・明示」のうち審判対象画定の見地からは問題はなくても,被告人の防御権を保障する見地から,不意打ち認定になっていないかは吟味する必要あり
4 訴因の特定を欠く場合
(1) 犯罪事実が特定されず,訴因が他の犯罪事実と区別できない場合
ア 効果
審理を開始することができず,裁判所は公訴自体を棄却(338条4号)
イ 典型例
① 「被告人は人を殺したものである」
② 「被告人は他人の財物を窃取したものである」
* およそ具体的な犯罪事実の記載とはいえず,他の事実との区別ができない
(2) 具体的な事実はあるが不明確で犯罪事実の特定が困難な場合
ア 効果
⇒ 裁判所に釈明義務
∵ 裁判所は,訴因の明示を欠くと認めた起訴状については,被告人側の求釈明の申出の有無にかかわらず,検察官に釈明を求める訴訟法上の義務あり
イ 犯罪事実の特定に不可欠な事項が検察官の釈明により明確化された場合
⇒ 釈明内容は訴因の内容となったと解すべき
∵ 釈明によってはじめて訴因明示の要請が充足されて起訴が適法となった
* 後の審理過程を経て裁判所が検察官の釈明内容と重要部分で異なる事実を認定しようとする場合は,原則として訴因変更の手続が必要
(3) 訴因は特定しているが,特定に不可欠ではない事項の記載が不明確な場合
ア 効果
① 公訴提起は無効とならない
② 裁判所に訴因に関して釈明を求める法的義務も生じず
イ 裁判所の手続裁量
裁判所は訴訟指揮の一環として合目的的裁量による釈明権限あり
⇒ 被告人の起訴状に対する認否や防御目標の明示に一層視すると思われる事項を明確化したり,具体的に明らかにするよう検察官に釈明を求めるのが望ましい場合あり
* 裁判所が釈明を求めれば検察官はこれに従い釈明する義務あり
ウ 犯罪事実の特定に不可欠でない事項について検察官が釈明した場合
⇒ 釈明内容は訴因の内容とはならないと解すべき
∵ 審理対象の特定という観点
* 後の審理過程を経て,裁判所が異なる事実認定をするときに,原則として,訴因変更手続はいらない[14]
5 訴因の予備的・択一的記載(256条5項)
(1) 予備的記載
「A」しからざれば「B」
(2) 択一的記載
「A」又は「B」
* 数個の訴因及び罰条は,公訴事実の同一性が認められる範囲内である必要* 実務では,ほとんど利用されず公判の推移により訴因の追加・撤回・変更
(312条)となるケースが圧倒的(検察69)
第2 起訴状一本主義
1 意義
(1) 定義
起訴状一本主義とは,起訴に当たっては,起訴状だけしか提出してはならないという原則をいう
(2) 制度趣旨
① 裁判所の予断排除
② 訴訟構造の転換
2 予断排除
(1) 脅迫文書や名誉毀損文書の引用
① 犯罪方法の特定の観点
② 予断排除の観点
⇒ 予断を生じるおそれのある文書の内容を引用することは原則として許されないが,恐喝事件の脅迫文や名誉毀損の文書でその表現が犯罪構成に欠かせない例では,ほぼ全文の引用も許されることもある(寺崎186)
(2) 余事記載
余事記載とは,訴因の明示に必要でない事項を起訴状に記載することをいう
ア 起訴状一本主義の射程距離
余事記載は,起訴状一本主義には反しない。256条6項が禁止しているのは,添付・引用だけであり,起訴状の記載は検察官の主張にすぎないので,直ちに予断を生じさせることにはならない
イ 余事記載を制約する原理
(ア) 根拠
余事記載は,256条2項が起訴状の記載事項を限定列挙し,3項は,簡潔な記載で訴因を特定・明示するよう求めている(寺崎187)。そこで,詳細・具体的な余事記載は,256条6項ではなく,256条2項3項の趣旨から許されない
(イ) 典型例
同種前科の記載
⇒ 予断を生じさせるおそれのある事項にあたるが,前科が犯罪の構成要件となっている場合や公訴事実の内容である場合は適法
* 犯罪の動機
⇒ 殺人,傷害致死,放火などの動機犯罪については,犯意を明確にし,ひいては,罪となるべき事実自体も明確にするという限度で動機を例外的に記載する場合はあるが,この場合でも,予断排除の原則に抵触しないよう簡潔に記載すべき(検察68)
[1] 平成14年判例の調査官解説は,識別説の理解は,335条1項の有罪判決に示すべき『罪となるべき事実』の判示の程度(概括的認定) に関する判例及び通説の立場と整合すると指摘している。256条3項と335条1項は,必要とされる特定の程度に関しては同じであるという趣旨と解される。そうすると,概括的認定に関する判例・通説の可否を決するのも,識別できるか否かということになると考えられる。したがって,335条1項の罪となるべき事実においても,被告人の所為がどの構成要件に該当し,他の犯罪事実と区別できるかという観点から判断されることになると思われる。
[2] 訴因が特定するというためには,常に,日時,場所,方法の記載が不可欠というわけではない。たしかに,犯行の日時が不特定化すれば,そのような訴因の記載は,構成要件の記載そのものと同じとなり,識別の用をなさなくなる。例えば,強姦罪は,同一人物に対する複数回の強姦もあり得るので,日時,場所,方法は必要である。しかし,審判対象の識別・画定と防御目標の告知という法の目的という観点からすれば,犯行の日時・場所・方法が一般的には重要な意味を持たない犯罪類型もあり得る。たとえば,殺人罪の場合は同じ人を殺すということはあり得ず,1回しかあり得ない。それゆえ,殺人罪の場合は,日時,場所,方法の特定は不可欠というわけではない。日時・場所は,訴因を特定する一手段にすぎない。
[3] 訴因明示の趣旨には論理的な順序があるので,この2つは,並列的に並べてはいけない。すなわち,訴因の明示の一次的な趣旨,目的は,起訴の名宛人である裁判所に対して,公判における審理の対象を具体的に呈示し,裁判所がこれを他の事実から識別・特定して審理を開始・進行することができるようにする点にある。そして,この第一次的な趣旨・目的が達成される効用として,訴追の対象となる被告人に対して,被告人の防御の目標が明らかになるという関係にあるのである(法教298号70頁)。
[4] 注意すべきであるのは,最決平成13年4月11日刑集55巻3号127頁が示した「審判対象の画定の見地」の要請を充足するかの判断基準が識別説という点である。
[5] 訴因の特定・明示の段階で,「被告人の防御の利益」を強調するのは相当ではない。なぜなら,訴因の特定の第一次的な趣旨・目的は,審理開始の時点における審理対象の識別・特定と被告人に対する告知機能にある(法教298号70頁)。したがって,被告人の防御との関係では,まず,訴追側主張の告知がなされることで,被告人の防御の観点は満足せざるを得ないものと考えられる。そして,被告人の防御活動に資する様々な側面は,起訴状提出意向の手続過程の全体を通じて担保されるべきものと考えられる。
[6] 判例は,特殊事情について,判文上は,直接の被害者がいないことや犯行目撃者がいないなどの犯罪の密行性と被疑者の否認・黙秘に伴う捜査・証拠収集上の困難をいうように見えるが,それは審判対象画定の見地から訴因の特定があるかとは関係のない事情である。むしろ,判文には書かれていない「真の事情」とは,要するに,他の犯罪事実があり得ないので,識別することには問題はなかったという点にあると解せられる(法教298号76頁)。したがって,訴因に日時・場所・方法について抽象的な記載がなされていても,それについて,捜査機関が「できる限り」のことをしているかという行為無価値を問題にするのではなく,あくまで,法の目的である審判対象の識別・画定と防御目標の告知機能が害されていないかという点の判断に尽きるものと解せられる。白山丸事件以降,最高裁判所は「特殊事情」というワーディングを用いなくなったが,これは,白山丸事件で挙げられている特殊事情が,捜査機関の行為無価値や被害者や目撃者がいないという,審判対象画定の見地とは関係ない,間違った事情ばかりであったので,後の判例ではこの点は触れられなくなったものと考えられる。
[7] すでに,尿検査によって覚せい剤が検出されているから,必ず覚せい剤を自己使用しているという点は確実であり,いつ・どこで・どんな方法で覚せい剤を使用したかの特定は,犯罪の成否に影響を与えるものではない。例えば,犯罪の成立が決定的である以上,アリバイなどの主張をしても無意味である。したがって,ここでの問題の本質は,裁判所に対して示す審判の対象が特定されているかという点にあるわけである。そうすると,特定の有無は,実質的に他の犯罪事実と区別することができるかにより決まるということになる。この点,演習221は,「覚せい剤使用罪の性質に基づく捜査の困難さは否定できない」とするが,吉田町事件の「特殊事情」は,目撃者がおらず,捜査が困難であることを問題にしているわけではないことを正しく理解しておく必要がある。
[8] 白山丸と吉田町の区別が難しいかもしれないが,白山丸事件では,たしかに,帰国時に逮捕されているところ,その帰国に対応する出国は1回しかあり得ないので,「他にも密出国している」という他の事実があり得るとしても,それは,1回しかない帰国行為に対応するものではないので,論理的に他の犯罪事実との区別は問題にならないといえる。そういう意味では,白山丸事件は,平成14年判例の思考に近いものがあるといえる。これに対して,吉田町事件の場合は,そういう訳にもいかない。というのも,被告人の尿から陽性反応が出てきたといっても,それは,複数回の使用の結果がまざっていることも十分考えられるからである。そうすると,いったいどの行為を起訴しているのかというのは,審判対象画定の見地から深刻な問題を提起することになると解せられる。
[9] 東大系の学者たちは,特に,覚せい剤事犯については,「訴因の特定がないのではないか」という問題意識を持っているように思われる。すなわち,訴因の特定があるというためには,他の使用行為と区別することができるのが前提であり,これは,審判対象画定の見地に由来するものであるから,被告人の具体的防御は害しないという理由で緩和することは許されないからである。酒巻は,最終一行為説や最低一行為説について,「いずれも難点があり,『訴因の明示』ないし『罪となるべき事実の特定』の第一次的な識別機能が真に満たされているのか,あるいは,問題の合理的な解決であるのか,なお疑問が残る」とする。そのうえで,酒巻は,「訴因の識別機能という刑事手続の基本枠組みを動揺・不安定化」させるくらいであれば,端的に,刑法の解釈として,覚せい剤の使用行為は,包括一罪説によるべきではないかと指摘している。
[10] なぜ,最終一行為説によると観念的であるかを考えてみよう。客観的に被告人Xは,1月1日,1月4日,1月5日に覚せい剤を使用としていたとする。検察官は,「どうやら,3回覚せい剤を使用したらしい」という嫌疑を生じたが,1月4日の行為を最終の1回と考えて,起訴したとする。ところが,Xが公判廷で突然,「1月4日にも覚せい剤を使用したが,1月5日に覚せい剤を使用した」と自白したとするとどうなるのであろうか。この場合,検察官は,当初は,1月4日を最終使用日と考えていたわけであるが,その後,1月5日が最終使用日であるということが判明したとする。そうすると,初めから,検察官が起訴していたのは,1月5日の覚せい剤の使用であったということになるわけである。したがって,「最終1行為」と言っても,訴訟の進展に併せて,論理的にはその中身が入れ替わってしまう可能性がある。しかるに,特定があるといっても,それは非常に観念的な特定にすぎないとする批判なわけである。しかしながら,上記の説明は,あくまでも,フィクションにすぎない。というのも,現実には,客観的にいつ覚せい剤を使用したかという日時は被告人が自白しない限り明らかにならないからである。そうすると,現実にあり得るのは,「被告人の自白によって,当初1回だと思っていた覚せい剤の使用が複数回あると表面化した場合」に特定が失われてしまうのではないかという問題にすぎない。したがって,上記のように,明確に内容が入れ替わると感じられる場面は現実には多くないと考えられる。
[11] 香城説について敷衍して説明する。この見解は,非常におもしろい発想をしている。この見解の特徴は,単に,裁判所に対する審判対象が特定しているかという観点だけでなく,訴因変更の可否や一事不再理効の範囲についてまで思考をめぐらせた上での見解という点で,最終一行為説とは理論的な精緻さが異なるといえる。
まず,特定の有無という観点から考えてみよう。この点,香城説によっても,「観念的である」という批判はそのまま妥当することになる。したがって,このような観念的レベルでの特定を認めないということになれば,それは,最終一行為説でも最低一行為説でも訴因の特定はないと解することになろう。敷衍して,観念的であるということを説明すれば,上記の例と同様に,Xは,1月1日,1月4日,1月5日に覚せい剤を使用していたとする。そうすると,最低一行為説によると,検察官の訴追意思は,「1月1日,1月4日,1月5日のどれでもよいので最低1個」ということになる。問題は,これでなぜ特定がなされたといえるかであるが,訴因の機能である裁判所に審判対象を明らかにするということの実践的な意義は,「一事不再理効の及ぼす範囲を明らかにする」,「二重起訴の判断の指標を与える」という点がメインとなる。ところが,検察官が,抽象的には複数回の使用行為があり得ても,「起訴状に記載した期間の間では,1回しか起訴しません」と宣明することによって,その期間内については,一事不再理効が及ぶことになるし,期間内の他の使用行為を起訴すれば二重起訴になるという指標を裁判所に与えることになる。そうすると,裁判所としては,「起訴状に記載されている期間については,他の事実と区別する必要がなくなるので,起訴状に記載されている期間以外の犯罪と区別することができれば識別がある」ということになる。したがって,裁判所は審判対象を識別できるので,それゆえ,特定があるということになるわけである。たしかに,この見解は,検察実務でも採用されておらず,最終一行為説と比較しても,より抽象度の高い特定しかしないわけであるから,「あまりに観念的」と評価することはできると思われる。しかしながら,それでも,この最低一行為説が極めて魅力的に思えるのは,「訴因の特定・明示があるか」という論点ではなく,むしろ,訴因変更の可否を決する基本的事実の同一性があるかという判断と極めて整合的であるからである。というのも,普通に考えると,検察官が,上記でいえば,1月4日を犯行日と考え,その旨を起訴状に記載して起訴した場合に,実は,「1月5日」と自白した場合に,これを訴因変更することができるのかはなぜであるかとの説明は,最終一行為説からではなかなか難しいものがある。というのも,上の設例では,1日しか期間がずれていないわけであるが,これが例えば2週間くらいにずれが生じていると仮定するとき,「最終一行為」が2週間も移動するが,基本的事実が同一であるというのは,若干の躊躇があるところと思われる。これに対して,最低一行為説による場合,起訴状に記載された幅のある期間内の行為であれば,どの行為についても訴因変更はできるということになる。なぜなら,検察官は,その期間内では1回しか起訴しないことをすでに宣明しているので,期間内の他の使用行為との関係は,実体法併合罪の関係にあるにもかかわらず,かかる宣明の故に,非両立性基準を満たすことになり,それゆえ,基本的事実関係の同一性が認められるという論理になるからである。そして,その範囲では,一事不再理効が生じるので,仮に被告人が3回の覚せい剤を使用していても,残る2つは起訴する余地はなくなるので,被告人の利益保護という観点からもバランスが取れているということになるわけである。たしかに,最低一行為説は,「訴因の特定があるか」という見地からは,あまりに抽象度が高いので,妥当な見解とはいえないが,訴因変更の可否について判例を統一的に説明できる論理として極めて魅力的な見解といえるのである。
[12] 大澤の見解は,覚せい剤の訴因の特定・明示の説明の仕方であまり主張されない「この起訴は,被告人の尿から検出された覚せい剤の使用行為を起訴するものであるから,特定される」という論理を応用するものと考えられる。これは,白山丸事件の特定の説明の仕方と同じである。すなわち,1回の帰国に対応する出国は,論理的には1回しかあり得ないので,密出国罪の訴因は特定されているという説明である。この説明は,覚せい剤の訴因の特定・明示の説明では,あまりなされることはない。なぜなら,尿から検出された覚せい剤が複数回の使用の結果の合わさったものである可能性が十分にあるからである。そこで,考えられる複数回の使用のうち,「最終1回」を起訴する趣旨と解することもできる。しかし,この場合は,結局,いかなる行為が最終1回であるかは分からず,観念的な特定にとどまるものといえる。そこで,鑑定書の陽性反応が出た中での最低1回を起訴している趣旨と解すべきとする。そのうえで,大澤は,自説は香城説とは異なるという。というのも,香城説は,「この起訴は,被告人の尿から検出された覚せい剤の使用行為を起訴するものであるから,特定される」という論理を下敷きにしたものではないからである。この点,大澤は,香城説が「少なくとも1回」とするのでは特定がないと批判する。たしかに,起訴状記載の期間の中で少なくとも1回ということになると,特定の要素は,「検察官の訴追意思が1個しかない」という点しかない。これでは,特定として不十分であろうというものと解される。そこで,「陽性反応が出た中での最低1回を起訴している趣旨」とする。たしかに,そのように解すると,特定の契機は,「検察官の訴追意思が1個しかない」ということと,「陽性反応が出ていることから最低限これに論理的に対応する1個の覚せい剤使用行為がある」という論理の2つにより基礎付けられることになる。そして,論理的には複数回使用はあり得るわけであるが,それは,検察官の訴追裁量の行使により1個しか起訴しなかったと説明することになる,と・・・自信がないが概ね以上のようなことを言っていたように思われるが,文献があるわけではないので答案に用いるにはなお注意を要しよう。たしかに,香城説だと「検察官の訴追意思が1個しかない」という点のみを突き詰めてプッシュしていくというイメージであったが,大澤説によると,それに,陽性反応に少なくとも論理的に1回対応するものがあること,それ以外を起訴しないのは訴追裁量という論拠が加わることで,特定を肯定しやすくするという趣旨であれば首肯できないこともない。
[13] この特色からすれば,判例は,他の事実との区別ができるかが「罪となるべき事実」=「訴因」の記載の基本的な手続的要請であるとの理解に立っている。
[14] もっとも,たとえば,共謀共同正犯における共謀の日時,場所,方法,態様や共同正犯や単独犯との区別など被告人の防御にとって重要な事実について,裁判所の裁量的な求釈明に応じて検察官の釈明が現に行われ,その事実をめぐり,当事者間で攻撃防御がなされた場合には,裁判所がこの釈明内容と重要部分において異なる事実をいきなり認定することは不意打ちとなり違法というべきであろう。このような場合,裁判所には,認定しようとする事実について,被告人側に防御の機会を付与するために顕在化させ,または,訴因変更に準じた手続を検察官に促す訴訟法上の義務があると解される(法教298号72頁)